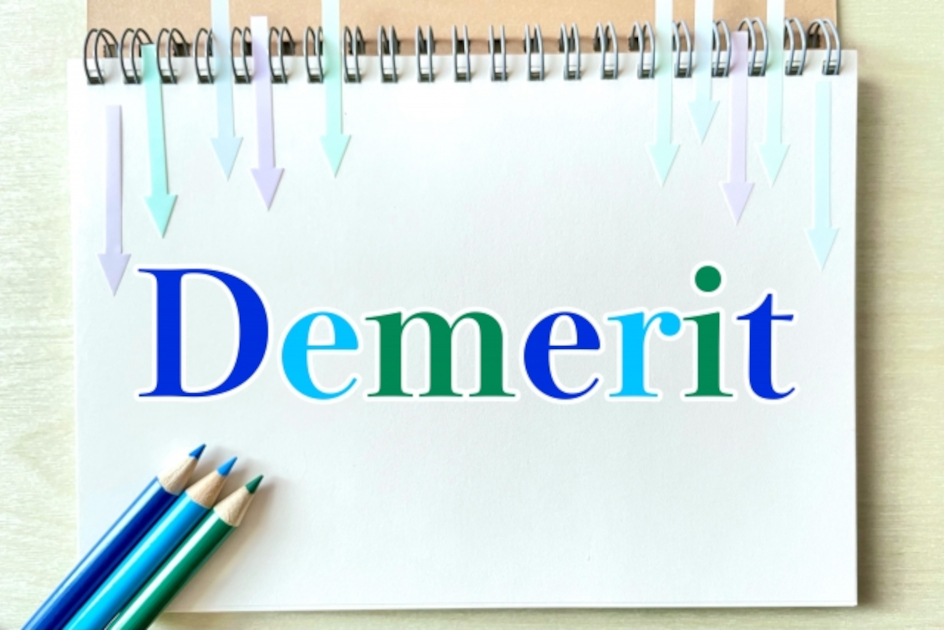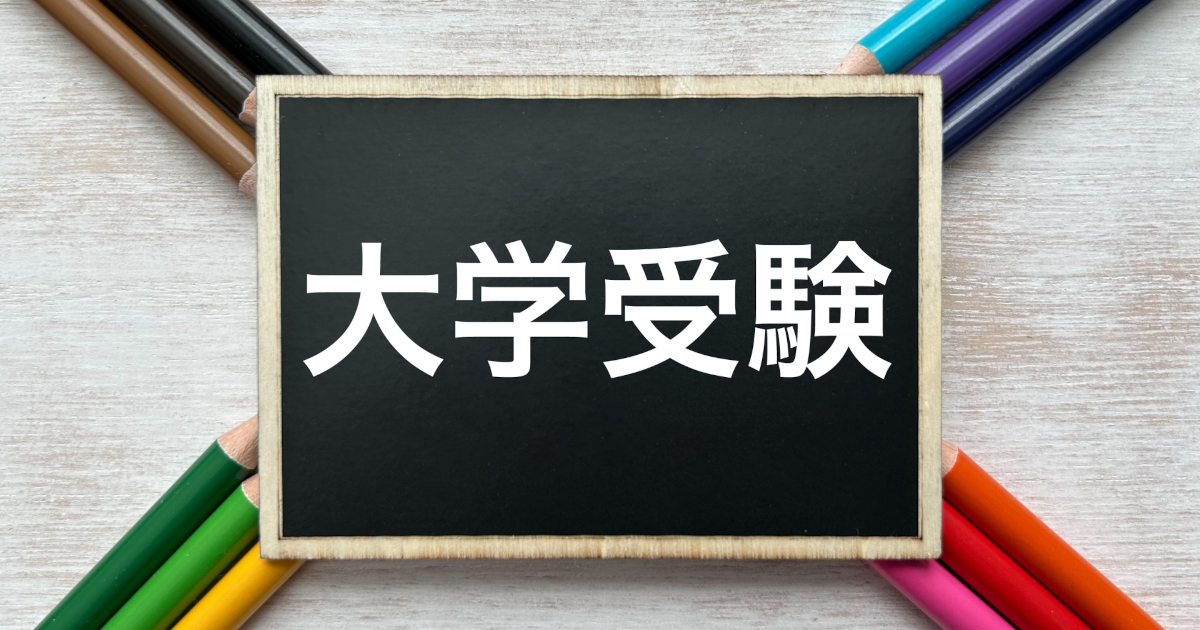こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

ゲームが好きな高校生は多く、子どもがなかなか勉強に取り組んでくれないと悩む保護者の方は多いです。
大学受験に向けて、ゲームは禁止させるべきだろうかと迷われているのではないでしょうか。
結論
ゲームを禁止すれば大学受験の勉強に前向きに取り組めるというわけではありません。
まずは大学受験を頑張る目的を探し、それからメリハリをつけてゲームと付き合っていくことが大切です。
今回は、大学受験に向けての勉強に取り組むうえでのゲームとの付き合い方について解説します。
最後まで読んでいただき、お子様がゲームと上手に付き合いながら受験勉強に取り組み、第一志望校に合格するための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団指導塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
ゲームを禁止することのデメリット
子どもが勉強に取り組まずにゲームをしている姿を見ると、ついついゲームを禁止したくなってしまうと思いますが、ゲームを禁止することにはデメリットも多いので、頭ごなしにゲームを禁止するべきではありません。
ゲームを禁止することのデメリットは、主に次の3つです。
ゲーム禁止のデメリット
デメリット1:禁止されればやりたくなる
ゲームは、禁止されると一層やりたくなってしまうものです。
特に、高校生はまだまだ反抗期である場合も多いです。
頭ごなしに禁止されれば、強い不快感を感じるでしょう。
受験勉強は子どもが一人で頑張るのではなく、学校や保護者、塾、子どもが一つのチームとなって取り組めたほうが結果が出やすいです。
頭ごなしにゲームを禁止して親子間の信頼関係が崩れてしまうと、今後の受験勉強が上手く進まなくなってしまいます。
デメリット2:他のことに時間を使うだけ
無理矢理ゲームを禁止しても、子どもは勉強に取り組みません。
テレビや動画投稿サイト、友達との遊びなど、他のことに時間を使うようになるだけです。
子どもは勉強したくないからゲームをしているわけではなく、ゲームをしたいからゲームをしています。
ゲームができなくなれば、他のしたいことをするようになります。
デメリット3:ストレスが溜まる
ゲームを禁止して、無理矢理勉強に取り組ませることに成功しても、成績を大きく伸ばすことはできません。
前向きに勉強に取り組めなければ、学力は伸びないからです。
また、ゲームを禁止されてイヤイヤ勉強に取り組んでいる子どもには、大きなストレスがかかり続けることになります。
長期戦になる大学受験の勉強では、ストレス管理はとても大切です。
上手にストレスを発散できなければ、どこかのタイミングでパッタリと勉強できなくなってしまうこともあります。
ゲームを禁止する前にすべきこと



ゲームを禁止しても勉強に取り組めるようになるわけではありませんが、このまま何も対策しないのも問題です。
難関大学に合格する高校生の中にもゲーム好きの高校生は多く、そのような子はゲームと上手に折り合いをつけていました。
ゲームと上手に折り合いをつけながら受験勉強を頑張るためには、まずやるべきことがあります。
大学受験の勉強に取り組めるようにするために、ゲームを禁止する前にすべきことは、主に次の4つです。
ゲームを禁止する前にすべきこと
対策1:勉強とゲームの両立を目指す
大学受験の勉強に取り組めるようにするためには、ゲームを禁止するのではなく、勉強とゲームの両立を目指すべきです。
スムーズに受験勉強を開始できるようにするためです。
好きなこともやりつつ、やるべきことにも取り組んでいくと、無理なく取り組むことができます。
「好きなこと」か「やるべきこと」かの二者択一にしてしまうとつらいですが、まずはバランスを取りながら両方とも選択できると良いです。
対策2:大学受験をする目的を探す(最重要)
大学受験の勉強に取り組めるようにするためには、ゲームを禁止するのではなく、大学受験をする目的を探すことが最重要です。
夢や目的がなければ、頑張り続けることは難しいからです。
子どもがゲームよりも勉強に取り組めるようにするためには、子どもの中での勉強の優先度を上げる必要があります。
保護者の方が「ゲームよりも勉強すべき」と押し付けるのでなく、子ども本人が「ゲームよりも勉強すべき」と感じなければなりません。
子ども本人が「勉強すべき」と感じるためには、将来の夢や目的を見つけ、行きたい大学や学部を見つけ、今勉強に取り組むべき理由を見つける必要があります。
高校生が一人で夢や目的を探すのは難しい
高校生はまだまだ社会に対する知識も乏しく、将来の夢や目標を自分の力だけで探すのは難しいです。
大人がサポートしてあげる必要があります。
子どもと対話しながら、一緒に将来のことを考える時間を作れると良いです。
将来のことはすぐに決められることではないので、継続的に対話していけると良いです。
将来の夢を重視している学習塾・予備校
- 東進ハイスクール・東進衛星予備校

※夢・志を育む指導を受けられる! - モチベーションアカデミア

※大学受験の先にある社会を見据えた指導!
対策3:志望校とのギャップを把握する
大学受験の勉強に取り組めるようにするためには、志望校とのギャップを把握する必要があります。
自分の立ち位置を知らなければ、やるべきことが明確にならないからです。
なかなか受験勉強に取り組まない高校生の中には、大学受験の難易度がわかっておらず、舐めプ(ゲーム用語で「相手を舐めて手抜きプレイする」という意味)している人もいます。
志望校と自分の学力とのギャップを知ることで、何にどれくらい取り組まなければならないかが見えてきて、「勉強しなければならない」という気持ちになる高校生も多いです。
大学受験向けの模試は数多く実施されているので、まずは模試に申し込んでみると良いでしょう。
▼あわせて読みたい
>>大学受験の勉強はいつから?高校受験の意識のままでは絶対に間に合わない!
対策4:入試までにやるべきことを知る
大学受験の勉強に取り組めるようにするためには、大学入試までにやるべきことを知ることが大切です。
模試を受けたら、偏差値と志望校判定を見るだけでなく、結果をしっかりと分析して、何から取り組むべきか具体的に考える必要があります。
受験勉強をはじめるときに、大学受験についてミリしら(ネット用語で「1ミリも知らない」の略)状態で、「結局何からはじめればよいのかわからない。」と、困ってしまう高校生は多いです。
模試の結果を参考にしながら、勉強の長期計画を立てることが望ましいですが、まずは今すぐ何に取り組むべきかということだけでも決められると良いです。
ゲームと勉強を両立するための工夫



受験生がゲームと勉強を両立させるためには、次のような工夫をすると良いです。
ゲームと勉強を両立するための工夫
工夫1:ルールを決める
ゲームと勉強を両立させるためには、ルールを決めることが大切です。
ルールを決めると、自分の行動や感情をコントロールしやすいからです。
どのようなルールを作れば勉強に取り組めるか、子ども自身が考え、子ども自身が決めることが大切です。
誰かに押し付けられたルールでは反抗したくなってしまいますが、自分で考えて納得したルールであれば守れるからです。
たとえば、次のようなことをルール化すると有意義です。
ゲームと勉強を両立させるためのルール
- ゲームをして良い時間を決めて固定する
- ゲームをする場所を決める(誰かに見られている場所が好ましい)
- ゲーム機を自室に置かない
- 先に勉強に取り組み、ゲームは勉強のあとにする
作ったルールは書き出して、目に入るところに貼り出しておけると良いです。
工夫2:スマホはホーム画面を切り替える
可能であればスマートフォンも自分の部屋ではない場所に置いておくと良いですが、現代の勉強ではスマートフォンを活用する場面も多いです。
スマートフォンのゲームをプレイする高校生も多く、スマートフォンは専用のゲーム機よりも工夫してルールを決める必要があります。
たとえば、スマートフォンを使わない勉強に取り組むときは家族に預けておき、必要になったら返却するというルールを作ると良いです。
また、ホーム画面を「勉強用」と「ゲーム用」に分けておき、勉強するときは勉強用のホーム画面だけを使うようにすると良いです。
工夫3:自習室を利用する
ゲームと勉強を両立するためには、学習塾や予備校の自習室を利用すると効果的です。
自習室で勉強している間は、ゲームから完全に離れることができるからです。
ルールをしっかりと決めたとしても、ゲームができる環境下であれば、ついついゲームに手が伸びてしまうときもあります。
一方で、勉強する環境を整えてしまえば、ゲームをしたいと思ったときでも勉強し続けることができます。
ルールを作ることも重要なのですが、環境を作ることも重要です。
実際に、自習室を使いたいがために塾や予備校に入学する高校生も多いです。
仲間の頑張る姿が背中を押してくれる
塾や予備校の自習室は、頑張っている仲間の姿が見えるのも大きなメリットです。
仲間が頑張っている姿を見ると、「自分ももう少し頑張ってみよう。」と思うことができ、自然と努力量を増やすことができます。
受験は個人個人で頑張るものではありますが、仲間の存在はとても大きいです。
▼あわせて読みたい
>>大学受験対策は塾に行くべき!メリットや選び方のポイントを解説!
ゲームをやめられるならやめたほうが良い
ゲームがどんなに好きであっても、状況によっては一旦ゲームから離れる必要がある場合も多いです。
私の過去の生徒も、高校3年生の夏頃を目安に、ゲームを封印する場合が多かったです。
一方で、入試直前期であっても、気分転換にゲームをプレイする生徒もいました。
両者の違いは、休憩時間に何を優先するかという点です。
入試が近づくにつれて、自由に使える時間は少なくなっていきますので、その自由時間をどのように使いたいかで判断できると良いです。
多くの受験生は、自由時間を友だちと話す時間に当てていました。
友だちと話すことで、勉強のストレスを解消したり、勉強の悩みを相談したり、お互いに励まし合ったりできるからです。
子どもが「一旦ゲームを封印したい」と言うようであれば、保護者の方は次のようにすると良いでしょう。
ゲームを封印するなら
ゲームアプリを削除させる
ゲームを一旦封印するのであれば、スマートフォンからゲームアプリを削除してしまうと良いです。
私の過去の生徒も、入試直前期にゲームアプリを削除する生徒が多かったです。
SNSアプリも削除している生徒が多かったです。
再開するときのために、ゲームデータやアカウント情報の管理に気をつけつつも、思い切ってアプリを削除してしまうと良いです。
ゲーム機を預かる
普段ゲーム機を使ってゲームをプレイしているようであれば、ゲーム機本体を預かってしまうと良いです。
可能であれば、本人の目に入らないところにしまってしまうと良いです。
目に入らなければ、最初のうちはゲームをやりたくなるかもしれませんが、いずれその衝動も小さくなっていきます。
なお、ゲーム機を子どもから取り上げても意味はないので、必ず本人との合意のもとに預かるようにしてください。
まとめ
それでは、大学受験に向けての勉強に取り組むうえでのゲームとの付き合い方についての解説をまとめます。
結論
ゲームを禁止すれば大学受験の勉強に前向きに取り組めるというわけではありません。
まずは大学受験を頑張る目的を探し、それからメリハリをつけてゲームと付き合っていくことが大切です。
ゲームを禁止することにはデメリットも多いので、頭ごなしにゲームを禁止するべきではありません。
ゲーム禁止のデメリット
大学受験の勉強に取り組めるようにするために、ゲームを禁止する前にすべきことは、主に次の4つです。
ゲームを禁止する前にすべきこと
受験生がゲームと勉強を両立させるためには、次のような工夫をすると良いです。
ゲームと勉強を両立するための工夫
子どもが「一旦ゲームを封印したい」と言うようであれば、保護者の方は次のようにすると良いでしょう。
ゲームを封印するなら
今回はの記事が、お子様がゲームと上手に付き合いながら受験勉強に取り組み、第一志望校に合格するきっかけとなればとてもうれしいです。
大学受験対策におすすめの予備校
- 東進ハイスクール・東進衛星予備校

※実力講師によるIT授業!AI演習も充実! - 全科目指導で第一志望合格【難関大受験専門塾 現論会】

※全科目定額制!スタディサプリ講師陣監修! - 駿台予備学校
※臨場感あふれるライブ授業!オンライン配信も!
-

-
大学受験対策は塾に行くべき!メリットや選び方のポイントを解説!
続きを見る