こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。


音楽を聴きながら勉強をする子どもは多いです。
ながら勉強は良くないという話もよく聞きますが、音楽を聴いていた方が勉強がはかどるという子どもも多く、何が正解なのかわからなくなってしまっているのではないでしょうか。
結論
勉強中に音楽を聴くのはやめさせるべきですが、いきなり禁止してしまうのは良くありません。
子どもと話し合いながら、音楽との上手な付き合い方を考えていくべきです。
今回は、音楽を聴きながら勉強することについて解説します。
最後まで読んでいただき、お子様が今よりも集中して勉強に取り組めるようにするための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
勉強中に音楽を聴くのをやめさせるべき理由

勉強中に音楽を聴くべきではない理由は2つあります。
勉強中に音楽を聴くのをやめさせるべき2つの理由
一つひとつ解説します。
理由1 勉強に集中できない

勉強中に音楽を聞くべきではないのは、ながら勉強は集中できないからです。
あまり大規模な実験が行われていないので確かな証拠とはならないかもしれませんが、音楽と集中力に関する実験は過去に行われています。
4桁÷2桁の計算を、好みの音楽を聴きながら取り組んだ場合と、静かな環境下で取り組んだ場合とでどのような違いがあるかを確かめる実験です。
掲載された論文には、以下のような考察が記載されています。
遂行数の比較から,音楽環境が計算遂行の妨げとなっていることが示唆された。この結果は単純情報処理作業時の結果(島貫ら,2017)と同様のものであった。これは計算課題における課題の難易度が,BGMに影響しないことを示している。 以上のことから,課題の難易度に関係なく,「静穏環境が学習環境に適している」ことが暫定的に示唆された。
引用:井上果林, et al. 好みの音楽は計算能力を向上させるのか~ 非単純情報処理作業に注目して~. 北海道心理学研究, 2020, 42: 42-42.
この実験からは、音楽を聴きながら勉強に取り組むよりも、静かな環境下で勉強した方が良いということがわかります。
音楽の種類も関係ない
音楽の種類やジャンルに関係なく、勉強中に音楽を聴くと集中力が下がります。
勉強する時に聴くと良い音楽としてよく言われているものには、以下のようなものがあります。
勉強する時に良いとされている音楽
- 歌詞がないもの
- クラシック音楽
- ヒーリングミュージック
- 風の音や水の音などの環境音楽
音楽の種類についても実験が行われています。
4桁÷2桁の計算中に、イヤホン、ヘッドホン、スピーカーから雑音を流し、各サウンドデバイスでの解いた問題数と誤答数を比べる実験です。
雑音は、せせらぎの音と雨の音の2種類を用意して実験しています。
掲載された論文には、以下のような考察が記載されています。
サウンドデバイスの違いによる,知的作業に与える影響の差異,雑音の違いによる影響の差異はともに有意差は得られなかったが,差異がある可能性を否定できない結果となった.また,作業効率の面では,無音が最も望ましい条件であるという結果となった.
引用:NIIYAMA, Rei; KANNO, Yoshihiro. 雑音が知的作業に与える影響のサウンドデバイス間の違いについて.
この実験から、サウンドデバイスや音の種類に関係なく、無音状態が一番作業効率が良いということがわかります。
勉強ができる生徒は勉強中に音楽を聴かない
ここからは長年塾で働いていた私の感覚的な話をします。
実験データや統計的裏付けがあるわけではありません。
偏差値60以上の難関校に合格するような生徒は、勉強中に音楽を聴く生徒はほとんどいませんでした(少しはいました)。
音楽を聴いた方が勉強に集中できると主張する生徒は、勉強が苦手である生徒が多かったです(全員ではありません)。
「音楽を聴くと集中できる」と勘違いする理由
それでは、なぜ子どもたちは「音楽を聴くと集中できる」と勘違いしてしまうのでしょうか。
理由は2つ考えられます。
音楽を聴くと集中できると勘違いする理由
理由1:『勉強』ではなく『作業』をしている
「音楽を聞くと集中できる」と勘違いしている子どもは、『勉強』ではなく『作業』をしてしまっている可能性が高いです。
たとえば、英単語を覚えるのではなく、英単語を10回ずつ書いてるだけかもしれません。
問題を解けるようにするのではなく、ただ問題集を解いて丸付けをしているだけかもしれません。
出された宿題を、ただの作業として終わらせているだけかもしれません。
音楽を聴いていると楽しいですし、気が紛れます。
楽しいうちに『作業』が終わるので、時間が速く進んだように感じます。
この感覚を、「集中して勉強に取り組めた」と勘違いしてしまっている子どもは多いです。
▼あわせて読みたい
>>勉強がわからないときは勉強のやり方を変えるべき!勉強の苦手克服法!
理由2:周りの環境から遮断されているように感じる
音楽を聴いていれば、当然周りの音は聞こえなくなります。
そうすると、自分が周りの環境から遮断されて、自分の中だけの世界に入った感覚を得ることができます。
しかし、これは錯覚です。
音楽の力に頼らずに自分の中だけの世界に入ることを、『集中する』と言います。
理由2 テスト中は音楽を聴けない
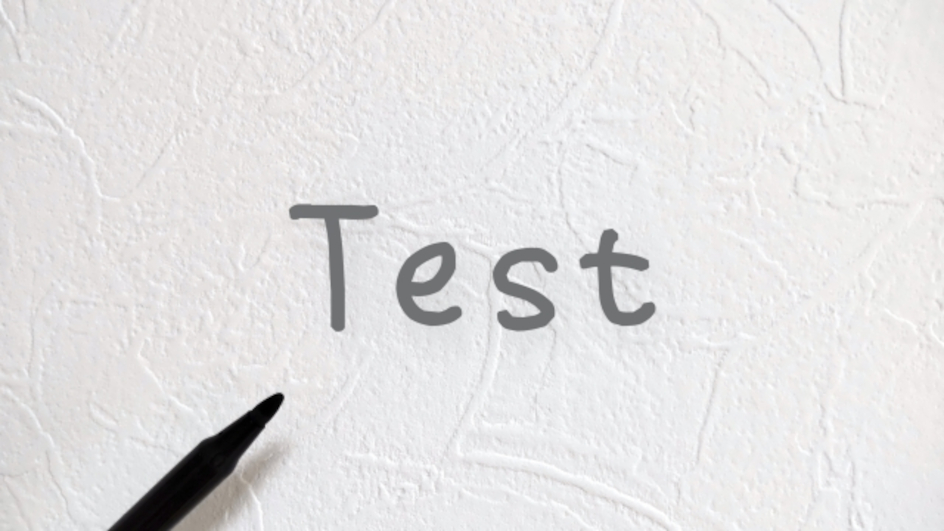
勉強中に音楽を聴くべきではないのは、テスト中に音楽を聴くことができないからです。
テスト中に音楽を聴くことができないのであれば、勉強中も音楽を聴くべきではありません。
なるべく本番に近い条件で勉強に取り組んだほうが効果的だからです。
▼あわせて読みたい
>>定期テストで点数を取れない子の特徴と改善策!今日からできる見直しリスト
▼あわせて読みたい
>>定期テストではできるのに模試の点数が取れない!たった1つの理由と3つの対策
勉強中に音楽を聴くことは悪いことだけではない

では、勉強中に音楽を聴くことは100%悪かというと、そういうわけではありません。
先ほど紹介した2つの論文についてですが、無音状態の方が学習環境に適していると結論付けていますが、差異はそれほど大きくなかったとも記述されています。
音楽を聴きながら勉強することのメリットが、音楽を聴きながら勉強することのデメリットを上回るようであれば、音楽を活用すべきだということです。
勉強中に音楽を聴くメリットは、主に次の2つです。
勉強中に音楽を聴くメリット
一つひとつ解説します。
メリット1:不快な雑音をシャットアウトできる

塾の自習室を当然のように使える場合はあまり気が付かないかもしれませんが、静かな勉強環境というのは実はかなり貴重です。
私が教室長を務めていたときも、自習室を求めて塾に入塾する生徒は多かったです。
否応なく音がする環境であれば、不快な雑音よりも音楽の方が良いです。
音楽を聴くことで周りの不快な雑音をシャットアウトできるようであれば、音楽を聴きながら勉強するのもアリでしょう。
▼あわせて読みたい
>>【元塾教室長の本音】自習室目当てで塾に通うのはアリか
-

-
【元塾教室長の本音】自習室目当てで塾に通うのはアリか
続きを見る
自分にとって意味を成さない音であるべき
勉強中に音楽を聴くのであれば、やはり歌詞がない音楽が良いでしょう。
洋楽なら問題ありませんが、バリバリに歌詞が聞き取れてしまう場合はおすすめしません。
音楽を本格的に勉強している場合は、水の音や鳥のさえずりなどの環境音楽をおすすめします。
人は、自分にとって意味を成す音を聴くと、途端に他の作業に集中できなくなります。
意味のない雑音はあまり気になりませんが、人の会話は小さな音でも気になってしまうのと同じ原理です。
メリット2:やる気がアップする

好きな音楽を聴くと気分が盛り上がります。
何か行動をしようと思った時に、音楽は背中を押してくれます。

この用に思った時も、好きな音楽を聴くと、

と、思えます。
音楽はやる気を引き出してくれるクスリになることも多いです。
子どもから音楽を取り上げてはいけない




頭ごなしに子どもから音楽を取り上げてはいけない理由は、主に次の3つです。
頭ごなしに子どもから音楽を取り上げてはいけない理由
理由1:全集中することだけが勉強ではない
常に全集中で勉強に取り組めることは理想ではありますが、現実はそうはいきません。
ときには全然やる気が出ない時もありますし、上手く勉強の世界に入り込めない日もあります。
そんな時は、勉強を放り出してしまうのも良いでしょう。
一方で、音楽を聴きながらだましだまし勉強に取り組んでみるのも良いでしょう。
理由2:子ども自身が納得しなければ意味がない
ルールや決まり事は、頭ごなしに押しつけても意味がありません。
「勉強中には音楽を聴かない」というルールを作るのであれば、ルールを作る意味を子ども自身が納得する必要があります。
子どもとよく話し合ってルールを作り、運用していく中で柔軟にルールを変えていく必要があります。
子ども自身がルールに納得しなければ、問題点が別の形で浮上し続けます。
音楽がダメならテレビ、テレビがダメならYou Tube、You TubeがダメならSNSと、ただただ形を変えてイタチごっことなってしまいます。
理由3:音楽を聴くことのメリットもある
先ほど解説したとおり、勉強中に音楽を聴くことにはメリットもあります。
音楽を聞くことのメリットも活用しながら、音楽と勉強のバランスを上手に取ることができれば理想的です。
勉強と音楽のバランスを取らせるために

それでは、どのように勉強と音楽のバランスを取ればよいでしょうか。
例として、2つのアイデアを紹介します。
勉強と音楽のバランスを取るためのアイデア
アイデア1:最初は半々を目指す
勉強中にずっと音楽を聴いている子どもは、「集中して勉強に取り組む」ということの意味がわかっていない可能性があります。
宿題などのノルマをこなすことが勉強だと思っていて、物事を理解することの意味がわかっていない可能性があります。
その状態からいきなり音楽をすべて禁止するのは難しいでしょう。
まずは、

と、提案してみてください。
反抗期真っ盛り!
お子様が中学生や高校生であれば、反抗期真っ盛りかもしれません。
たとえ言うことを聞かなかったとしても、頭ごなしにルールを押しつけないようにしてください。
子どもは反抗しながらも、自分が納得したことには素直に取り組みます。
試しに音楽なしで勉強に取り組んでみた結果、テストで良い点数を取れたり、「いつもより集中できた」という実感を持てれば、音楽を聴きながら勉強する時間を少しずつ減らしていくはずです。
子どもが聞く耳を持たなかったとしても、時期を見て何度か提案してみてください。
アイデア2:勉強スタート時だけ音楽を聴く
勉強は取り組みはじめる時に一番エネルギーを使います。
一番エネルギーを使う勉強スタート時に音楽を活用し、勉強に取り組みはじめることができたら音楽を止めて、勉強に集中すると良いでしょう。
取り組みはじめてしまえば、あまりエネルギーを使わずに勉強を続けることができます。
勉強に取り組みはじめる時に音楽の力を借りると良いでしょう。
好きな音楽はやる気をアップさせてくれます。
まとめ
それでは、音楽を聴きながら勉強することについての解説をまとめます。
結論
勉強中に音楽を聴くのはやめさせるべきですが、いきなり禁止してしまうのは良くありません。
子どもと話し合いながら、音楽との上手な付き合い方を考えていくべきです。
勉強中に音楽を聴くべきではない理由は2つあります。
勉強中に音楽を聴くのをやめさせるべき2つの理由
勉強中に音楽を聴くことには、メリットもあります。
勉強中に音楽を聴くメリット
頭ごなしに子どもから音楽を取り上げてはいけません。
頭ごなしに子どもから音楽を取り上げてはいけない理由
勉強と音楽のバランスを取る例を2つ紹介しました。
勉強と音楽のバランスを取るためのアイデア
私のプロフィールにも書きましたが、私は音楽ガチ勢です。
音楽を愛して止みません。
そんな私も、音楽との付き合い方についてはずっと考え続けました。
音楽とは正しく付き合うことが大切です。
今回の記事が、お子様が今よりも集中して勉強に取り組めるようになるきっかけとなればとてもうれしいです。
-

-
【元塾教室長の本音】自習室目当てで塾に通うのはアリか
続きを見る






