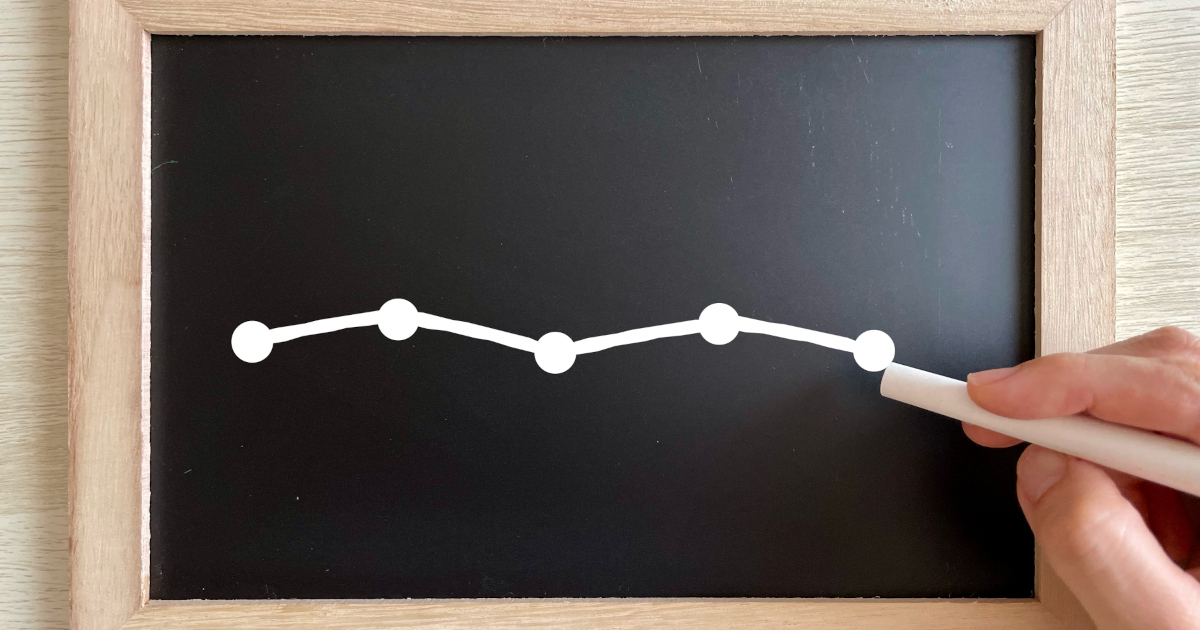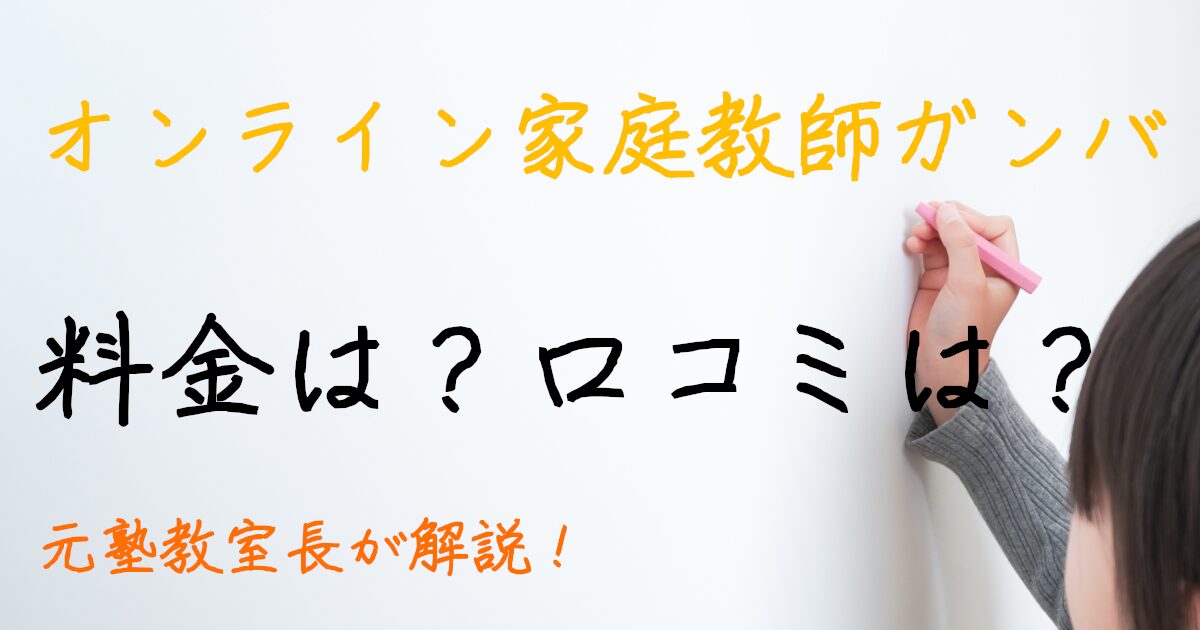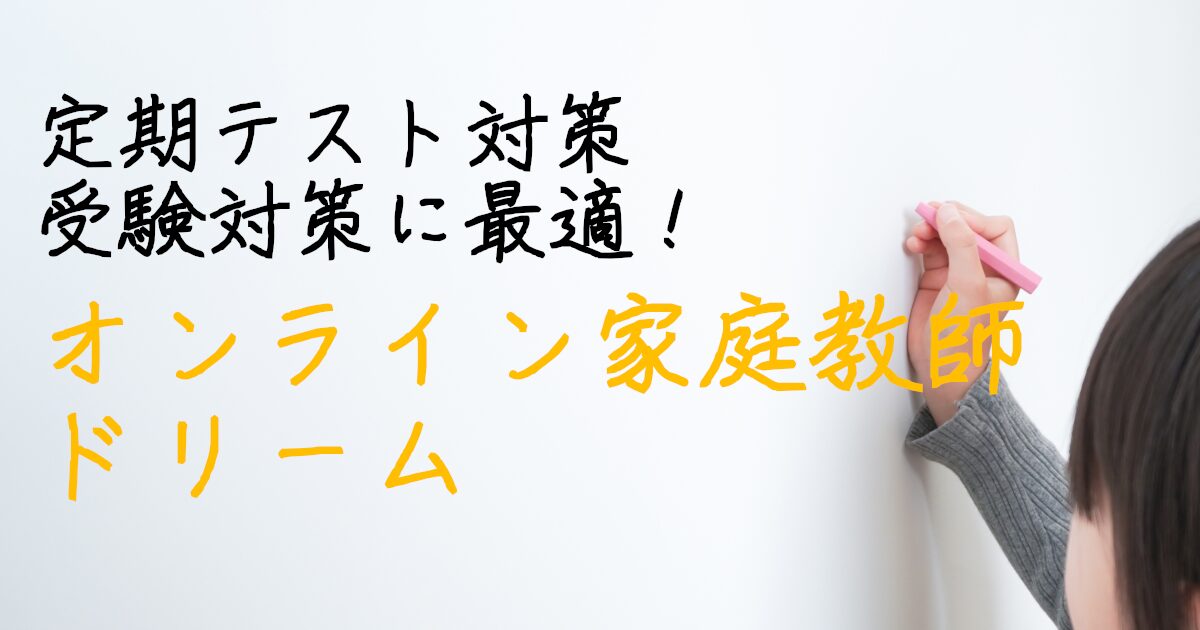こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

勉強には取り組んでいるのにも関わらず、定期テストで点数が取れないと悩む中学生は多いです。
保護者の方としても、どのようにすれば点数を取れるようになるのかと、心配されているのではないでしょうか。
結論
間違った勉強法に取り組んで、勉強をした気になっているだけの子どもは多いです。
意識と取り組み方を変えなければ、定期テストの点数はずっと上がりません。
今回は、子どもが定期テストで点数を取れない理由と、その対処法を解説します。
中学生を対象に解説していきますが、高校生も参考にしていただけます。
最後まで読んでいただき、お子様が正しい勉強法で勉強に取り組み、定期テストの点数を大きく伸ばしていくための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
定期テストで点数を取れない理由
定期テストで点数を取れない理由は、主に次の3つです。
定期テストで点数を取れない理由
理由1:勉強時間が足りない
定期テストで点数を取れない理由として一番多いのは、勉強時間が足りないということです。
勉強は、まずは勉強時間と勉強量が大切だからです。
勉強の質と効率を考えるのは、勉強時間を確保してからです。
定期テストで点数を取れないと悩む中学生・高校生の多くは、勉強時間を増やすだけで点数を取れるようになります。
定期テスト1週間前は1日4~5時間
定期テスト対策の勉強は、定期テストの3週間前から取り組みはじめるのが一般的です。
定期テストの1週間前であれば、平日は1日に4時間~5時間、休日は1日に10時間~12時間というのが勉強時間の目安です。
最低でも、平日は1日3時間、休日は1日8時間は必要です。
それよりも勉強時間が短い場合は勉強不足です。
▼この表は横にスクロールできます。
| 平日 | 休日 | |
| 最低勉強時間 | 3時間 | 8時間 |
| 目標勉強時間 | 5時間 | 12時間 |
理由2:勉強ではなく作業をしている
勉強が苦手な子どもは、自分では勉強に取り組んでいるつもりであっても、実は作業をしているだけという場合が多いです。
小学校のときに、自主的に勉強に取り組んだ経験が少ないためです。
小学校のときは、言われたことに取り組むような、受動的な勉強が多かったと思います。
それが、中学になった途端に、定期テストで良い点数を取るために自主的に勉強に取り組まなければならなくなります。
それにも関わらず、正しい勉強方法がわからずに、小学生の時と同じように、出された課題を解いて丸付けするだけの作業に取り組んでしまう中学生は多いです。
効果がない勉強
- すべて同じ回数ずつ書くような書き取り練習
- カラフルできれいなノート作り
- 解いて丸付けするだけの問題演習
理由3:テストを受けっぱなしにしている

定期テストで点数を取れない子どもほど、テストを受けっぱなしにしてしまいます。
テストを受けたあとの勉強を大切にできる子どもほど、成績は伸びやすいです。
できなかったことをできるようにすることが勉強だからです。
定期テストの結果は、次の定期テストで点数を取るための貴重なデータです。
そのような貴重なデータをポイポイ捨ててしまっているようでは、定期テストの点数を取れるようにはなりません。
定期テストで点数を取れないときの対処法
ここからは、定期テストで点数を取れないときの具体的な対処法を8つ解説していきます。
定期テストで点数を取れないときの対処法
対処法1:基礎基本だけを徹底する
定期テストで点数を取れないときは、基礎基本だけを徹底して定着させることを意識して勉強に取り組むことが大切です。
学校の定期テストは、基礎基本をしっかりと理解できていれば、80点以上取れるように作られているからです。
発展問題や応用問題は、定期テストで80点を取れるようになるまでは取り組む必要はありません。
応用問題で悩んで無駄な時間を使うよりも、基礎基本の問題を何周も解いて、徹底的に固めたほうが効果的です。
▼あわせて読みたい
>>中学校の定期テストで400点を目指す!学年上位に入るための勉強法と教科別対策
▼あわせて読みたい
>>中学校の定期テスト平均点は?確実に超えるための勉強法と教科別対策
対処法2:暗記は毎日コツコツ取り組む
漢字や英単語などの基礎暗記は、毎日コツコツ取り組み続けることが大切です。
基礎暗記は、覚えたり忘れたり思い出したりを何度も繰り返すことで定着していくからです。
歯磨きと同じように毎日の習慣としてしまい、コツコツと積み上げていけると良いです。
▼あわせて読みたい
>>効率的な暗記方法!長期記憶にするための19のコツ【元塾教室長が解説!】
対処法3:普段の授業の予習復習をする
定期テストで点数を取れないときは、普段の授業の予習・復習に取り組むことがとても大切です。
勉強の基本は、一つひとつの授業の内容をしっかりと理解してくことだからです。
勉強は、同じ内容に繰り返し取り組むことで定着していきます。
「予習→学校の授業→復習」と、短期間の間に同じ学習内容に繰り返し取り組むことで、授業内容を定着させることができます。
普段の勉強を一つひとつ定着させていけば、学習内容をある程度完成させた状態で定期テスト前の勉強に取り組むことができます。
余分な復習に時間を取られずに定期テスト対策に集中できるので、スムーズに準備を進めることができます。
学習習慣が大事
定期テストで点数を取れる子どもほど、普段から習慣的に勉強に取り組めています。
まずは、1日30分からでも良いです。
毎日の学習習慣を身につけていくことが大切です。
対処法4:丸付けをしたあとの勉強を意識する
定期テストで点数を取れるようにするためには、丸付けをした後の勉強を大切にできるようにする必要があります。
丸付けをしたあとが本当の勉強だからです。
問題を解いて丸付けを終えた状態は、「できること」と「できないこと」を選別した状態に過ぎません。
丸付けをして見つけた「できないこと」を、できるようにすることが本当の勉強です。
「できない」ことを「できるようにする」ことを意識しながら問題演習に取り組むことができると、成績を大きく伸ばすことができます。
問題演習に取り組むときのポイントは、主に次の5つです。
問題演習に取り組むときのポイント
- 丸付けをした後の勉強を大切にする
- 間違えた問題は答えを書き写すだけでなく、必ず解説を読んで理解する
- 解説を読んでも理解できない場合は、教科書やノートを見て復習する
- 間違えた問題は、期間を空けてもう一度解き直す
- 自分の力だけで解けるようになるまで繰り返し解く
問題演習は、たくさんの問題に手を出そうとするのではなく、一つひとつの問題を、自分の力だけで解けるようになるまで何度も繰り返し解くことが大切です。
対処法5:学校のワークは最低2周する
学校ワークは、定期テスト当日までに最低2周は解きます。
定期テストでは、学校ワークからの出題が多いからです。
本気で取り組むのであれば、3周を目標にすると良いです。
学校ワークをしっかりやり込むことが、定期テストの点数アップのための近道です。
学校のワークは必ず提出する
学校ワークは、定期テスト終了後の提出課題となっていることが多いです。
必ず提出してください。
課題提出は内申点(通知表の評定)に直結しますし、高校受験では内申点が超重要だからです。
他の問題集に手を出すのは、すべての教科の学校ワークを3周解いてからにするべきです。
▼あわせて読みたい
>>高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!
対処法6:定期テストの復習と解き直しに取り組む
定期テストで点数を取れるようにするためには、定期テストが終わった後に復習と解き直しに取り組むことが重要です。
定期テストの復習に取り組んで苦手を残さないようにすると、テスト後の学校の授業をスムーズに理解できるようになるからです。
定期テストの復習に取り組むメリットは、主に次の5つです。
定期テストの復習に取り組むメリット
- 苦手を早期発見して克服できる
- 正しい勉強方法が身につく
- 次の定期テストの点数アップを狙える
- 受験対策につながる
- 入試直前期に点数を爆上げするための準備になる
テストが終わったらパーッと遊びに行きたくなってしまいますが、あと少しの頑張りが大きな成果につながります。
定期テストの復習についての詳細は、『定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント』で詳しく解説しています。
-

-
定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント
続きを見る
対処法7:定期テストの振り返りに取り組む
定期テストで点数を取れるようにするためには、定期テストの振り返りに取り組むことも大切です。
定期テストの振り返りが、次のテストの点数アップに大きく役立つからです。
定期テストの振り返りをすべき理由
- 苦手を残さないようにするため
- 正しい勉強方法を身につけるため
- 受験勉強を有利に進めるため
- 物事を改善できる力を育てるため
定期テストの振り返りに取り組むことで、テスト対策の取り組み方を毎回改善していくことができます。
「結果につながった良い勉強法」と、「結果につながらなかった良くない勉強法」を見分けることができるからです。
定期テストの振り返りについての詳細は、『定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント』で解説しています。
-

-
定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント
続きを見る
▼あわせて読みたい
>>【例文付き】定期テスト振り返りシートで差をつける!効果的な書き方と活用法
対処法8:勉強する意味を考える
定期テストで点数を取れない場合や、子どもが前向きに勉強に取り組めていない場合は、勉強することの意味を親子で一緒に考えてみると良いです。
意義や目的がなければ、前向きに取り組むことはできないからです。
子ども自身がどうありたいのか、どうなりたいのか、未来のことを一緒に考えてあげてください。
子どもが思い描く未来のために、知識や教養はどのような意味を持つのか、一緒に調べたり、話し合ったりしてみてください。
時間はかかりますが、子ども自身が「芯」となる部分を見つけることができれば、自然と前向きに勉強に取り組めるようになります。
▼あわせて読みたい
>>将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント
▼あわせて読みたい
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
定期テスト対策なら学習塾がおすすめ
定期テスト対策を取れるようにするのであれば、学習塾を利用することをおすすめします。
塾であれば、授業で勉強を教えてもらえるだけでなく、定期テストで点数を取るためのサポートもしてもらえるからです。
定期テストに向けての適切な宿題を出してもらえますし、自習室を利用することもできます。
定期テスト対策のための塾であれば、次の6つがおすすめです。
定期テスト対策におすすめの学習塾
おすすめ1:森塾
定期テスト対策には、個別指導塾『森塾』がおすすめです。
森塾では、リーズナブルな料金で定期テスト対策や学校の勉強対策に取り組めるからです。
先生1人に生徒2人までの少人数制の個別指導塾なので、問題を解くだけの授業にならずに、しっかりと解説や指導をお願いすることができます。
1科目+20点の成績保証制度があるので、安心して利用できます。
▼森塾の公式サイトはこちらから
【森塾】![]()
おすすめ2:オンライン家庭教師ガンバ
定期テスト対策には、オンライン家庭教師『ガンバ』がおすすめです。
ガンバでは、勉強の仕方やノートの取り方から、丁寧に指導してもらえるからです。
1週間の授業回数が多いほうがお得になる料金システムになっているため、週2コマや週3コマのマンツーマン授業を、料金を安く抑えて利用することができます。
予習復習計画帳を使って講師といっしょに学習計画を立てながら取り組むので、計画的に勉強に取り組む練習をすることもできます。
▼オンライン家庭教師ガンバの公式サイトはこちらから
>>オンライン家庭教師ガンバ![]()
オンライン家庭教師ガンバについては、『オンライン家庭教師ガンバは勉強が苦手な子どもの味方!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。
-

-
【2025年版】オンライン家庭教師ガンバは勉強が苦手な子どもの味方!料金・口コミは?
続きを見る
おすすめ3:個別教室のトライ
定期テスト対策には、『個別教室のトライ』がおすすめです。
個別教室のトライでは、完全マンツーマン授業で苦手対策に取り組むことができるからです。
専任講師と教育プランナーが、一人ひとりに合わせたカリキュラムを作るので、現状の学力に合った授業計画を立ててもらうことができます。
▼個別教室のトライの公式サイトはこちらから
【個別教室のトライ】![]()
おすすめ4:明光義塾
定期テスト対策には、個別指導塾『明光義塾』がおすすめです。
明光義塾では、10段階学習法で、子どもの現状の成績に応じた、最適な指導を受けることができるからです。
授業では、学習内容を子どもが自分の言葉で説明するので、しっかりと理解できているかどうかを確認しながら学習を進めることができます。
教室が多く、家の近くにあることも多いので、便利に利用することができます。
▼明光義塾の公式サイトはこちらから
個別指導の明光義塾![]()
おすすめ5:中高一貫校専門 個別指導塾WAYS
定期テスト対策には、中高一貫校専門個別指導塾『個別指導塾WAYS』がおすすめです。
個別指導塾WAYSでは、「長時間指導」と「塾内完結」で、勉強の量と質を確保することができるからです。
中高一貫校専門の塾なので、特に「中だるみしてしまっている」と感じているご家庭におすすめです。
低料金で長時間指導を受けられることも大きなメリットです。
▼個別指導塾WAYSの公式サイトはこちらから
中高一貫校専門 個別指導塾WAYS![]()
おすすめ6:オンライン家庭教師ドリーム
定期テスト対策には、オンライン家庭教師『ドリーム』がおすすめです。
オンライン家庭教師ドリームには、普段からの学習習慣を身につけられる仕組みがあるからです。
宿題が毎日細かく設定されて、写真で提出するので、日々の勉強に取り組みやすく、学習習慣を身につけやすいです。
24時間いつでもLINEで質問することもできるので、普段の勉強に取り組みやすい仕組みが整っています。
1科目+20点の成績保証制度があるので、安心して利用できます。
▼オンライン家庭教師ドリームの公式サイトはこちらから
>>オンライン家庭教師ドリーム
オンライン家庭教師ドリームについての詳細は、『オンライン家庭教師ドリームは定期テスト対策と受験勉強に最適!メリット・デメリットや料金は?』で解説しています。
-

-
【2025年版】オンライン家庭教師ドリームは定期テスト対策と受験勉強に最適!メリット・デメリットや料金は?
続きを見る
-

-
オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】
続きを見る
今後の定期テストで点数を伸ばしていくための対策
中学校の定期テストでは、現状の成績に関係なく、正しく努力をすることで点数を伸ばしていくことができます。
正しい努力の仕方を知り、実践していくことが大切です。
中学生の定期テスト対策については、『中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド』に詳しくまとめてあります。
ぜひチェックして、定期テストの成績アップを目指してください。
-

-
中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド
続きを見る
まとめ
それでは、子どもが定期テストで点数を取れない理由と、その対処法についての解説をまとめます。
結論
間違った勉強法に取り組んで、勉強をした気になっているだけの子どもは多いです。
意識と取り組み方を変えなければ、定期テストの点数はずっと上がりません。
定期テストで点数を取れない理由は、主に次の3つです。
定期テストで点数を取れない理由
定期テストで点数を取れないときの具体的な対処法は、主に次の8つです。
定期テストで点数を取れないときの対処法
定期テスト対策のための塾であれば、次の6つがおすすめです。
定期テスト対策におすすめの学習塾
今回の記事が、お子様が正しい勉強法で勉強に取り組み、定期テストの点数を大きく伸ばすきっかけとなればとてもうれしいです。
-

-
中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド
続きを見る
-

-
【2025年版】オンライン家庭教師ガンバは勉強が苦手な子どもの味方!料金・口コミは?
続きを見る
-

-
【2025年版】オンライン家庭教師ドリームは定期テスト対策と受験勉強に最適!メリット・デメリットや料金は?
続きを見る
-

-
オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】
続きを見る