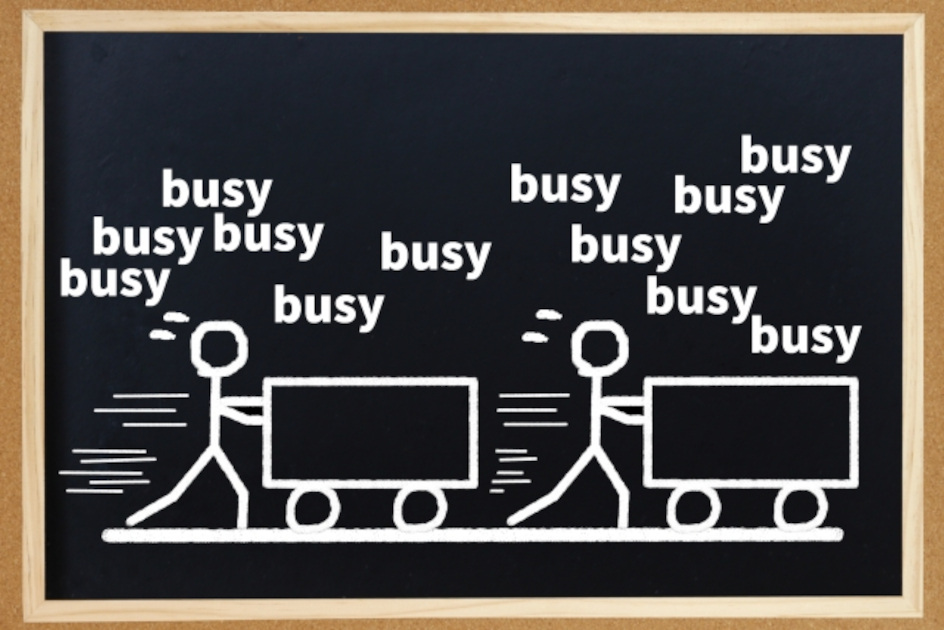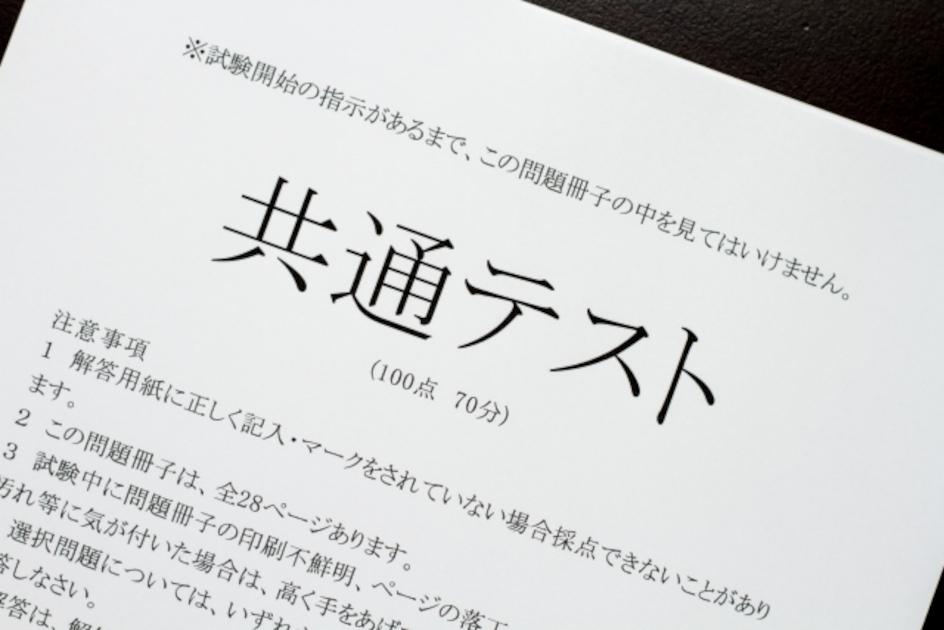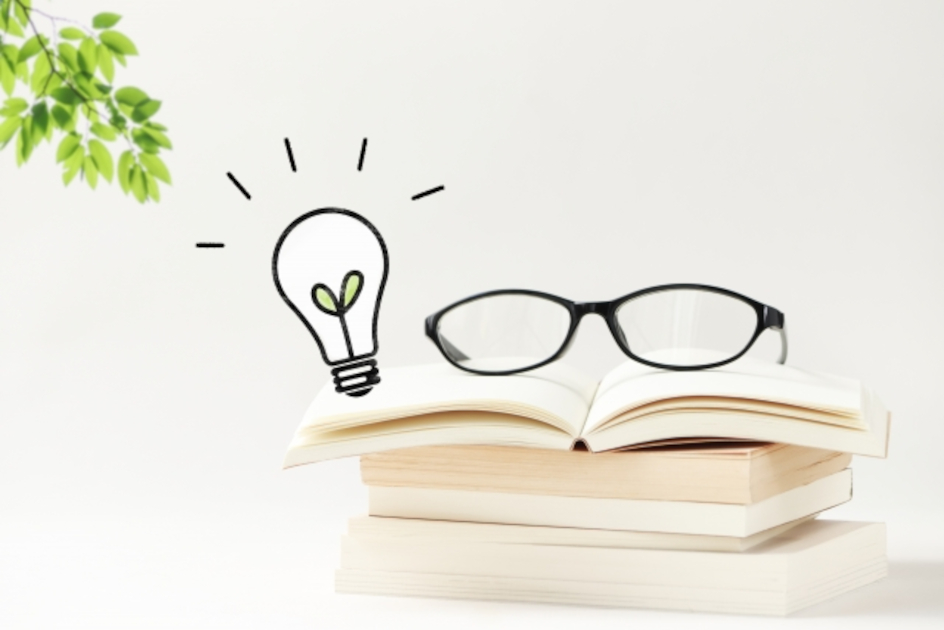こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。


第一志望の大学は決められても、その他の受験校をよく考えていない受験生は多いです。
子どもが適当に受験校を決めてしまっているようで、本当に大丈夫だろうかと不安になってしまいますよね。
大学入試の仕組みは複雑で難しいと感じられているかもしれません。
結論
大学受験の難易度は、高校受験とはレベルが違います。
大学受験を成功させるためには、併願校を含め、受験する大学をよく考えて戦略的に決めるべきです。
今回は、大学受験の併願校戦略についての6つのポイントを解説します。
最後まで読んでいただき、お子様が戦略的に受験校を決定し、大学受験を成功させるための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ (@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
併願とは
受験では、第一志望校の他にも、併願校を受験するのが一般的です。
併願とは、第一志望の学校に不合格になってしまったときに備え、複数の学校を受験することを指します。
高校受験では、第一志望校の他に、1つか2つ併願校を受験した場合が多いと思います。
しかし、高校受験と同じような感覚で大学受験の併願校を考えると失敗します。
大学受験では、併願校戦略は超大事です。
大学受験は高校受験と同じように考えると失敗する



高校受験と同じように大学受験を戦おうとすると失敗します。
その理由は、主に2つあります。
理由1:倍率が高い
大学受験の志願倍率は、高校受験に比べて遥かに高いです。
2023年度の国公立大学全体の志願倍率は4.3倍でした。
40人受験したら、合格するのは約9人です。
他の約31人は不合格です。
2022年の早稲田大学商学部の一般選抜の倍率は9.3倍でした。
40人受験したら、合格するのは約4人です。
他の36人は不合格です。
高校受験と違い、合格する人数よりも不合格になる人数のほうが遥かに多い試験です。
高校受験のときと同じような戦略で戦うのは無謀です。
理由2:入試制度が複雑
大学受験の入試制度は、高校受験よりも遥かに複雑です。
制度をしっかりと理解し、有効活用することができれば有利になります。
逆に、制度のことをあまり理解しないまま、活用することできなければ不利になります。
もちろん、受験生がしっかりと努力をして学力を伸ばすことが一番大切です。
一方で、伸ばした学力を最大限活かせるよう、入試制度を活用して戦略を立てることも大切です。
大学入試の種類(時系列順)
複雑な大学入試制度ですが、まずは大まかなところから知っていけば大丈夫です。
この記事では、大学入試の種類を時系列順に簡単に解説していきます。
大学入試の種類(時系列順)
一つひとつ解説します
10月~11月:総合型選抜(旧AO入試)
大学受験の総合型選抜(旧AO入試)は、10月~11月に試験があることが多いです。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)とは異なり、高校からの推薦は必要ありません。
選抜方法は大学によって多種多様ですが、小論文や面接、プレゼンテーション、個別学力試験等が多いです。
大学によっては、大学入学共通テスト(旧センター試験)が課される場合があります。
11月~12月:学校推薦型選抜(旧推薦入試)
学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、11月~12月に試験が行われことが多いです。
試験の内容は学校ごとに異なります。
書類(調査書、志望理由書等)、小論文、面接などが課されるのが一般的です。
個別の学力試験や大学入学共通テスト(旧センター試験)が課される場合もあります。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、大きく2種類に分かれています。
学校型推薦選抜の種類
- 公募推薦
- 指定校推薦
公募推薦
公募推薦は、学校長の推薦を得て出願するタイプの学校型推薦選抜です。
通知表の評定が出願条件とされることが多いです。
指定校推薦
指定校推薦は、大学が高校を指定して推薦枠を設定するタイプの学校型推薦選抜です。
高校によって出願できる大学の枠が決まっているため、高校内の選考を勝ち抜かなければ出願することができません。
逆に、高校内での選考に通れば、入試ではほぼ確実に合格となります。
1月中旬:大学入学共通テスト(旧センター試験)
大学入学共通テスト(旧センター試験は)は、1月の中旬に行われます。
国公立大学を受験する受験生は共通テストを必ず受験しますが、私立大学の受験でも共通テストを利用することができます。
そのため、国公立大学を志望しない受験生も、多くの場合、共通テストを受験します。
1月末~2月:私立大学一般選抜
私立大学の一般選抜は、多くの場合、1月末から2月にかけて行われます。
募集枠は少ないですが、3月入試も多いです。
各大学が作成した個別試験を受けて、その点数によって合否が決められる形式の選抜方法が多いです。
ほぼすべての大学が、共通テスト(旧センター試験)の点数のみで合否を決める、共通テスト利用入試を導入しています。
また、大学の個別試験と共通テストの点数の合計で合否を決める、共通テスト併用方式の選抜方法も多いです。
英検などの英語外部試験を利用した入試を実施している大学も多いです。
私立大学一般選抜
- 個別試験
- 共通テスト利用入試
- 共通テスト併用型
- 英語学部試験利用入試
>>大学受験で英検は超有利なわけではないがきっちり取っておくべき
2月下旬~3月中旬:国公立大学一般選抜
国公立大学の一般選抜は、2月下旬から3月中旬にかけて行われます。
前期、中期、後期に分かれていて、それぞれ1校のみ受験することができます。
そのため、国公立大学は最大で3校受験することができます。
ただ、中期や後期の試験を実施していない大学も多いです。
大学入学共通テスト(旧センター試験)と、各大学が独自に作成した2次試験の合計点によって合否が決められます。
大学受験の併願校戦略の6つのポイント
大学受験は高校入試よりも遥かに難易度が高く、入試制度も複雑なため、受験する大学を戦略的に考える必要があります。
ここからは、大学入学共通テスト(旧センター試験)以降の試験においての併願校戦略について解説します。
大学受験の併願校戦略のポイントは、主に次の6つです。
大学受験の併願校戦略の6つのポイント
一つひとつ解説します。
ポイント1:数は撃とう

このような受験生もときどきいるのですが、基本的には受験する学校は多いほうが良いです。
あくまでも目安ですが、安心できる出願校数は次の通りです。
| 第一志望校 | 1校 |
| 挑戦校 | 4~5校 |
| 実力校 | 1~3校 |
| 安全校 | 1~2校 |
上の表は、あくまでも目安です。
また、同じ大学の異なる選抜方式に出願する可能性もあるので、実際にはそれほどいろいろな大学に出願するわけではありません。
私大の受験料は高額なので、予算の問題もあるでしょう。
家庭や子どもの状況にもよりますが、優先順位をつけるのであれば、「第一志望校」「安全校」「実力校」「挑戦校」の順です。
大学受験は、高校受験や中学受験のときとは異なり、進学できない可能性が大いにある入試です。
よって、安全校の優先度は高いです。
安全校は必ず受験すべき
安全校の話を生徒とすると、「その学校に行くのであれば浪人します。」という答えが返ってくることがあります。
たとえそうであっても受験すべきです。
たとえ浪人するにしても、受験した大学を全滅して浪人生になるか、1校でも合格して浪人生になるかで、次の1年間のモチベーションが大きく変わります。
一見、受験料を無駄にしているように感じるかもしれませんが、次の1年への投資だと思えば格安です。
そもそも、なぜその学校へは行きたくないのでしょう。
偏差値で判断してませんか?
もし、そうであればリサーチ不足です。
偏差値帯に関わらず、自分に合った良い大学はたくさんあります。
視野を広げてしっかりと探してみてください。
挑戦校はできるだけ厚めに
予算や受験スケジュールにもよりますが、できることなら挑戦校の出願数を多めに確保したいです。
たとえ合格確率が30%であっても、数撃てば1つは当たる可能性があります。
挑戦校ということは憧れのが大学です。
全て合格する必要はありません。
1つでも合格すれば良いです。
イメージしやすいように、次の例題を解いて、憧れの大学に合格する確率を考えてみましょう。
問題
30%の確率で勝つゲームを5回続けて、少なくとも1回勝つ確率はいくつでしょう。
解答・解説
問題文に「少なくとも」とあるので、余事象を疑いましょう。全体から、5回とも負ける確率を引きます。
1-0.7×0.7×0.7×0.7×0.7=0.831...
答え 約83%
合格確率30%の大学でも、5校受験すれば約83%の確率で1校は合格します。
もちろんこれは理論値です。
まったく手が届かない大学をどんなにたくさん受験しても合格しません。
ただ、私の肌感覚なので確かなデータではありませんが、「ここはちょっと難しいな」と思う学校を複数校受験した生徒の多くが、合格を勝ち取ってきたように感じます。
セット出願割引を活用する
出願校を増やす際に問題になること。
そう!それは受験料です!
私大の受験料は35,000円のところが多いです。
10校受ければ35万円です!
ただ、学校によってはセット出願割引を設置しています。
同じ大学の複数の試験日に出願したり、選抜方式の異なる試験に複数出願したりすると、受験料が大幅に安くなる大学も多いです。
受験料に関しては、各大学の入試要項をチェックするのが確実です。
入試要項は郵送で取り寄せずとも、ほとんどの大学がネット上に公開しています。
「学校名+入試要項」で検索してみてください。
ポイント2:安全校から受けよう
入試の日程を確認して、一番最初は安全校の試験を受けられるようにスケジュールを考えましょう。
安全校から受けると良い理由は、次の2つです。
安全校から受験する理由
- 志望度が高い学校の試験のための練習になる
- 早い時期に合格があると安心する
最初は安全校で本番のテストを経験して、本番の雰囲気に慣れてから志望度の高い大学の試験に挑めると良いです。
現役生にとっては初めての大学受験です。
いきなり志望度の高い大学から受験してしまうと、緊張して本来の力が発揮できないかもしれません。
また、なかなか合格が出ないと精神的に追い込まれます。
早い時期に1つでも合格が出ていると、その後の試験のときに過度に緊張せずに済みます。
>>試験で緊張しないための勉強法!本番に強くなるための準備と心構え
ポイント3:連続日程は避けよう
入試の連続日程は3日までにするようにしましょう。
欲張ってスケジュールを詰めすぎると、疲れが溜まって試験に集中できなくなってしまうからです。
入試は、想像以上に体力を消耗するものだからです。
試験の日は早朝に家を出て、長時間電車に揺られて会場へ向かい、試験開始の1時間前から会場入りして準備して、頭をフル回転させて試験を戦って、また長時間電車に揺られて家に帰ってきます。
体力的には3日連続が限界です。
試験中の体調の良し悪しは、試験結果に直結します。
入試カレンダーを作ってみて、4日連続試験となってしまっているものがあるようであれば、優先度の低い学校をあきらめるか、別日程の試験を受けるようにするべきです。
2月のスケジュールは過密
2月前半は、特に過密日程になりがちです。
大学入試の多くは2月に行われます。
受験校が多くなると、日程が重なってしまったり、連日試験を受けに行けなければならなかったりします。
試験日が重なってしまった場合や、4日以上の連続日程になってしまった場合は、どの大学を受験するか選ばなくてはなりません。
志望度などを考えて、受験校を取捨選択しましょう。
ポイント4:共通テスト利用を活用しよう
共通テスト利用入試は、共通テストの点数で各私立大学の合否判定が行われる仕組みです。
共通テスト利用のメリット
共通テスト利用のメリットは、主に次の2点です。
共通テスト利用のメリット
- 一般入試を受けに行く必要がない
- 一度の試験で複数の大学、複数の学部に挑戦できる
共通テスト利用の最大のメリットは、多くの大学・学部に出願できることです。
共通テストを受験するだけで良いので、各大学に試験を受けに行く必要がないからです。
日程が重なってしまうことや、日程が連続になってしまうことを気にせずに出願することができます。
共通テスト利用のデメリット
共通テスト利用のデメリットは、主に次の3点です。
共通テスト利用のデメリット
- 倍率が高く、合格ラインが高い
- 一度の試験で多くの合否を出すため、リスクがある
- 多くの大学は、共通テスト前に出願する
共通テスト利用の最大のデメリットは、合格ラインが高いということです。
共通テスト利用では、 ワンランク上の大学の個別試験入試に合格する学力が必要になります。
例えば、MARCHクラスの共通テスト利用に合格するためには、早慶クラスの個別試験入試で合格できる学力が必要になります。
そのため、共通テスト利用は挑戦校の試験には向きません。
安全校や実力校の試験として利用するのがよいでしょう
また、一度の試験で複数の大学・学部の合否を出せることはメリットでもありましたが、デメリットでもあります。
試験というものは、調子が良いときも悪いときもあります。
たまたま共通テストの結果が悪かった場合は、共通テスト利用で出願したすべての大学に影響してしまいます。
また、共通テスト利用は多くの場合、共通テストの前に出願します。
したがって、共通テストの自己採点をしてから出願することができません。
一部、共通テスト後に出願できる大学もあるので、その場合は自己採点後に出願するかどうかを決めることができます。
ポイント5:Aプラン、Bプランは事前に作ろう
共通テスト本番の自己採点が良かった時のAプランと、悪かったときのBプランを事前に作っておきましょう。
例えば、共通テストの自己採点で、得点率が〇〇%以上なら国公立はここに出願、〇〇%未満だったらここに出願と、共通テストを受ける前に決めておきましょう。
私大の共通テスト利用入試を利用するようであれば、共通テストで〇〇%以上取れていれば□□大学は合格するから、少し背伸びをしたAプランでいこうと決めておきましょう。
「事前」に決めることが大切
具体的な得点率と具体的な出願プランを、共通テストを受験する前に事前に決めておきます。
事前にAプランBプランを決めておかなければ、もし仮に共通テスト本番で力が発揮できなかった際に、その後ドタバタしてしまい、ドタバタを私大の入試本番まで引きずってしまう可能性があるからです。
逆に、しっかりと事前にAプランBプランを練っておけば、たとえ共通テストの自己採点が悪かったとしても、スムーズに軌道修正することができます。
なお、AプランとBプランのボーダーを決める際は、おおよその合格ラインを調べましょう。
おおよその合否ラインを調べる際は、「大学受験パスナビ」というサイトが便利です。
ポイント6:入学手続き締切日を意識しよう
出願プランを作る際は、合格発表日と入学手続き締切日を意識しましょう。
入学手続きの締切りが早い大学があった場合、他の大学の合格発表の前に、入学手続きをするかどうか決めなければなりません。
入学手続きは、入金まで済ませなければ完了となりません。
入学手続きの際の入金には、大きく2パターンあります。
入金のパターン
- 入学金のみ入金
- 入学金と授業料等を入金
入学金のみ入金
入学金のみ入金の場合は、入学手続きの締切日までに、20万円~30万円の入学金を支払います。
その大学に入学する場合は、2次締切日までに入学金以外を入金します。
その大学に入学しない場合は、入学金の返金はありません。
入学金と授業料等を入金
入学金と授業料等を入金の場合は、入学手続きの締切日までに、一旦100万円前後を入金することになります。
入学を辞退する場合は、後ほど入学辞退の手続きをします。
入学辞退の手続きが済むと、入学金以外が返金されます。
返金には数ヶ月かかるのが一般的です。
「事前」に決めることが大切
入学手続きの際の入金のパターンがどちらであったとしても、その大学に入学しない場合は、入学金は戻ってきません。
大きな金額になるので、手続きの締切日が近づいてから決めようとすると、アタフタしてしまい、正しい判断ができなくなるかもしれません。
各志望校の合否がどういった状況であれば入学の手続きをして、どういった状況であれば入学の手続きをしないのか、共通テスト(旧センター試験)を受験する前に決めておきましょう。
必ず各大学の入学締切日を確認して、その日までにどこの大学に合格していれば手続きをしないのか、どこの大学に不合格であれば手続きをするのか決めておきましょう。
入試カレンダーは必ず作る
入試カレンダーを必ず作りましょう。
出願校が増えてくると、考えなければならないことがどんどん増えていくからです。
カレンダーに、各大学の願書の出願締切日、入試日、合格発表日、入学手続き締切日を入れていきましょう。
頭の中であれやこれやと考えると大変ですが、カレンダーに書き出すと、整理されて注意すべきポイントがわかりやすくなります。
紙のカレンダーに書き込んでいくのも良いですし、グーグルカレンダーなどのカレンダーアプリを使うのも良いです。
一つひとつ入試要項をチェックしながら書き込んでいくのは少し大変ですが、そうするだけの価値がある作業です。
必ず作りましょう!
大学受験の併願校の戦略以外の注意点
ここまで、大学受験の併願校戦略について解説してきましたが、戦略のことだけを考えて併願校を決めてはいけません。
実際にその学校に通うことになる可能性は低くありません。
大学名や偏差値だけを見て受験校を決めてしまうと後悔します。
大学の併願校を選ぶ際の戦略面以外の注意点は、主に次の3点です。
高校受験とは違う!
一つひとつ解説します。
注意1:学校調べをする
併願校は学校名や偏差値だけで選ばないようにしてください。
第一志望の大学だけでなく、併願校として受験する予定の大学も必ずリサーチをしてください。
大学によって特徴が大きく異なり、大学の特徴は偏差値以上に重要だからです。
しっかりと大学のリサーチをして、「この大学に通ってみたい!」と思う大学を併願するようにしてください。
>>【大学受験】志望校の決め方と選ぶときの7つのポイント!偏差値だけで選んではいけない!
注意2:オープンキャンパスに行く
併願校も、オープンキャンパスには行くべきです。
オープンキャンパスでなく、学園祭などのイベントもチェックしましょう。
なんでもない普通の日に行って、普段のキャンパスの雰囲気を感じてみるのも良いです。
いずれにしても、実際に大学に足を運んで、その雰囲気を肌で感じるべきです。
画面越しに見る大学と、実際に自分の目で見る大学は全然違うからです。
実地で得られる情報量は多いです。
オンライン開催も利用する
時間的な余裕がある高1・高2の時期に、いろいろな大学のオープンキャンパスに参加できると良いです。
ただ、志望大学が遠方にあり、なかなか現地に足を運べないという高校生も多いです。
最近はオンラインでオープンキャンパスを行ったり、動画で詳しく大学紹介をしていたりする大学も多いです。
最低限、オンラインイベントに参加できると良いです。
注意3:やりたいことができるかチェックする
その大学で、本人がやりたいことができるのかを必ずチェックしてください。
大学受験は難易度が高いので、どの併願校に通うことになってもおかしくありません。
実際に通ってみてから、「この大学では自分がやりたいことができなかった。」ということになったら、後悔ばかりしてしまうことになります。
逆に、たとえ第一志望校ではない学校に通うことになったとしても、そこで本人がやりたいことに目一杯取り組むことができたなら、受験は成功したと言えます。
大学受験の成否は、併願校選びからはじまっていると言っても過言ではありません。
-

-
受験勉強は諦めるな!大学の第一志望校を変えるべきではない5つの理由
続きを見る
まとめ
それでは、大学受験での出願校戦略の6つのポイントをまとめます。
結論
大学受験の難易度は、高校受験とはレベルが違います。
大学受験を成功させるためには、併願校を含め、受験する大学をよく考えて戦略的に決めるべきです。
併願とは、第一志望の学校に不合格になってしまったときに備え、複数の学校を受験することを指します。
高校受験と同じように考えて、大学受験の併願校を決めると失敗します。
高校受験とは違う!
- 倍率が高い
- 入試制度が複雑
大学入試の種類を、時系列順に解説しました。
大学入試の種類(時系列順)
- 総合型選抜(旧AO入試)
- 学校推薦型選抜(旧推薦入試)
- 大学入学共通テスト(旧センター試験)
- 私立大学一般選抜
- 国公立大学一般選抜
大学受験の併願校戦略のポイントは、主に次の6つです。
大学受験の併願校戦略の6つのポイント
- 数は撃とう
- 安全校から受けよう
- 連続日程は避けよう
- 共通テスト利用を活用しよう
- Aプラン、Bプランは事前に作ろう
- 入学手続き締切日を意識しよう
大学の併願校を選ぶ際の戦略面以外の注意点は、主に次の3点です。
高校受験とは違う!
- 学校調べをする
- オープンキャンパスに行く
- やりたいことができるかチェックする
今回の記事が、お子様が戦略的に受験校を決定し、大学受験を成功させるきっかけとなればとてもうれしいです。