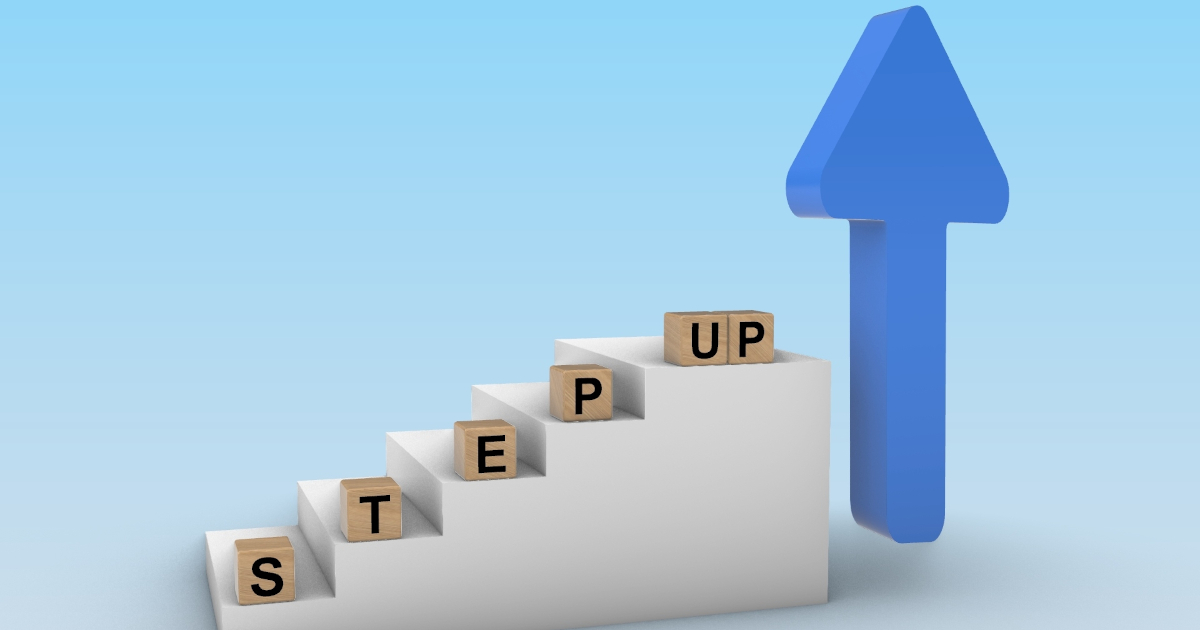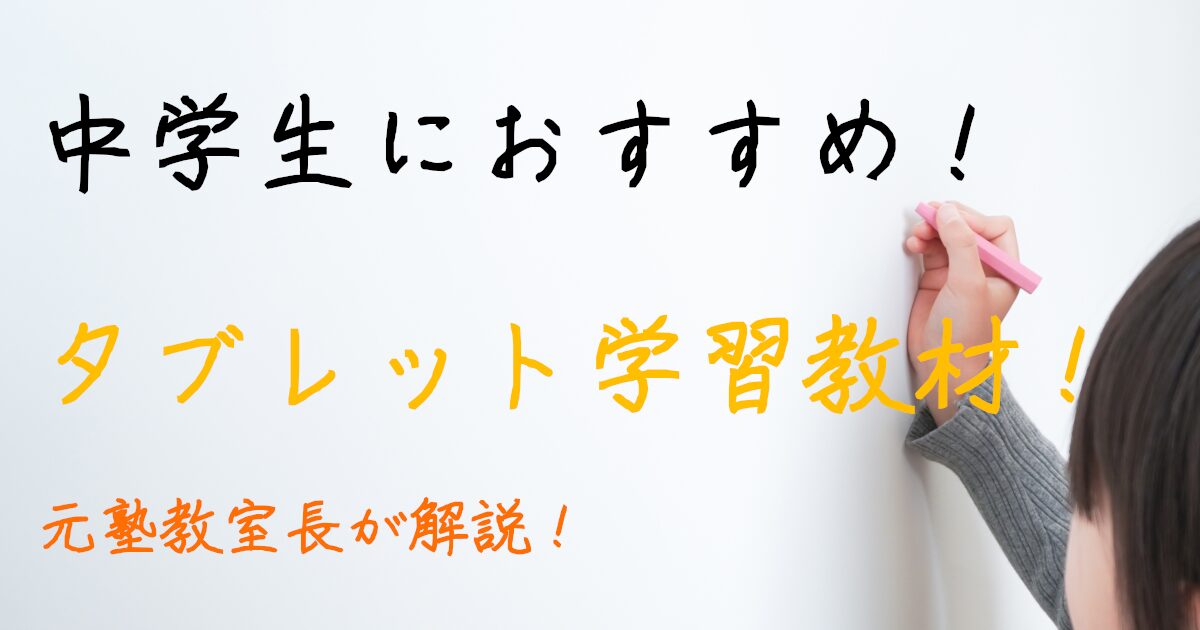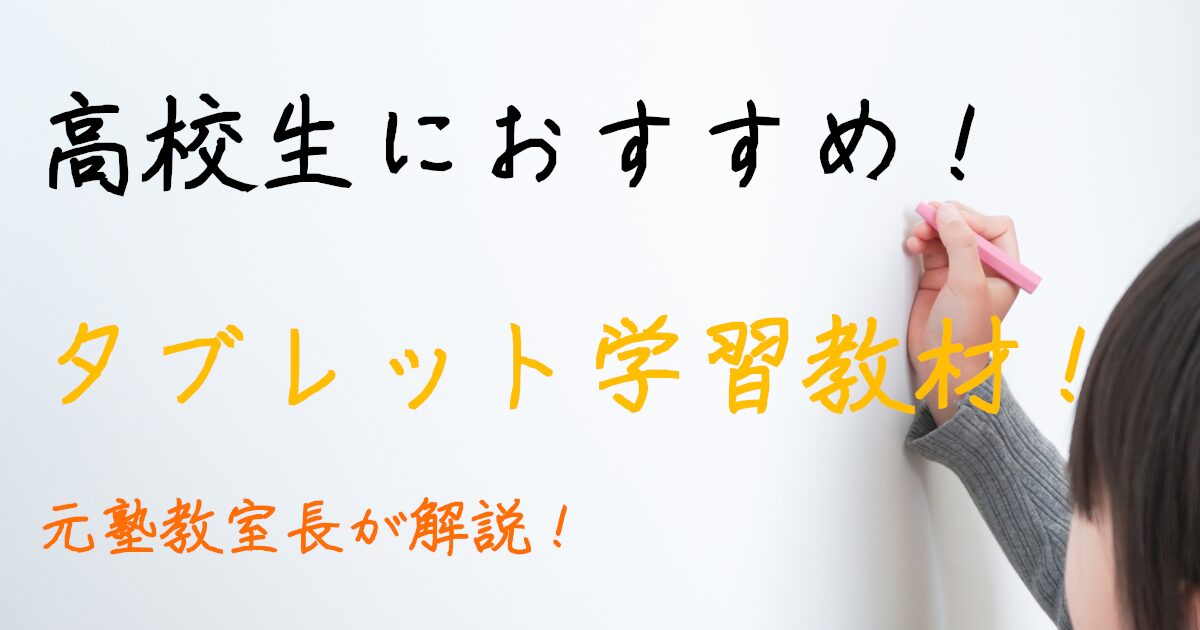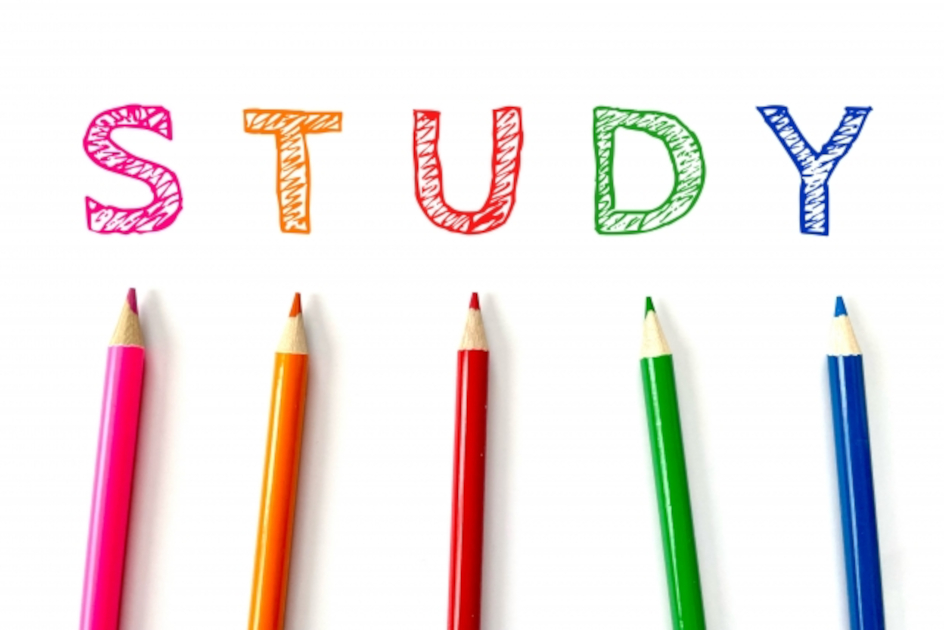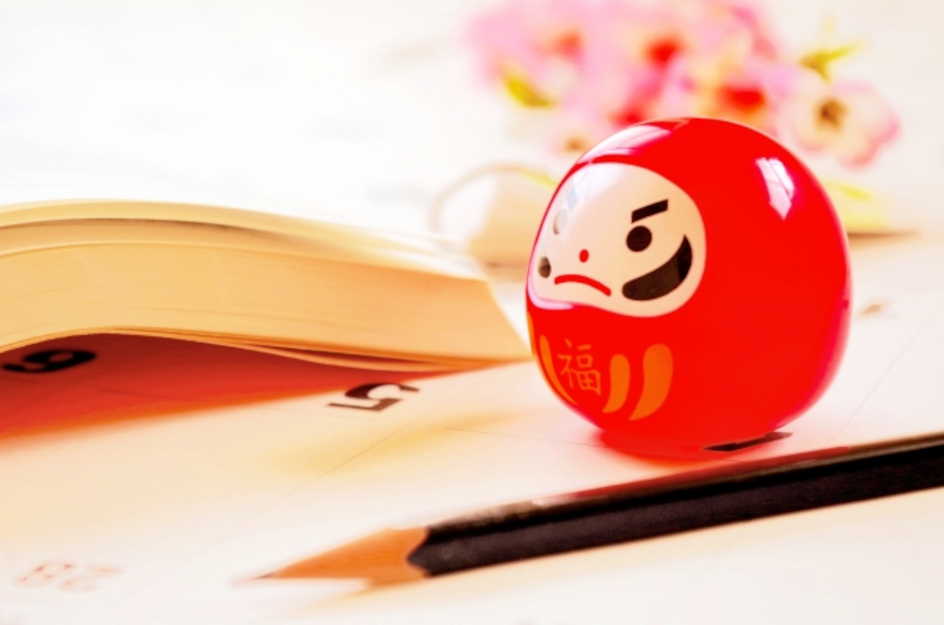こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

どうすれば子どもが勉強を得意にできるのかと、悩まれている保護者の方は多いです。
子どもの受験のことや将来のことで心配されていることと思います。
結論
勉強ができない理由は大きく2つあります。
理由を理解したうえで、勉強ができるようにするための対策をしていくことが大切です。
今回は、勉強ができない2つの理由と、勉強をできるようにするための4つのステップを解説します。
最後まで読んでいただき、お子様が勉強を得意にするための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
勉強ができない理由
勉強ができない理由は、主に次の2つです。
勉強ができない理由
一つひとつ解説します。
理由1:勉強量が足りない
勉強ができない理由として一番多いパターンは、勉強量が足りていないパターンです。
勉強ができない子どものほとんどは、ただ単純に勉強時間と勉強量が足りません。
勉強で一番大事なのは、努力量です。
勉強をできるようにするためには、十分な勉強時間を確保することが最優先です。
理由2:正しい勉強方法が身についていない
たくさん勉強しているのにも関わらず、勉強ができないという子どももいます。
その場合は、正しい勉強方法が身についていない可能性が高いです。
特に、先生に言われたことを真面目に取り組む子どもは、正しい勉強法が身についていないパターンである可能性が高いです。
「言われたことをしっかりやること」に集中してしまい、「なぜそれをやるのか」を考えられていないことが多いからです。
正しい勉強方法というものは、子どもの得意不得意によっても異なります。
子ども自身が、自分で正しい勉強方法を模索しなければ、正しい勉強方法を身につけることはできません。
勉強ができるようになる4つのステップ
勉強ができない2つの理由を克服すれば、勉強ができるようになります。
つまり、勉強量を増やして、正しい勉強方法を身につければ勉強ができるようになります。
一方で、そんなに簡単にこの2つの課題を克服することはできません。
勉強をできるようにするためには、次の4つのステップを一歩一歩取り組んでいく必要があります。
勉強ができるようになる4つのステップ
一つひとつ解説します。
ステップ1:勉強する目的を話し合う


何も言わなくても自主的に勉強に取り組める子どもには、大きく2種類のパターンがありました。
自主的に勉強に取り組める子ども
- 勉強がおもしろいと思っている
- やりたいことやなりたいものがある
>>勉強しない子どもに試してほしい!親子でできる“やる気アップの仕組み”
目的があると頑張れる
勉強のおもしろさを理解するのには時間がかかります。
まずは、勉強する目的を子どもと一緒に考えられると良いです。
目標や目的がなければ、努力をすることは難しいからです。
「勉強する意味」や、「勉強する目的」は、子どもによって異なります。
親が思う価値観を子どもに押し付けるのではなく、子どもと普段から対話して、一緒に考えることが大切です。
夢がある子どものほうが頑張れる
勉強する意味や目的は、将来の夢を実現させるためであることが多いです。
どんな夢であっても、その夢を叶えるためには勉強が必要になります。
勉強そのものをゴールにするのではなく、将来の夢を叶えることを目標にして、勉強はその夢を叶えるための手段に位置付けします。
一方で、子どもたちは「将来の夢」を考えられるほどの基本知識が身についていないことも多いです。
学校の成績のために勉強することも大切ですが、仕事や職業についての勉強も大切です。
子どもと一緒に、将来の夢を考える時間を作ることも大切です。
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
ステップ2:習慣化する
なかなか勉強に取り組むことができない場合は、「習慣化」でつまずいてしまっている可能性が高いです。
やる気があっても、「なかなか勉強に取り組むことができない」と悩む子どもは多いです。
そのような場合は、生活パターンの中に「勉強」を取り入れてしまい、習慣化してしまうことをおすすめします。
夕飯やお風呂や歯磨きと同じように、「勉強」も生活パターンの一部としてしまえると取り組みやすいです。
効率化よりも習慣化
勉強方法と言えば、「効率的な勉強方法」や「成績が上がる勉強法」に飛びついてしまいがちですが、最初のステップの「習慣化」ができていなければ何もはじまりません。
はじめは正しさや効率よりも習慣化です。
「それでは勉強の効率が悪いのでは?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、効率の良い勉強をするためには、まずは効率の悪い勉強をする必要があります。
勉強の効率に関しては、『勉強の効率を上げる方法。それは効率の悪い勉強をすることです。』というnote記事にまとめてあります。
有料記事ですが、はじめの方は無料ですので、ぜひそちらも参考にしてください。
習慣化のための勉強法
習慣化するための勉強は、基礎演習が良いです。
はじめは正しさや効率を考えていないので、体で覚えるような勉強が良いでしょう。
具体的には、計算練習や漢字練習、一問一答などの基礎問題集が良いです。
単純な計算練習であれば、たとえ効率が悪くとも、続けていれば計算力がついていきます。
漢字練習も、「全部10回ずつ書こう!」のような効率の悪い方法であったとしても、漢字を書いていれば、ある程度覚えることができます。
逆に、1題解くのに10分以上かかるような複雑な問題は、習慣化には向きません。
10分考えて1問達成では、達成感に欠けます。
達成感を得られなければ、習慣化する前に飽きてしまうでしょう。
はじめは1日10分から
まずは1日10分からでも良いです。
だんだんと時間を増やしていきましょう。
もし、子どもが中学生であれば、「1日10分は少なすぎる!」と思うかもしれません。
実際に1日10分では少なすぎます。
しかし、多くの子どもたちは、小学生の頃からコツコツと習慣化して、中学生になる頃にやっと1日4時間、1日5時間と勉強することができるようになります。
その積み重ねがなければ、いきなり1日何時間も続けて勉強することは難しいでしょう。
まずは10分、一番最初が難しいのです。
最初のスタートを切ることができれば、だんだんと時間を増やすことはそれほど難しくありません。
スモールステップで、だんだんと勉強時間を増やしていきましょう。
習慣化は、「飽きないこと」「嫌にならないこと」が大切
勉強を習慣化させるときは、子どもが飽きないような勉強、嫌にならないような勉強を取り入れられると良いです。
たとえば、計算問題に取り組むのであれば、10問中9問程度正解するような基本問題が良いでしょう。
子どもはたくさんバツがつくとやる気を失ってしまうものです。
勉強の習慣化のときには、基本的な問題で、たくさん取り組めるようなものが良いです。
習慣化にはルール作りも必要
習慣化に関しては、ある程度の強制力は必要です。
「夕方5時から1時間は勉強の時間」のように、ご家庭でルール作りをすると良いでしょう。
ただし、強制するだけでは子どもは嫌になってしまいますし、子どもの自主性は育ちません。
子どもと話し合いながら、一緒にルールを決めていくことが大切です。
タブレット教材も活用できる
勉強の習慣化には、タブレット教材を利用するのも良いです。
タブレット教材は、子どもが勉強に前向きに取り組めるような工夫がされている教材が多いです。
タブレット教材の中には無学年式の教材も多いので、学年問わず子どもにピッタリのレベルの問題に取り組むことができるのもメリットです。
AIが子どもの学習状況に応じて最適な問題を出題してくれるような教材もあるので、難しい問題ばかりで嫌になってしまうことを防ぐことができます。
タブレット教材は利用料金がかかってしまうというデメリットがあるので、もし、子どもに合いそうなものがあれば、体験してみて決めると良いでしょう。
ポイント
- 料金が安い
- AIによって演習を効率化
- 学習計画を作ってもらえる
- 学年を超えて学習できる
▼あわせて読みたい
>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
-

-
タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
続きを見る
成績目標点別おすすめのタブレット教材
- 平均点を目指すなら
塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】
※苦手克服に特化!担当コーチがつく! - 学年上位を目指すなら
【進研ゼミ中学講座】
※学校の予習復習・定期テスト対策に特化! - 学年最上位を目指すなら
Z会
※学年最上位を目指せる!
タブレット学習教材については、『小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】』『中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』『高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』で解説しています。
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
ステップ3:正しい勉強法を知る
ある程度勉強を習慣化でき、勉強時間が確保できるようになったら、次は正しい勉強法を身につけましょう。
正しい勉強法を身につけられると、勉強の努力をテストの点数に結びつけやすくなります。
正しい勉強法を身につけるうえで意識すべき点は、次の2点です。
勉強法1:「わかる」を「できる」にする
「わかる」を「できる」ようにすることを意識できると、テストの点数が伸びていきます。
授業内容が「わかる」だけでなく、実際の問題を自分の力で「できる」ようにすることで、テストで正解できるようになるからです。
「授業を受けることが勉強することだ。」と、思っている子どもは多いです。
「できる」ようにすることを意識すると、習慣化のステップではただの「作業」となっていた取り組みを、本当の意味での「勉強」にステップアップさせることができます。
今までは、「宿題で出されたから」という理由で、ただ漢字を10回ずつ練習していたものを、
テストでできるようにするためには「書く」だけでなく、「覚える」必要があるのだと気がつくことができます。
勉強を「作業」にしている子どもの具体例
勉強を「作業」にしている子どもの具体例として、塾の生徒でよくあるエピソードを1つ紹介します。
正しい勉強法を意識できていない生徒に暗記課題を出すと、「(1)は江戸幕府、(2)は徳川家光」と、暗記してくることがあります。

勉強ができない子どもは、このように意味のない関連付けをすることが多いです。
暗記は関連させて覚えます。
本来であれば、「(1)」と「江戸幕府」を関連させるのではなく、「1603年に徳川家康が開いた」と「江戸幕府」を関連させなければいけません。
ただ漠然と「作業」として勉強に取り組むのではなく、「どのように勉強すればできるようになるのか」、「どのように勉強すればテストで正解できるのか」を意識できるようにする必要があります。
テストの分析が必要
子どもがある程度の勉強量を確保できるようになってきたら、学校のテストが返ってくるたびに、「この問題はなぜできなかったのか」「この問題はなぜできたのか」を分析するようにしてください。
テストの結果の分析では、必ず「なぜできなかったか」だけでなく、「なぜできたか」も確認すると良いでしょう。
また、親が子どもに一方的に分析結果を教えるのではなく、子どもが自分で考えられるように、問いかけながら一緒に分析するようにすべきです。
▼あわせて読みたい
>>定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント
▼あわせて読みたい
>>定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント
勉強法2:できない問題をできるようにする

このように思っている子どもも多いです。
しかし、実際には丸付けをしてからが本当の勉強になります。
丸付けのあとの勉強ができるようになるかどうかは、「勉強ができる・勉強ができない」の大きなターニングポイントになります。
丸付けのあとの勉強が大事
問題を解いて丸付けをすることは、「自分で解ける問題」と「自力では解けない問題」を選別するための「作業」です。
ここまでは、まだ「勉強」ではありません。
「自力では解けない問題」を、自分だけの力で解けるようにすることが「勉強」です。
ですので、丸付けのあとが勉強です。
バツが付いた問題を、解説を読んだり、教科書を読んだりして、「どうすれば解けるのか」を学ぶことが大切です。
自力で解けるまで繰り返す
解説や教科書を読んで理解した問題は、次の日にもう一度解いてみます。
何も見ずに、誰の助けも借りずに解けたのならOKです。
自分一人では解けなかった場合は、もう一度解説を読んだり、教科書を読んだりして、「どうすれば解けるのか」を確認します。
そして、もう一度同じ問題を解いてみます。
何も見ずに、誰の助けも借りずに解けるようになるまで、何度でも繰り返しトライします。
そうして、できない問題を一つひとつできるようにしていく必要があります。
できなかった問題ができるようになったその瞬間が、本当の意味での勉強となります。
バツは悪くない!
できない問題をできるようにすることが勉強なので、問題を解いてバツがつくことは悪いことではありません。
むしろ、課題が見つかって嬉しいことです。
しかし、子どもはバツがつくことを嫌がります。
「できないと面白くない」という理由もありますが、「できないと怒られる」という理由も強いです。
少し根気が必要ですが、「バツがつくことは悪いことじゃない!」「バツがついたものをできるようにすれば、もっと勉強ができるようになる!」と、子どもに伝え続けてください。
子どもが「バツがつくこと」にネガティブなイメージを持たなくなるまで、何度でも伝え続けてください。
子どもが安心して間違えられる環境を作ってあげることが大切です。
ステップ4:勉強を効率化する
正しい勉強方法で勉強に取り組めるようになってきたら、ここでようやく勉強を効率化することを考えることができます。
多くの場合は、いきなり勉強の効率化を考えてしまうのでうまくいきません。
「勉強の効率化」というものは、かなり高度なテクニックなのです。
しっかりと前段階を踏んでいかなければ到達できないものです。
一つひとつのステップをスモールステップで進んでいくことが大切です。
子どもの得意不得意によって異なる
勉強の効率化にはある程度の定石はありますが、子どもそれぞれに「合う・合わない」があります。
多くの人が「この勉強は最高だ!」と、紹介しているような勉強法でも、合わないものはまったく合いません。
まずは、どんな勉強方法が効率的なのか、いろいろな人の話を聞いてみてください。
勉強が得意な友達や学校の先生、You Tubeなどの動画サイトを参考にしても良いでしょう。
その人たちにアドバイスしてもらったことを、実際に試していきます。
そして、うまくいったアドバイスは採用して、うまくいかなかったアドバイスを不採用にしていきます。
一つひとつ試しては採用・不採用を考え、試しては採用・不採用を考えの繰り返しです。
そうして積み上げて、本人に一番合った、効率的な勉強方法を考え続けていきます。
>>【元塾教室長が解説!】中学数学を復習するための効率的な勉強方法
>>効率的な暗記方法!長期記憶にするための19のコツ【元塾教室長が解説!】
「受験直前に本気出す!」は危険

このように思っている子どもは多いのですが、受験直前から本気を出そうと考えるのは大変危険です。
いきなり効率の良い勉強はできないからです。
「本気出す!」と思っても、いきなり1日5時間以上勉強するのは難しいです。
まずは勉強する目的を考えるところからはじめて、勉強を習慣化していき、1日の勉強時間を頑張って増やしていく必要があるのです。
一方で、普段から勉強して習慣化できていれば、受験直前になったらいきなり「効率化」を意識しながら、「正しい勉強法」で、長時間勉強することができます。
受験直前に本気を出すためには、普段から勉強に取り組んでいることが大切です。
>>高校受験の受験勉強はいつから本気を出せば間に合うのか【元塾教室長が解説!】
>>大学受験の勉強はいつから?高校受験の意識のままでは絶対に間に合わない!
習慣化は基礎の基礎から!
勉強ができない子どもが勉強を習慣化させるのであれば、基礎の復習からはじめることを強くおすすめします。
勉強ができない子どもは、学校の勉強についていけていない可能性が高いからです。
学校の勉強の対策に取り組む前に、つまずいてしまっている部分の復習からはじめたほうが良いです。
前の学年の学習内容でつまずいてしまっているようであれば、勇気を持って前の学年まで戻って復習をしたほうが良いです。
特に、算数(数学)や英語などの積み上げ式の教科は、わからないところまでしっかりと戻って復習したほうが効率的です。
1つの苦手が、その後の学習内容でずっと足を引っ張り続けてしまうからです。
学年を超えての復習は遠回りに感じるかもしれませんが、長い目で見れば一番の近道です。
苦手克服に特化したタブレット教材『すらら』
すららは、苦手克服に特化したタブレット教材です。
無学年式なので、学年を超えて苦手なところから取り組むことができます。
勉強のつまずきの原因は、普段の学習の中でAIが自動的に判別して対策してくれます。
勉強にゲームの要素を取り入れる「ゲーミフィケーション」機能によって、子どもの勉強へのモチベーションを引き上げる工夫がされています。
すららは、コーチがつくのも大きな特徴です。
質問対応をしてもらえるだけでなく、保護者のサポートもしてもらえるのが心強いです。
| すらら | |
| 料金 | 小中3教科コース
|
| 教科 |
|
| おすすめポイント |
|
| 体験授業 |
▼無料体験に申し込む |
\入会金無料!/塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】
![]()
※2025年5月31日まで!
▼もっと詳しく見る
>>『すらら』は基礎のおさらいに最適の無学年式タブレット学習教材!料金は?口コミは?
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
まとめ
それでは、勉強ができない2つの理由と、勉強をできるようにするための4つのステップをまとめます。
結論
勉強ができない理由は大きく2つあります。
理由を理解したうえで、勉強ができるようにするための対策をしていくことが大切です。
勉強ができない理由は、主に次の2つです。
勉強ができない理由
- 勉強量が足りない
- 正しい勉強方法が身についていない
勉強をできるようにするためには、次の4つのステップを一歩一歩取り組んでいく必要があります。
勉強ができるようになる4つのステップ
- 勉強する目的を話し合う
- 習慣化する
- 正しい勉強法を知る
- 勉強を効率化する
受験直前期になって「本気を出す!」と思っても、勉強ができるようになる4つのステップを駆け上がることはできません。
普段から勉強に取り組むことが大切です。
今回の記事が、お子様が勉強を得意にするきっかけとなればとてもうれしいです。