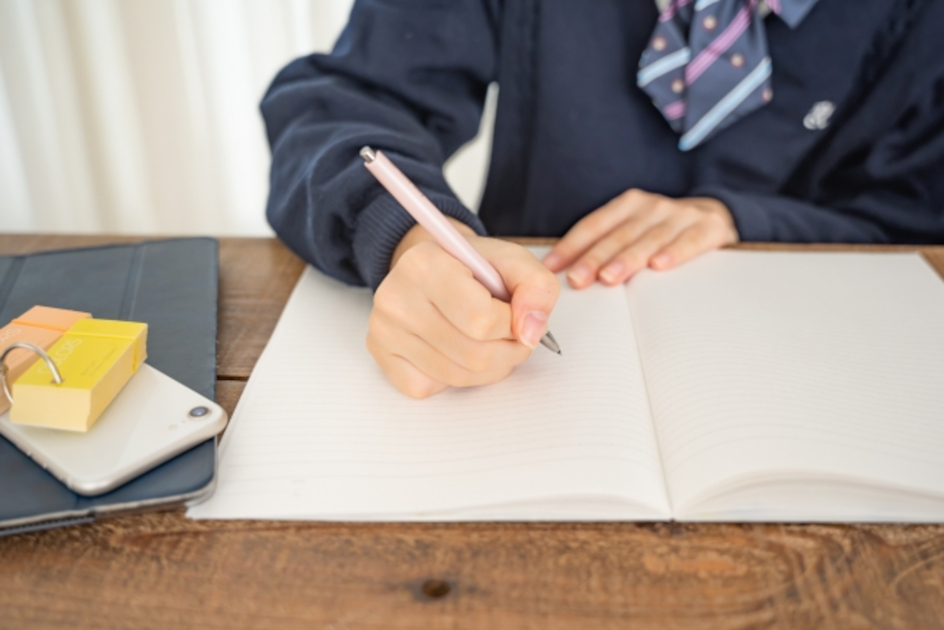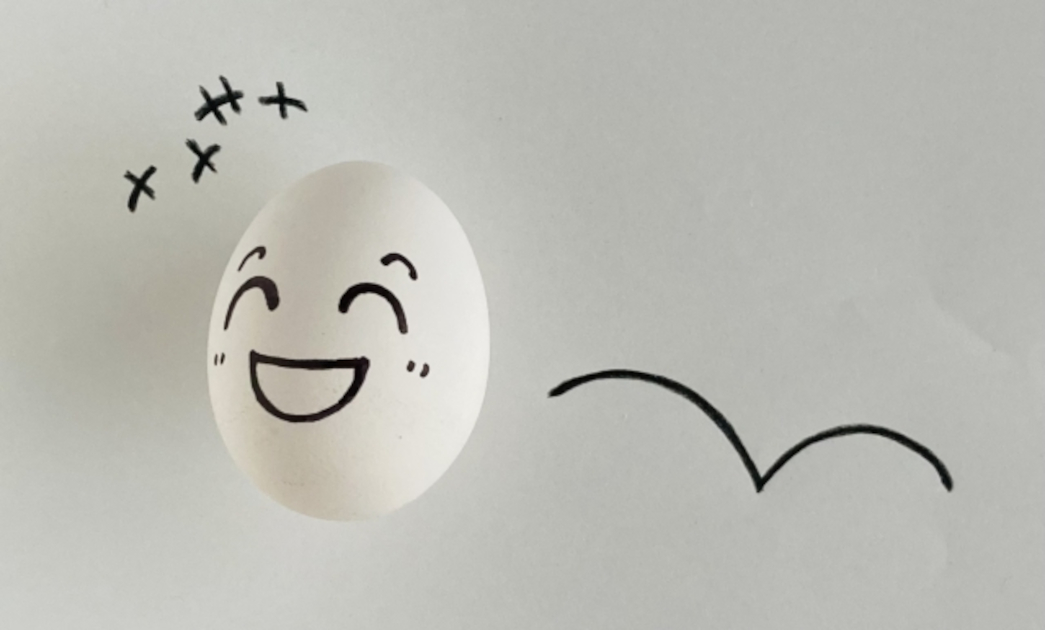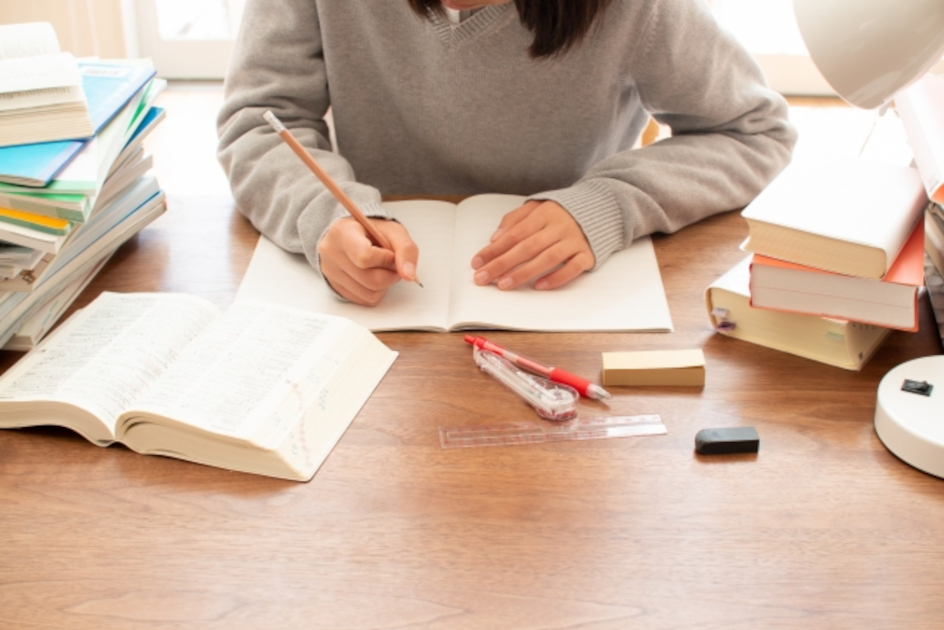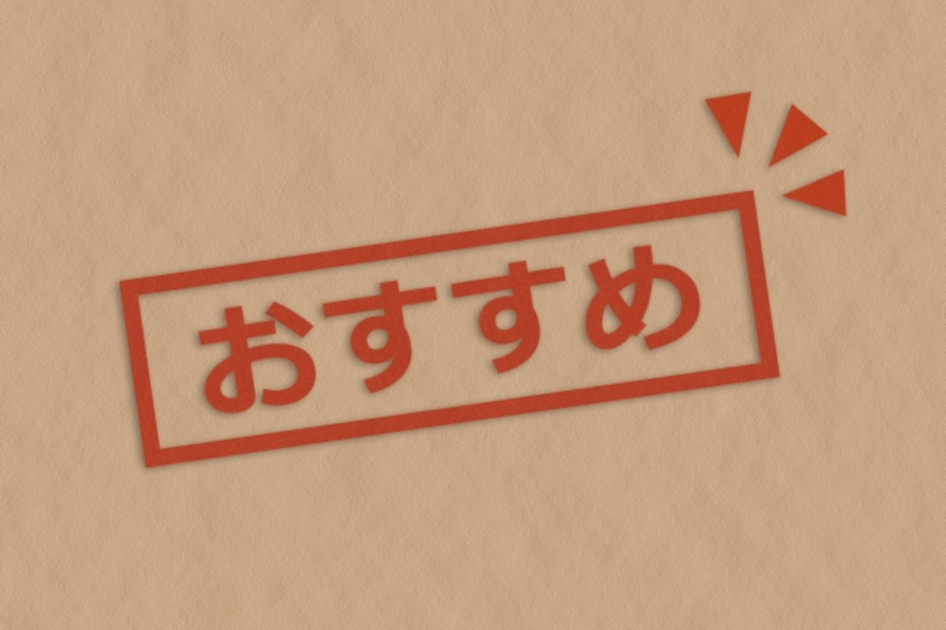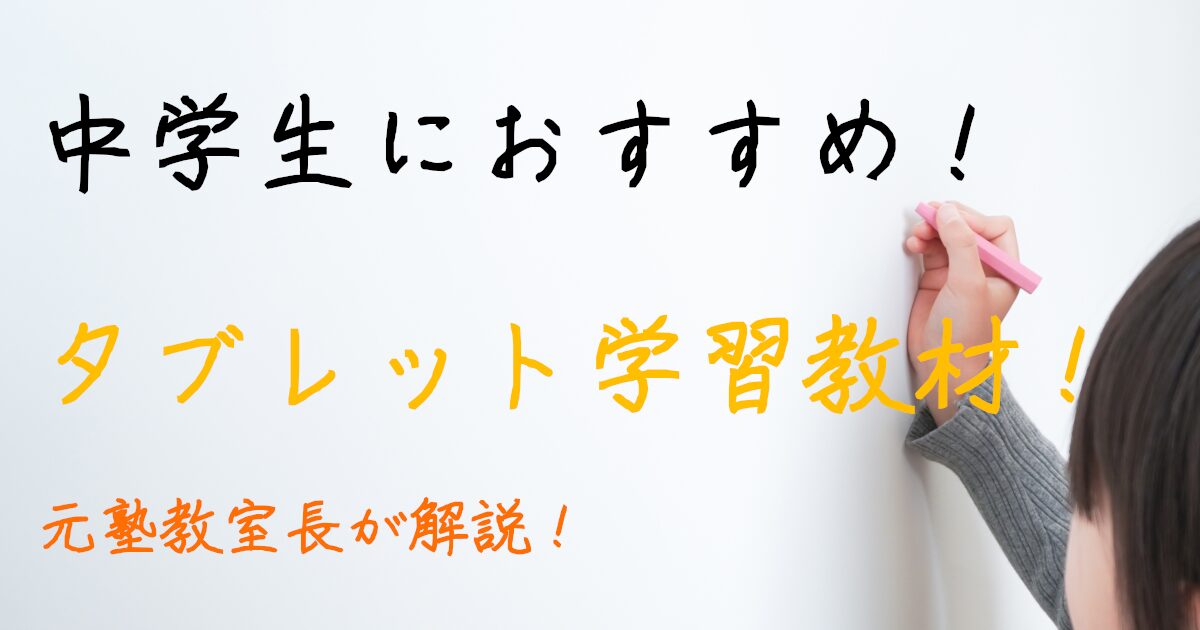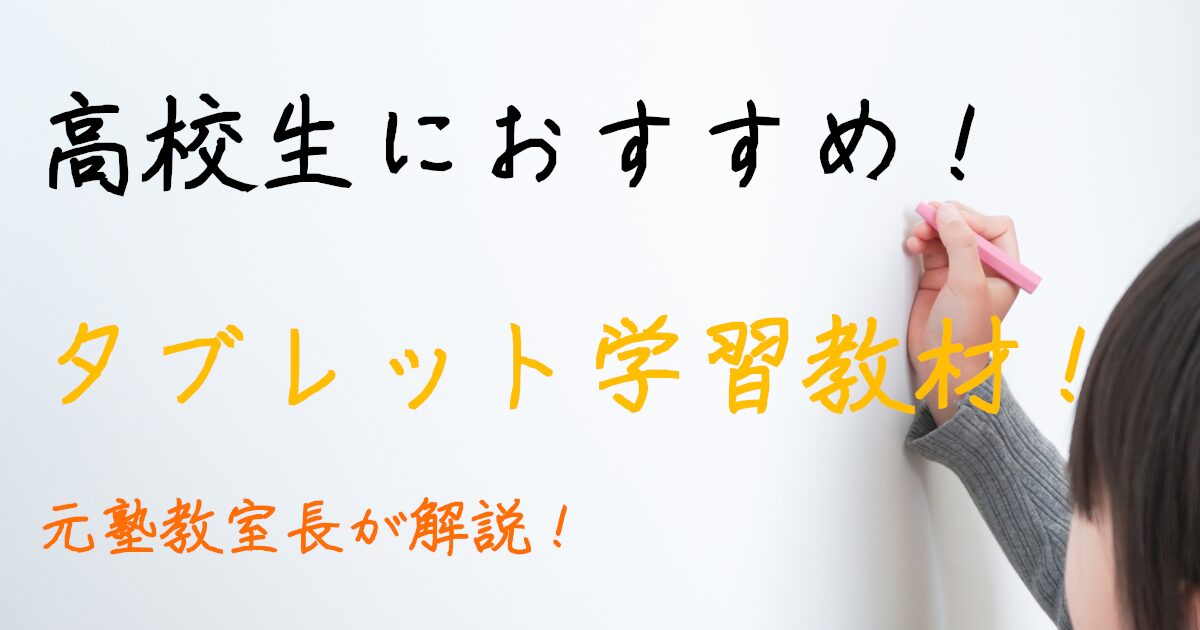こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。


教育もようやくデジタル化が進んできていて、民間からはタブレットを活用した学習教材も多く登場しています。
タブレット教材を検討されているご家庭も多いです。
しかし、紙と鉛筆での勉強に慣れ親しんできた世代からすると、本当にタブレットなんかで勉強ができるのかと心配になってしまいますよね。
結論
タブレット教材は効率良く勉強できるのでおすすめです。
一方で、デメリットも多いので適切なケアが必要です。
今回は、タブレット教材の8つのメリット・デメリットを解説します。
最後まで読んでいただき、お子様がタブレット教材を活用して勉強を得意にしていくための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
タブレット学習教材のデメリット
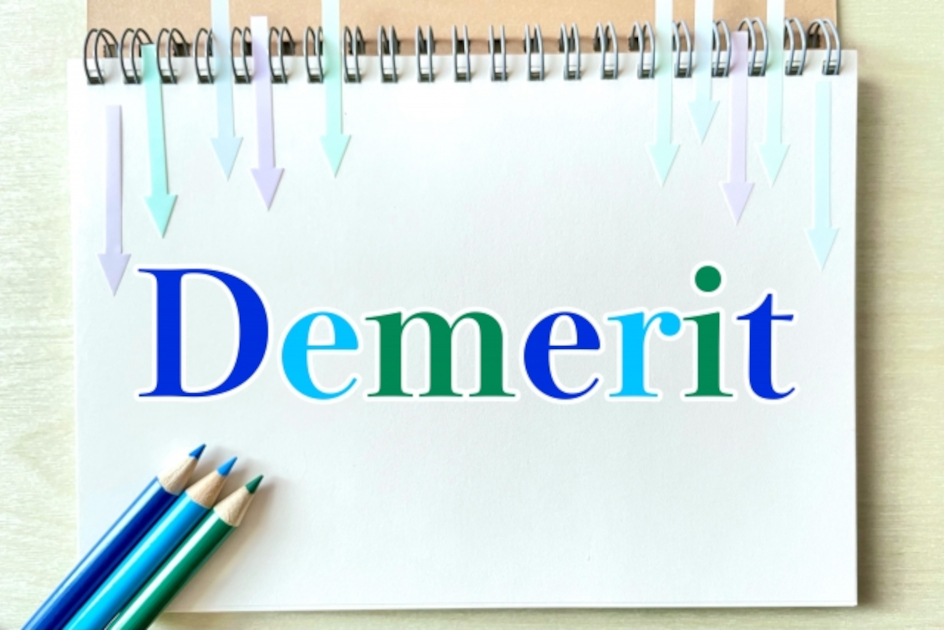
タブレット教材のデメリットは、主に次の8つです。
タブレット教材のデメリット
一つひとつ解説します。
デメリット1:勉強の進捗管理が難しい

タブレット教材の最大のデメリットは、子どもの勉強の進捗管理が難しいということです。
タブレット教材は一人で自由に取り組める反面、好きなだけサボることもできてしまうからです。
塾や予備校に通っていたり、家庭教師がついている場合は、子どもの勉強の進捗は担当講師が管理してくれています。
いつまでにどこまで勉強を進めて、定着のために演習をどれくらいやるかを、すべて講師が決めてくれます。
学習に遅れがあった場合はすぐに気がついて、学習計画の修正を行ってくれています。
タブレット教材に限らないのですが、塾に頼らない勉強では、学習進捗の管理を保護者が行う必要があります。
各社が対策をしている
各教材会社も、この最大のデメリットを埋めるためにいろいろな対策をしています。
具体例としては、次のような対策を提供している教材会社があります。
進捗管理の工夫
- 学習カレンダーの提供
- AIによる学習スケジュールの自動生成
- 保護者にメールやLINEで学習進捗を報告
- 保護者向け学習管理画面を提供
- 専属コーチがつく
各社いろいろな工夫をしていますが、塾や予備校に比べれば保護者の負担は大きくなります。
タブレット教材を子どもに手渡すだけでは、ほとんどの場合は予定通りに学習を進めることはできません。
子どもが一人で自分の学習進捗を管理することは非常に難しいです。
塾や家庭教師であっても任せっきりにしていてはいけませんが、タブレット学習教材では学習管理に関する保護者の負担がグッと大きくなることを知っておいてください。
デメリット2:モチベーション維持が難しい

タブレット教材は、勉強へのモチベーションを維持することが難しいです。
人の気持ちを大きく動かせるのは、人だからです。



このように、子どもが勉強を頑張るきっかけには「人」が関係していることが多いです。
タブレット学習教材では先生と直接会って話をするわけではないので、モチベーション管理の役割を保護者が担う必要があります。
>>勉強のやる気を出す26のテクニックとモチベーションの上げ方
各社が工夫をしている
各教材会社も、モチベーション維持については工夫を凝らしています。
担当のコーチが子どもに向けてメッセージを送ってくれたり、保護者宛てに「今週はお子様がここを頑張ったから、こうやって褒めてほしい。」というメッセージを送ってくれたりします。
それでも、最後のところは生身の人間とのコミュニケーションが必要になります。
タブレット教材においては、保護者の方が子どもとのコミュニケーションを取って、モチベーション管理をしてあげる必要があります。
>>勉強しない子どもに親がすべき2つのこと【元塾教室長が解説!】
デメリット3:タブレットとタッチペンは慣れが必要

デジタル機器に慣れ親しんだ子どもであっても、タブレットとタッチペンに慣れるまでは少し時間がかかります。
液晶画面に文字を書くときの感触は、紙に書く感触とはかなり異なるからです。
特に、筆圧の安定しない小さな子どもには大変かもしれません。
逆に、消しゴムに関しては、力を入れてゴシゴシする必要のないタブレットの方が有利だったりします。
タブレットに紙のような質感で書くことができる、ペーパーライクフィルムというものも売られています。
タブレットを使って勉強する人や、絵を描いたりする人の中には、ペーパーライクフィルムを好んで使っている人も多いです。
デメリット4:記述解答の判定がシビア
タブレット教材は記述解答もその場で自動で採点してくれるのですが、その記述採点の判定精度が高くありません。
これは技術的な問題だと思われます。
漢字の「とめ・はね・はらい」までしっかりと判定することを売りにしている教材がある反面、明らかな正解を書いてもバツをつけられることがあります。
実際に一生懸命取り組んでいる子どもにとっては、正解にバツをつけられればやる気がしぼんでしまうでしょう。
勉強においては「書くこと」は非常に重要ですので、各社対応を急いでほしい部分です。
デメリット5:書いて覚える習慣をつけにくい
タブレット教材では、書いて覚える勉強習慣をつけにくいです。
タブレット教材では、選択肢から選ぶ問題が出題されやすいからです。
記述問題であっても、たくさん書いて覚えるような場面は少ないです。
特に、漢字や英単語のような単純な暗記勉強は、書いて覚えることが大切になります。
そのような「書く勉強」の習慣がつきにくいのは、タブレット教材の欠点です。
デメリット6:わかったつもりになりやすい
タブレット教材に取り組んでいると、子どもはわかったつもりになってしまいやすいです。
選択問題を解きながら手軽にどんどん勉強が進んでしまうためです。
しかし、どのような勉強であっても1回で理解することは難しいです。
勉強がサクサクと進んでわかったつもりになってしまうのは、非常に危険です。
一度解いた問題を何度も繰り返すように、保護者の方が子どもに指導する必要があります。
デメリット7:タブレットで遊んでしまう
子どもがタブレット教材で勉強していると思ったら、いつの間にかタブレットで遊んでいるということは多いです。
スマホやタブレットには、勉強以外の誘惑も多いからです。
普段から使っている端末を使ってタブレット教材に取り組むのであれば、子どもが勉強に集中できるように工夫して使う必要があります。
教材によっては、専用のタブレットを提供しているものもあります。
専用タブレットであれば他のアプリで遊んでしまうことはありませんが、専用タブレットを購入する必要があるので、費用がかかってしまいます。
>>スマホは勉強へのメリットが大きい!注意点や活用法を元塾教室長が解説!
デメリット8:機材トラブルがあると勉強できない
タブレット教材は、機材トラブルがあると勉強できなくなってしまうのもデメリットです。
タブレットが故障しまったり、ネットワークの調子が悪かったりすると勉強に取り組めません。
サービスによっては他のタブレットやパソコンを利用して勉強に取り組むことができますが、専用タブレットを利用している場合は、修理に出して戻ってくるまでは勉強がストップしてしまいます。
タブレット学習教材のメリット

タブレット教材のメリットは、主に次の8つです。
タブレット教材のメリット
一つひとつ解説します。
メリット1:復習や先取り学習がしやすい
タブレット教材の最大のメリットは、つまずいてしまっている部分の復習にも取り組みやすく、得意な教科の先取り学習にも取り組みやすいところです。
いつでも好きなところに取り組めるようになっているタブレット教材が多いからです。
教材によっては、小1~高3までの学習範囲にいつでも取り組めるようなものもあります。
そのような場合は、学年を超えた勉強にも取り組むことができます。
学年を超えるなら圧倒的にタブレット教材
タブレット教材は、学年を超えてさかのぼって復習したり、学年を超えて先取り学習をしたりするのに非常に便利です。
個別指導の塾や家庭教師でも、学年を超えて復習したり、先取りをしてくれる場合もあります。
しかし、学年を超えての勉強は、学年通りの勉強に比べると時間がかかります。
塾や家庭教師のような、1週間に数時間の授業では対応が難しいのです。
その点、タブレット教材には時間制限はありません。
努力次第では好きなだけおさらいができますし、好きなだけ先取り学習ができます。
メリット2:AIが勉強を効率化してくれる
今のタブレット教材は、AIが標準搭載です。
子どもの学習状況を分析しながら、今取り組むべき勉強をAIが判断してくれます。
繰り返し学習ができるように、タイミングを見計らって同じ問題を再出題してくれたりもします。
これまではベテラン講師の経験と勘に頼っていた部分を、AIが一部担ってくれるようになりました。
そのため、過去の通信教育教材とは大きく異なり、勉強効率が抜群に上がっています。
学習スケジュールもAIが作成
タブレット教材によっては、AIが学習スケジュールを作ってくれます。
学習の進捗を分析しながら、その都度必要に応じてAIが学習スケジュールを修正してくれます。
これまでの学習データを元に、定期テスト直前期に取り組むべき学習内容をスケジュール化してくれるような教材もあります。
今後もAIの活用はどんどん進んでいき、更に効率化されていくことが予測されます。
メリット3:場所と時間に縛られない
タブレット教材は、勉強する場所や時間に縛られないのも大きなメリットです。
いつでもどこでも、タブレットを取り出せばすぐに勉強をはじめられます。
部活や習い事が忙しく、なかなか曜日固定の塾には通えないという場合には特に活用しやすいです。
移動時間やスキマ時間に手軽に取り組めるのも、非常に便利です。
塾であれば、授業時間が「1週間に何分」と決まっていますが、タブレット学習教材であれば取り組みたいだけ取り組むことができます。
そのため、先取り学習をどんどん進めたいという子どもであれば、努力次第で何学年も先の先取りをすることもできます。
苦手の克服をしたいという子どもであれば、頑張り次第でとことん苦手単元に取り組むこともできます。
時間に縛られないことはデメリットにもなる
時間が自由であるということは、好きなだけサボれるという意味でもあります。
時間管理の練習になるとも言えますが、子どもが自力で時間管理をするのは非常に難しいです。
先程も解説した通り、保護者の方の協力は絶対に必要です。
メリット4:動画やアニメーションの解説がわかりやすい

タブレット学習教材は、紙の教材に比べて視覚的イメージを活用しやすいです。
文字だけの教材よりも、絵や写真があった方が理解しやすいですし、記憶にも残りやすいです。
紙の教材はページ数の関係上、スペースを取ってしまう絵や写真の数には制限があります。
しかし、デジタル教材であればスペースを気にする必要はありません。
絵や写真を使った説明がしやすくなります。
また、学ぶ内容によっては、動画やアニメーションなどで動きをつけた方が説明しやすい内容もあります。
紙で動きをつけることはできませんが、タブレットなどのデジタル教材であれば可能です。
授業配信も便利
動画授業がついているような教材であれば、わからなかった部分を何度でも見返すこともできます。
一時停止や早送り、倍速再生もできたりするので、勉強のやり方が身についてきていれば、学習効率を一気に上げることもできます。
メリット5:自動採点なのですぐに復習できる

タブレット教材は自動で採点されるので、一人で勉強していてもその場ですぐに復習できるのがとても良いです。
勉強においては、すぐに復習することは超重要です。
できなかったものをできるようにするのが勉強だからです。
タブレット学習教材は、ほとんどの場合、問題を解いたその場で自動採点されます(一部、人が時間をかけて添削する場合もあります)。
そして、その場ですぐに解説されます。
そのため、できなかった問題をその場ですぐに理解することができます。
教材によっては、間違えた問題から子どもの苦手ポイントをAIが分析し、その苦手ポイントを克服するための問題を出題してくれるようようなものもあります。
また、問題の難易度を自動で調整してくれる教材もあります。
丸付けはこまめにしたほうが良い
紙と鉛筆で勉強する場合、ある程度の数の問題を解いてから丸付けをします。
勉強が苦手な子どもは、10ページも20ページも問題を解いてからまとめて丸付けをしたりします。
そして、丸付けをして「はい!おしまい!」としてしまう子どもも多いです。
丸付けをしたあとが勉強です。
バツがついた問題を克服しなければ、勉強したということにはなりません。
紙と鉛筆で勉強していると、本人は勉強しているつもりでいても、実際のところは全然勉強できていないことも多いです。
こまめに丸付けをしてくれるタブレット教材は、正しい勉強方法で勉強するための手助けもしてくれます。
こまめに丸付けをすべき理由
勉強は、一つひとつしっかりと理解してから次へ進んだほうが効率的です。
理解していない部分があれば、その後の勉強を理解することができないからです。
たとえば、問題集の大問1で「6+8=」という問題が出たとしましょう。
この問題を「6+8=15」と間違えてしまったとします。
すると、大問2で「6+8+10=」という問題が出題されれば、「6+8+10=25」と、間違えてしまうことになります。
さらに、大問3で「(6+8)×3+5=」という問題が出題されれば、「(6+8)×3+5=50」と、間違えてしまうことになります。
全部解いてから全部丸付けをした場合、全部バツになり、全部計算し直さなければなりません。
しかし、大問1の時点で丸付けをして、

と、理解することができれば、大問2と大問3は正しく計算できます。
このように、丸付けはこまめにした方が効率的なのです。
タブレット教材では、こまめな丸付けを自動的に習慣化できることが大きなメリットです。
メリット6:論理的思考力を育てられる
タブレット教材は、論理的思考力を育てやすいです。
タブレット教材の中の先生と事細かに対話しながら、一つひとつ課題をクリアしながら勉強に取り組めるからです。
論理的な思考力を育てるためには、1つの大きな難題を、小さな課題に分けていって、それらを一つひとつ考えながら解決していく必要があります。
このプロセスを、先生が一人ひとりの子どもにつきっきりで指導するのは現実的には不可能です。
しかし、タブレット教材であれば可能になります。
個別に対話を繰り返しながら問題を解決していくような問題は、学校での授業よりもタブレット教材のほうが学びやすいです。
メリット7:繰り返し勉強できる
タブレット教材は、同じ問題内容を何度も繰り返し勉強できるのも大きなメリットです。
勉強は、繰り返すことが大切だからです。
特に、苦手な部分は何度も何度も繰り返してしっかりと理解しなければなりません。
紙の問題集でも、他のノートに問題を解けば繰り返し同じ問題に取り組むことはできます。
しかし、タブレット教材であれば何も気にせずに取り組んでも同じ問題を繰り返すことができるので便利です。
繰り返し取り組めるように、AIが自動的に出題してくれる教材もあるので、非常に便利です。
メリット8:楽しく勉強できる
タブレット教材には、ゲーミフィケーションを取り入れたものも多いです。
ゲーミフィケーションとは、ゲーム以外の物事にゲーム要素を取り入れることです。
勉強にゲームの要素を取り入れると、楽しく、興味を持って、前向きに勉強に取り組むことができます。
塾や予備校でも、生徒たちのモチベーションを上げるためにゲーミフィケーションの要素を取り入れていることも多いです。
勉強の達成度を見える化したり、頑張って取り組んだことにポイントをつけたり、仲間同士で競い合えるようにランキングを作ったりして、子どもたちが楽しく勉強に取り組めるよう工夫をしています。
タブレットはゲームとの相性が良いので、塾や予備校よりもゲーミフィケーションの要素を取り入れやすいです。
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
子どもの健康に影響はあるのか


健康面に注意するのであれば、次の3点に気をつけて勉強に取り組めると良いです。
健康面で注意すること
注意点1:スマホの小さい画面を見続けない
スマートフォンを利用できる教材であっても、タブレットやパソコンを利用することを強くおすすめします。
小さな画面を見続けるのは、子どもでも大人でも健康面に悪影響を及ぼすからです。
スマートフォンは、スキマ時間などに短時間で取り組むときのみ利用すると良いです。
注意点2:強すぎる光に注意
スマホやタブレット、パソコンのディスプレイなどから発せられる強い光には注意が必要です。
寝る前のスマホは睡眠不足の原因になるとも言われています。
寝る直前の時間の学習は控えたほうが良いです。
ブルーライトをカットしてくれる保護フィルムなどを利用しても良いでしょう。
注意点3:姿勢に注意
スマートフォンやタブレットに限ったことではありませんが、取り組む際の姿勢には注意が必要です。
特に、スマートフォンやタブレットを利用するときは、背中や首を曲げてしまうことが多いです。
スマートフォンやタブレットはを手に持って取り組むのではなく、タブレットスタンドなどで目線が上がる高さに設置して、画面から30cm以上離れて取り組むことをおすすめします。
紙と鉛筆も使うべき
タブレット教材にはメリットが多いですが、デメリットも多いです。
そのため、タブレット教材と紙の教材を併用して勉強していくべきです。
どちらか一方だけにするべきではありません。
タブレット教材をメインにして勉強を進めながらも、紙に書いたほうが取り組みやすい勉強は紙と鉛筆を利用していくのが良いでしょう。
特に、何かを大量に書くような勉強は紙と鉛筆のほうが取り組みやすいです。
それぞれのメリットを活かして取り組めると良いです。
自主的な勉強が鍵
他の勉強でも同じことではあるのですが、特にタブレット教材や通信教育教材については、子どもが自分から進んで勉強に取り組めるかどうかが鍵になります。
タブレット教材は好きなだけ自由に勉強に取り組める反面、好きなだけ自由にサボることもできてしまうからです。
親や先生に言われてイヤイヤ勉強している状態では、タブレット教材を上手に活用するのは難しいでしょう。
なぜ勉強するのかを一緒に考える
自分から進んで勉強に取り組める子どもには、大きく2種類のパターンがあります。
自主的に勉強に取り組む子どもの特徴
- 勉強を楽しめている
- 夢や目的を持っている
まずご家庭でできることは、子どもの将来について、子どもと一緒に考えることです。
将来やりたいことや将来なりたいものがある子どもは、自主的に勉強することができます。
勉強は、やりたいことをやるための手段です。
勉強は、なりたい自分になるための手段です。
なぜ勉強するのかを子どもと一緒に考える機会を作ることが大切です。
>>勉強しない子どもに親がすべき2つのこと【元塾教室長が解説!】
まずはインプット
子どもの将来の夢を考えるときも、勉強と同様にインプットが大切です。
知識がなければ、考えることはできないからです。
世の中にどのような仕事があるのか、どのようなことをして生きている人たちがいるのか、子どもと一緒に調べられると良いです。
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
おすすめのタブレット教材
昨今は多くのタブレット教材が提供さています。
各社が特徴のあるサービスを提供していますので、子どもの目的や得意・不得意に合った教材を選ぶことが大切です。
知名度や評判だけで決めず、複数のサービスのお試し体験をしたり、資料請求をしたりしてじっくりと考えて決めるべきです。
一例として、目的別におすすめのタブレット教材を紹介します。
おすすめのタブレット教材
- 学年最上位層を狙う
→Z会 - 学校の勉強の予習復習をしたい
→進研ゼミ - 書いて学ぶことにこだわりたい
→スマイルゼミ - 苦手教科を克服したい
→すらら - 算数対策に力を入れたい
→RISU算数
タブレット学習教材については、『小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】』『中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』『高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』で解説しています。
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
まとめ
それでは、タブレット教材の8つのメリット・デメリットをまとめます。
結論
タブレット教材は効率良く勉強できるのでおすすめです。
一方で、デメリットも多いので適切なケアが必要です。
タブレット教材のデメリットは、主に次の8つです。
タブレット教材のデメリット
- 勉強の進捗管理が難しい
- モチベーション維持が難しい
- タブレットとタッチペンは慣れが必要
- 記述解答の判定がシビア
- 書いて覚える習慣をつけにくい
- わかったつもりになりやすい
- タブレットで遊んでしまう
- 機材トラブルがあると勉強できない
タブレット教材のメリットは、主に次の8つです。
タブレット教材のメリット
- 復習や先取り学習がしやすい
- AIが勉強を効率化してくれる
- 場所と時間に縛られない
- 動画やアニメーションの解説がわかりやすい
- 自動採点なのですぐに復習できる
- 論理的思考力を育てられる
- 繰り返し勉強できる
- 楽しく勉強できる
タブレット教材にもメリット・デメリットがあるので、紙と鉛筆を使っての勉強も併用して取り組むべきです。
また、タブレット教材のメリットを最大限に活かすためにも、子どもが自分から進んで勉強できるようにしていかなければなりません。
子どもの将来のことを一緒に考え、なぜ勉強するのかを明確にしていく必要があります。
そのうえで、子どもの目的や得意・不得意に合わせてじっくりとタブレット教材を選べると良いでしょう。
おすすめのタブレット教材
- 学年最上位層を狙う
→Z会 - 学校の勉強の予習復習をしたい
→進研ゼミ - 書いて学ぶことにこだわりたい
→スマイルゼミ - 苦手教科を克服したい
→すらら - 算数対策に力を入れたい
→RISU算数
今回の記事が、お子様がタブレット教材を活用して勉強を得意にしていくきっかけとなればとてもうれしいです。
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る