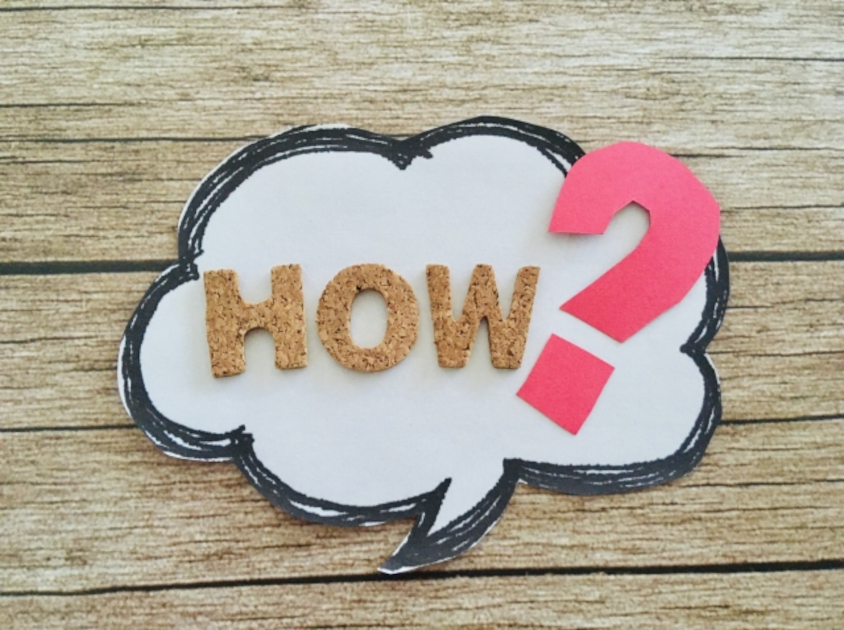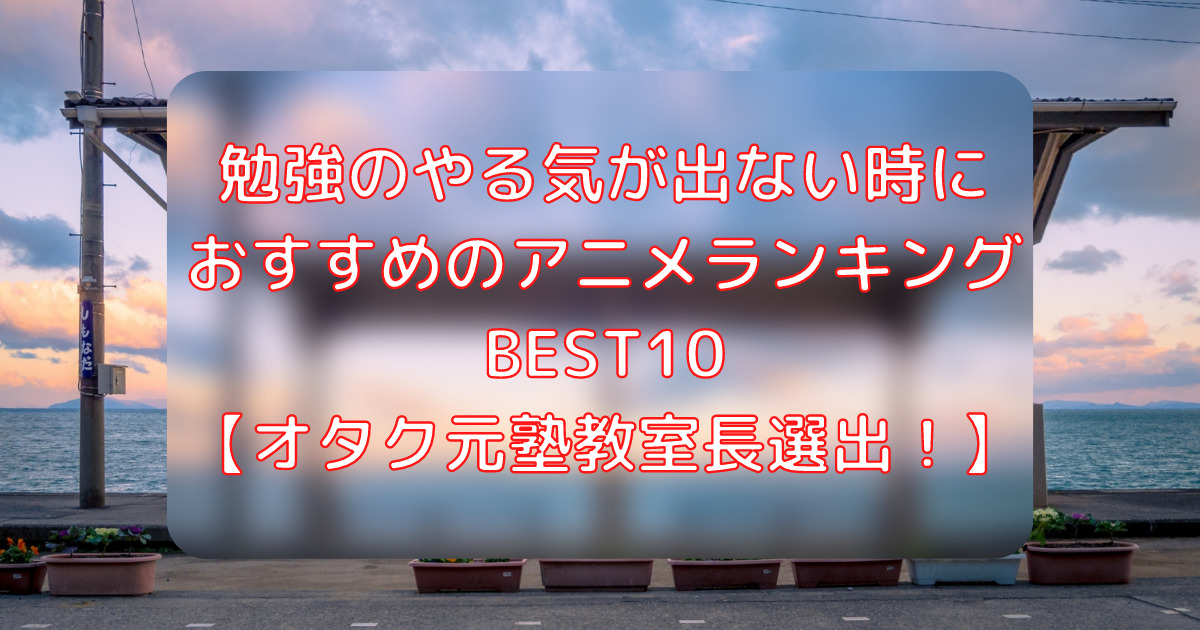こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

勉強のやる気が出ないと言う子どもは多いです。
子どもの受験や将来のことを考えると、なかなか勉強へのやる気を出さない子どもにヤキモチしてしまいますよね。
結論
勉強のやる気アップのためには、まずは根本的なモチベーションを上げる必要があります。
そのうえで、やる気が出ないときに活用できるテクニックを身につけていくことが大切です。
今回は、勉強へのモチベーションの上げ方と、やる気を出すための26のテクニックについて解説します。
最後まで読んでいただき、お子様が前向きに勉強に取り組めるようになるための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
対面型の個別指導のような授業をオンラインで!
「オンライン家庭教師WAM![]() 」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!
」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!
安心の返金保証・成績保証!
▼詳しくはこちらから!
>>オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・特徴は?
勉強のモチベーションは3段階
勉強のやる気を出すためには、まずは根本的な勉強へのモチベーションを上げる必要があります。
根本的なモチベーションを持てていなければ、どんなテクニックを駆使してもやる気を出し続けることは難しいからです。
勉強へのモチベーションは、大きく3段階に分かれています。
お子様が今どこの段階にいるかを確認して、一つひとつ段階を上げられるように導いていくことが大切です。
一つひとつ解説します。
段階1:怒られるからやる

子どもが勉強に取り組む動機として最も好ましくないのは、「怒られるから」という動機です。


このように、大きな声で怒鳴りつければ、子どもは「怒られたくない」と思って勉強に取り組みます。
周りから見ると子どもがしっかりと勉強しているように見えるので、問題がないように見えるのですが、勉強のモチベーションが「怒られるから」であることは非常に大きな問題です。
「怒られるからやる」は、勉強嫌いの温床
勉強にはある程度の強制力や、ルール作りは必要です。
「子どもに全て任せきりにしていたら、勝手にたくさん勉強するようになった。」というケースは激レアです。
しかし、子どもを叱りつけながら無理矢理に勉強させ続けるのは逆効果です。
「怒られるから勉強に取り組む」というのは、最もネガティブな動機だからです。
勉強への動機がネガティブな場合、続ければ続けるほど勉強を嫌いになってしまいます。
勉強とは、本来は楽しいものです。
学ぶことは、本来は楽しいものです。
勉強の楽しさを知ることも、勉強の一部と言えます。
「怒られるから」は、長続きしない
怒られるからという理由で勉強している子どもは、怒られなくなれば途端に勉強しなくなります。
勉強する動機がなくなるので当然です。
もう既に勉強が嫌いなっているので、チャンスがあれば勉強をサボります。
小学校高学年や中学生くらいになると、サボり方もだんだん上手くなってきます。



そして、段々と体が大きくなって力が強くなってくると、怒られても勉強をしなくなります。
何よりも、大人になって社会に出てから、まったく勉強しなくなってしまいます。
勉強嫌いを直すのは大変
一度勉強嫌いになってしまうと、そこから勉強を好きになってもらうのは本当に大変です。
勉強が好きになるようにとあれやこれやと試さなければなりませんが、それには多大な時間と労力を必要とします。
勉強を好きになってもらうには、まずは勉強に取り組んでもらう必要があります。
勉強は、わかってくるほど楽しくなってくるからです。
しかし、勉強嫌いな子どもは既に勉強にネガティブなイメージを持っているので、勉強に取り組みたくありません。
このパラドックスをなんとかしなければならないのです。
「怒られるから勉強する」という生徒は、年齢が上がれば上がるほど指導が難しくなります。
ですので、勉強に対する強制力は強すぎてはいけません。
ある程度の強制力とルール作りで勉強に取り組ませながら、ポジティブなイメージで子どもが勉強に取り組めるようサポートしてあげる必要があるのです。
ステップ2:やるべきだからやる

では、勉強へのポジティブな動機を持つためにはどうすればよいでしょう。
その答えは、「勉強する目的を持たせる」です。
勉強は手段であって、目的ではないからです。
勉強は、やりたいことをやるための手段です。
勉強は、なりたい自分になるための手段です。
子どもが勉強する目的を持っていれば、「怒られるからやる」から「やるべきだからやる」に昇格できます。
ここで初めて「自主性」や「能動性」が生まれます。
親は、「勉強しなさい!」と言い続けるのではなく、「なぜ勉強すべきなのか」「何のために勉強するのか」を、子どもに問いかけ続ける必要があります。
まずは子どもとの対話から
子どもの「やりたいこと」「なりたいもの」を発掘するために、まずは子どもと対話をしてみてください。
勉強する目的は、子どもによってそれぞれ異なります。
たとえば、「病気で苦しむ人達を助けるために、お医者さんになりたい!」と考えている子どもであればわかりやすいです。
医者になることが勉強の目的となります。
医者になることが目的、目的を達成するための手段が勉強です。
子どもがまだ勉強する目的を見つけられてないようであれば、まずすべきことは、子どもの「やりたいこと」「なりたいもの」の発掘です。
「どんなことがしたいか」「どんな大人になりたいか」「どういう人間でありたいか」「何に興味があるのか」「何が好きか」「何が得意か」「何が苦手か」。
たくさん子どもに聞いてみてください。
子どもはそれらの質問に答えることで、頭の中が整理され、言語化され、だんだんと自分のやりたいことが具体的に見えてきます。
親の希望は二の次
子どもとの対話のときは、親の希望や親の価値観は一旦隅に置いておいてください。


このように、子どもに将来を押し付けてはいけません。
押し付けてしまえば、ステップ1の「怒られるからやる」に逆戻りです。
対話の際に親がすべきことは、「問いかけること」「話を聞いてあげること」「知識を与えてあげること」です。
子どもの話をよく聞いて、「それならこういうものもあるよ。」「こんな人もいるんだよ。」「一緒に調べてみよう!」と、子どもにインプットの機会を与えてあげることです。
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
ステップ3:やりたいからやる
子どもの勉強へのモチベーションは、「やりたいからやる」という状態がベストです。
「やりたいからやる」を目指して導いてあげることが大切です。
勉強とは本来、楽しいものです。
勉強とは本来、おもしろいものです。
勉強も本気で取り組めばしっかりと辛いものではありますが、根底には楽しさとおもしろさがあります。
一方で、勉強の楽しさを知るためには、勉強に取り組み続ける必要があります。
勉強に取り組み続けるためには、できる限りポジティブに勉強に取り組む必要があります。
子どもが一度勉強の楽しさを知れば、もう親が「勉強しなさい!」と怒る必要はありません。
子どもが勉強に後ろ向きになっているときに、悩みを聞いてあげる程度の関わりで十分になります。
ここまでたどり着ければ、成長して大人になっても学ぶことをやめることはありません。
いつまでも成長し続ける大人になれるでしょう。
運良くステップ3に一気にたどり着けることもある
世の中には、勉強の楽しさを教えることが本当に上手な人がいます。
子どもの、「なんで?」「不思議!」「もっと知りたい!」を上手に引き出すことができる人がいます。
そんな人に出会えたらラッキーです!
また、普段の生活の中で強く好奇心を惹かれるものにたまたま出会って、「もっと勉強したい!」と思うこともあります。
そんなものに出会えたらラッキーです!
そうなれば、運良くひとっ飛びに「やりたいからやる」というモチベーションを手に入れることができます。
「勉強の楽しさを教えること」については、保護者の方も関われることです。
ぜひ、子どもにいろいろな体験をさせてあげて、子どもの好奇心に引っかかるものを一緒に探してあげてください。
体験は、学校の勉強とは関係のないものでも構いません。
多くの体験に出会うこと大切です。
勉強はその後でついてきます。
体験は巡り巡って学校の勉強につながっていくことが多いです。
それでも勉強する目的は持つべき
運良く一気にステップ3の「やりたいからやる」にたどり着けた場合でも、ステップ2の「やるべきだからやる」も意識させてあげてください。
どんなに楽しいと思って取り組む勉強であっても、本気で究めようと思えば大変な苦労を伴います。
どんなに好きなことでも、どうしても辛くなってしまうこともあります。
そんなときに味方になるのは、勉強する目的です。
辛いと思ったときも、「なんのために勉強していたのか」「どうなりたくて勉強していたのか」を思い出せると、それが原動力となってまた勉強を頑張ることができます。
勉強のやる気を出す26のテクニック
どんなに勉強へのモチベーションを高めていたとしても、どうしてもやる気がでないことも多いです。
ここからは、どうしてもやる気が出ないときに活用できるテクニックを紹介していきます。
ここで紹介するテクニックをすべて取り入れていただく必要はありません。
子どもの得意や不得意によって、効果があるものも効果がないものもあるからです。
実際に試してみて効果があったものは取り入れてください。
効果がなかったものは不採用にしてください。
勉強のやる気を出す26のテクニック
一つひとつ解説します。
テクニック1:睡眠時間を確保する
勉強のやる気を出すためには、睡眠時間を確保することが大切です。
眠気はやる気の大敵です。
睡眠時間を削って勉強時間を増やそうとするのは逆効果です。
寝不足の頭で長時間勉強しようとするよりも、勉強時間が短くなってしまったとしても、しっかりと集中して勉強できるようにしたほうが効果的です。
>>受験勉強中なのに眠い!すぐにできる対処法と根本的な解決策!
テクニック2:生活リズムを整える
睡眠は、時間の長さだけでなく、タイミングやリズムも大切です。
普段の睡眠時間が短く、休みの日だけ長く寝るようなリズムは、逆に体の調子を悪くします。
勉強は体力勝負でもあります。
体調が悪いと勉強に取りかかるのが億劫になりますし、勉強中も集中できません。
生活リズムを整えて、健康な状態で勉強に取り組むことが大切です。
テクニック3:とにかく勉強しはじめる
やる気は待っていても出てきません。
実際に行動することで、やる気が出てきます。
勉強に取りかかる瞬間が一番難しく、一度勉強しはじめてしまえば、やる気はだんだんと出てくるものです。
勉強のやる気を出すためには、まず、とにかく勉強しはじめることが重要です。
テクニック4:習慣化する


勉強しはじめるのが難しい場合は、勉強しはじめるための仕組みを作るのが一番良いです。
勉強しはじめるための仕組みとして一番簡単なのは、習慣化です。
夕飯や歯磨きやお風呂のように、勉強を日々の習慣として生活リズムの中に取り入れてしまうのが一番良いです。
「勉強の最初は必ず英単語暗記」というように、最初に取り組むことまで習慣化してしまうと、ほぼ無意識に勉強しはじめることができます。
テクニック5:カウントダウンする


勉強をはじめようとするときは、無意識のうちに勉強しない理由を探してしまいます。
「そうだ!部屋が汚いぞ!部屋の掃除をしなくては!」と、勉強しない理由を思いついてしまいます。
そのような無駄なことを頭に考えさせないために、セルフカウントダウンをします。
部屋に入ったら、「5,4,3,2,1,スタート!」とカウントダウンして勉強をスタートさせてみてください。
声に出してカウントダウンしたほうが、頭に余計なことを考えさせないようにすることができます。
テクニック6:切りが悪いところで区切る
1日の勉強を終わらせるときに、切りが悪いところで終わらせておくと良いです。
翌日の勉強をはじめるときに、前日の続きから取りかかれば良いので、迷いなく勉強をはじめることができます。
余計なことを考えずに勉強しはじめられるので、スムーズに勉強をスタートさせることができます。
テクニック7:「今からやる」と宣言する
「言葉」には、思ったよりも大きな力があります。

このように宣言すると、やる気が出ます。
誰かに向かって声を出して宣言することがベストですが、独り言として自分に向かって宣言しても良いでしょう。
SNS上で文字に起こして宣言しても良いでしょう。
テクニック8:得意教科からはじめる
勉強をはじめるときは、得意教科からはじめたほうがやる気が出ます。
得意教科でなくても、一番テンションがあがりそうな教科からはじめると良いでしょう。
一度勉強に取りかかりはじめてしまえば、あとはやる気が持続しやすいです。
勉強のエンジンがかかってきてから苦手教科に取り組むと、やる気に左右されずに苦手教科にも取り組むことができます。
テクニック9:学習内容が7割わかるものをやる
勉強に取り組むときは、7割くらいわかるものに取り組むとやる気が出やすいです。
無理をして難しい問題に取り組みたいと考える子どもも多いのですが、難しすぎる問題はやる気を減衰させます。
また、勉強の効率的にも、難しすぎる問題でウンウンと悩むのは良くありません。
勉強もモチベーションも、スモールステップが大切です。
「わかる」をコツコツと積み上げながら、難しい問題にも挑戦できる力をつけていくのが良いです。
テクニック10:最初の3分だけ頑張ってみる
どうしても勉強をスタートさせることができない場合は、とりあえず3分だけ頑張ってみてください。
3分タイマーをセットして、「タイマーが鳴ったら勉強終わり!」と、決めてください。
勉強は最初にスタートさせることが一番難しいので、タイマーが鳴る頃にはもうやる気が出ているはずです。
タイマーが鳴っても、タイマーを止めて、そのまま勉強を続けてください。
タイマーが鳴ったときもやる気がないようであれば、その日は思い切ってサボってしまっても良いでしょう。
テクニック11:やることリストを作る
やるべきことを可視化したほうが、勉強に取りかかりやすいです。
最初に何をやるべきか迷っている間に、やる気がどんどん消えていってしまいます。
やることリストを予め作っておいて、何も考えずに勉強しはじめられるようにしておくと良いです。
テクニック12:学習計画を立てる
学習計画を立てると、勉強をスタートさせやすいです。
学習計画といっても、すごく簡単なもので十分です。
最低限、次の2つのことを計画できると、スムーズに勉強しはじめることができます。
学習計画
- その日に取り組むこと
- 勉強をはじめる時間
繰り返しになりますが、勉強のやる気は、最初の勉強しはじめが一番難しいです。
何時に何から取り組みはじめるかだけでも決められると、勉強をスタートさせやすいです。
テクニック13:締め切りを作る


人は、目の前に明確な目標があったほうがやる気を持って取り組むことができます。
そのために、締め切りを自分で設定してしまうと良いです。
締め切り設定は、「9時まで勉強する」というような時間的なものではなく、「9時までに問題集の23ページまで終わらせる」というような、勉強内容的なものほうが良いです。
締め切りに限らず、勉強は「時間」よりも「内容」を意識して取り組んだほうが効率的です。
テクニック14:集中できる環境を作る

誘惑が多いと、勉強のやる気を途切れさせてしまう可能性が高いです。
スマートフォンやマンガ等は特に危険です。
視界に入るだけで集中力を切らせてしまうことも多いです。
誘惑を視界に入れないようにしたり、勉強しやすいように机の上を片付けたりと、勉強するための環境を作ることはとても大切です。
テクニック15:場所を変える
集中できる環境作りにも通ずるものがありますが、勉強する場所は、勉強のやる気につながる重要な要素です。

塾の自習室を利用したいという生徒はとても多いです。
自習室が人気すぎて、席をなかなか取れない塾もあるくらいです。
なかなか勉強のやる気が出ないときは、勉強する場所を考えてみるのも良いです。
ときどき勉強する場所を変えて、新鮮な気持ちで勉強してみるというのも、勉強やる気アップのテクニックです。
テクニック16:教科を変える
勉強している途中でどうしてもやる気が続かないと感じた場合は、思い切って勉強する教科を変えてしまうのも良いでしょう。
好きな教科であっても、その日のコンディションによっては前向きに取り組めないこともあります。
どうしても前向きに取り組めない場合は、スパッとやめてしまいましょう。
取り組む教科を変えると、気持ちがリフレッシュされて、やる気も復活するかもしれません。
テクニック17:適度な休憩を取る
勉強のやる気を持続させるためには、適度な休憩を取ることも大切です。
あまりに長時間集中しすぎると、頭が疲れ切ってしまい、勉強が続けられなくなってしまいます。
学習効率的にも、適度な休憩は大切です。
休憩中は、目と頭をしっかりと休めることに集中してください。
休憩中にマンガを読んだりスマートフォンを触ったりする子どもも多いのですが、それでは目と頭を休めることはできません。
リラックスしたり、体を動かしたりして、有意義な休憩時間を過ごすことが大切です。
テクニック18:仮眠を取る
眠くて勉強のやる気が続かない場合は、思い切って仮眠を取ってしまっても良いです。
繰り返しになりますが、眠気はやる気の大敵です。
また、眠気を我慢して勉強に取り組んでも、あまり成果は得られません。
仮眠を取ってスッキリした頭で勉強に取り組んだほうが効率的です。
ただし、仮眠は15分程度にします。
しっかりとタイマーをセットしておいてください。
15分以上寝てしまうと、夜眠れなくなってしまいます。
生活リズムの乱れは、勉強のやる気に悪影響があります。
テクニック19:ポモドーロテクニックを活用する
適度な休憩を取る方法として、ポモドーロテクニックを利用すると良いです。
ポモドーロテクニックとは、「25分作業して、5分休憩する」という、集中力を維持して生産性を上げるための時間管理術です。
2時間に1回程度、30分程度の長めの休憩も取ります。
ポモドーロテクニックを簡単に実行できるスマートフォンアプリも配信されています。
Apple Watch等のスマートウォッチがあると、音を出せない自習室のような場所でもタイマーを利用することができて便利です。
テクニック20:勉強を見える化する
本人が取り組んだ勉強を見える化すると、勉強へのやる気を上げることができます。
その日の成果や勉強時間を記録して、目に見える状態にすることで、より達成感を得ることができます。
スマートフォンアプリを活用すると、手軽で簡単に勉強記録を残すことができます。
テクニック21:一緒に頑張る仲間を作る
一緒に頑張る仲間を作ると、勉強のやる気をアップさせることができます。
勉強では、仲間やライバルの存在は支えになることが多いです。
学校や塾、予備校等で、同じ目標を持つ仲間を見つけられると良いです。
住んでいる場所や環境によっては、切磋琢磨できる仲間を見つけることができない場合もあります。
その場合は、ネットを活用してください。
「勉強アカ」と呼ばれる、勉強専用のアカウントをSNSで作って、インターネット上で仲間を作ることができます。
頑張っている勉強アカをフォローしてモチベーションを上げている子どもも多いです。
テクニック22:名言を読む
どうしても勉強のやる気が出ないときは、名言を読んでみるのも良いでしょう。
言葉の力は、思ったよりも強いものです。
インターネットで検索すると、いろいろな名言を読むことができます。
成功者の言葉に元気をもらって、やる気を高めてみてください。
>>受験生を応援する時によく使っているアニメのセリフ7選【元塾教室長が紹介!】
テクニック23:先輩の合格体験記を読む
特に、受験勉強のやる気が出ないときは、自分の志望校に合格した先輩の合格体験記を読んでみるのも良いでしょう。
憧れの志望校に実際に合格した先輩の言葉なので、「名言」よりも親近感を持てるかもしれません。
大手の塾や予備校のwebサイトには、多くの合格体験記が掲載されています。
先輩がどのように受験勉強に取り組んできたか、具体的な話も記載されているので、やる気アップのためだけでなく、勉強の取り組み方についても参考にすることができます。
テクニック24:目標を貼り出す
目標を書き出して、よく見えるところに貼り出しておくと、やる気が出やすいです。
目標は頭の中で考えているだけでなく、目に見えるようにすることが大切です。
いつでも目に入るところに貼り出しておけば、事あるごとに目標を思い出して頑張ることができます。
テクニック25:夢を書き出す
目標だけでなく、もっと先の未来の「夢」を書き出してみるのも良いでしょう。
将来の夢は、勉強に対するモチベーションの原動力です。
いつでも目に入るところに書き出しておくことで、勉強へのやる気をアップさせることができます。
テクニック26:夢を語る
将来の夢は、自分の心の中に留めておくだけでなく、周りの人に語ることで実現の可能性を上げることができます。
実際に言葉にすることで、頭の中にあるモヤッとした夢のイメージを、言語化することができます。
言語化することで、夢をより具体的なイメージに変換することができます。
夢や目標は、具体的であれば具体的であるほどやる気が出て、実際に行動に移すことができます。
いきなり目の前の人に夢を語るのは抵抗があるようであれば、インターネット上やSNS上で語っても構いません。
夢を言語化して、やる気につなげることが大切です。
褒める・認める・励ます・応援する
子どもがやる気を持って勉強に取り組めるかどうかは、保護者の方の協力にかかっています。
子どもは、親の影響を大きく受けるからです。
子どもがやる気を持って前向きに勉強に取り組めるよう、子どもを褒めて、認めて、励まして、応援してあげてください。
子どもが勉強にポジティブな感情を持てるかどうかが、前向きに勉強に取り組めるかどうかの分かれ道になります。
ぜひ、保護者の方が、子どもの勉強のやる気の原動力になるよう導いてあげてください。
-

-
勉強のやる気が出ない時におすすめのアニメランキングBEST10【オタク元塾教室長選出!】
元塾教室長でアニメオタクの筆者が、勉強のやる気が出ない時に見てほしいおすすめのアニメをピックアップしました。
続きを見る
まとめ
それでは、勉強へのモチベーションの上げ方と、やる気を出すための26のテクニックをまとめます。
結論
勉強のやる気アップのためには、まずは根本的なモチベーションを上げる必要があります。
そのうえで、やる気が出ないときに活用できるテクニックを身につけていくことが大切です。
勉強へのモチベーションは、大きく3段階に分かれています。
お子様が今どこの段階にいるかを確認して、一つひとつ段階を上げられるように導いていくことが大切です。
勉強の3段階のモチベーション
- 怒られるからやる
- やるべきだからやる
- やりたいからやる
やる気が出ないときに活用できるテクニックを紹介します。
すべてのテクニックを取り入れるのではなく、子どもの得意や不得意に合ったテクニックを取り入れることが大切です。
勉強のやる気を出す26のテクニック
子どもがやる気を持って勉強に取り組めるよう、保護者の方は子どもを褒めて、認めて、励まして、応援してあげてください。
今回の記事が、お子様が前向きに勉強に取り組めるようになるきっかけとなればとてもうれしいです。