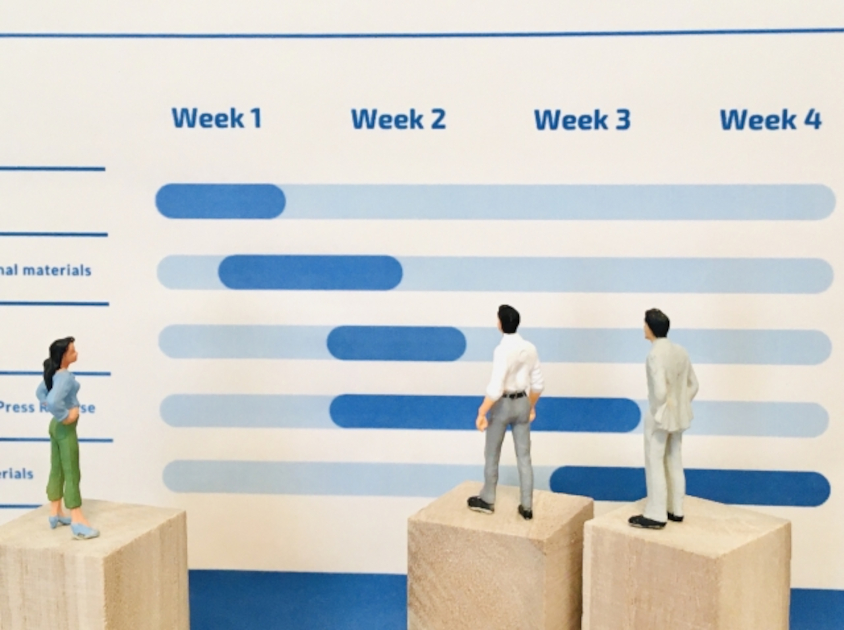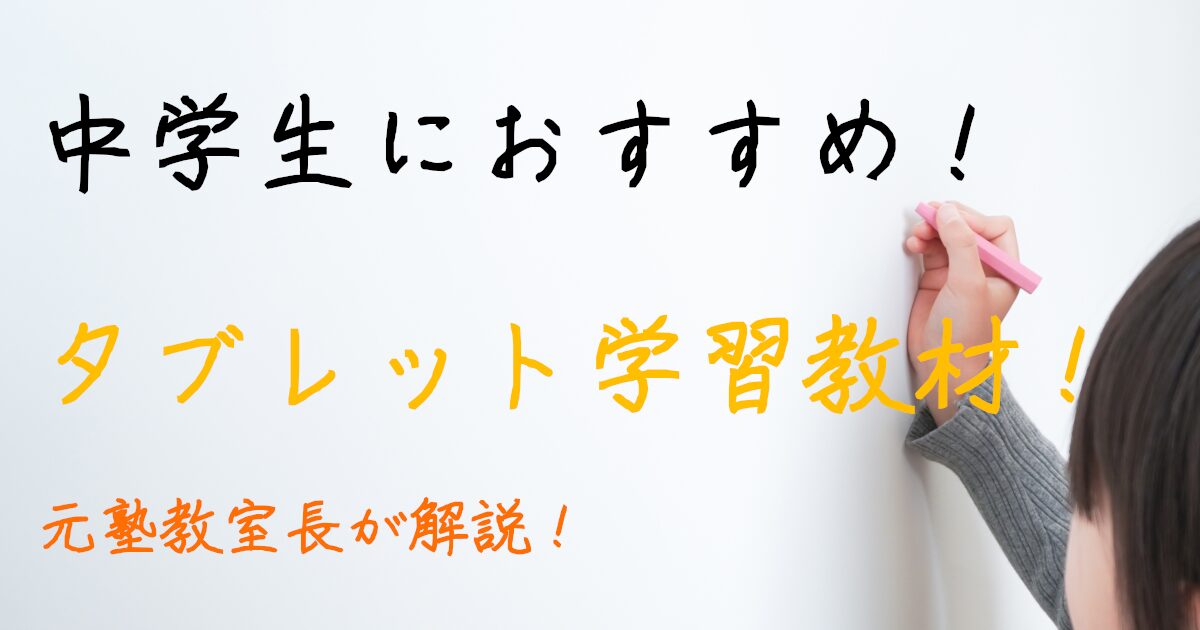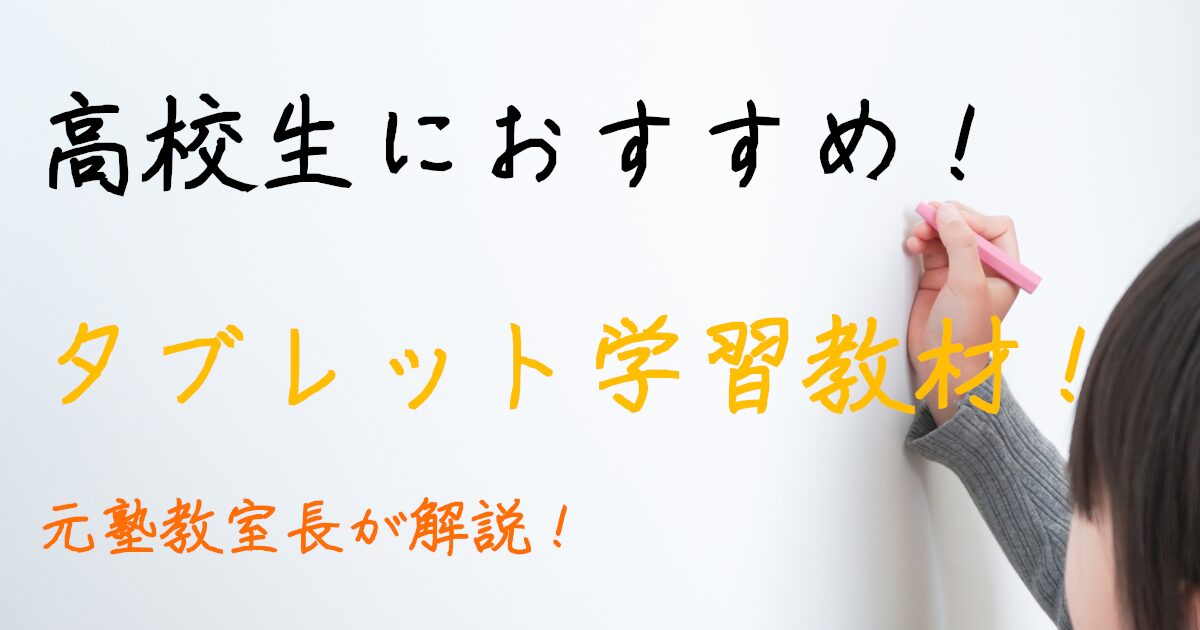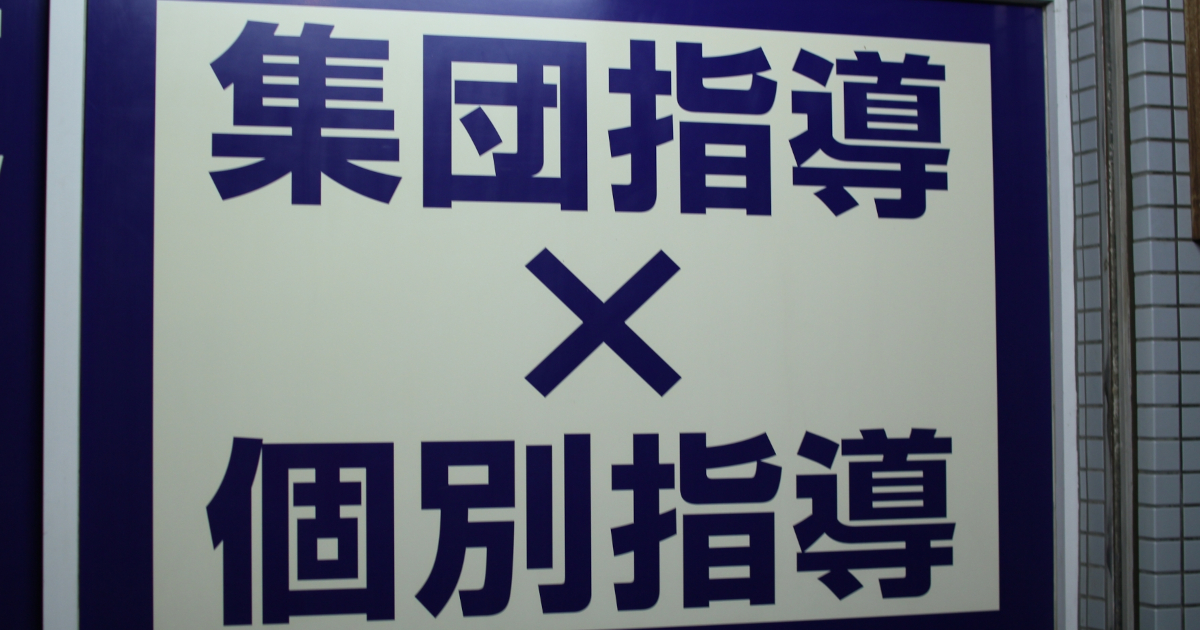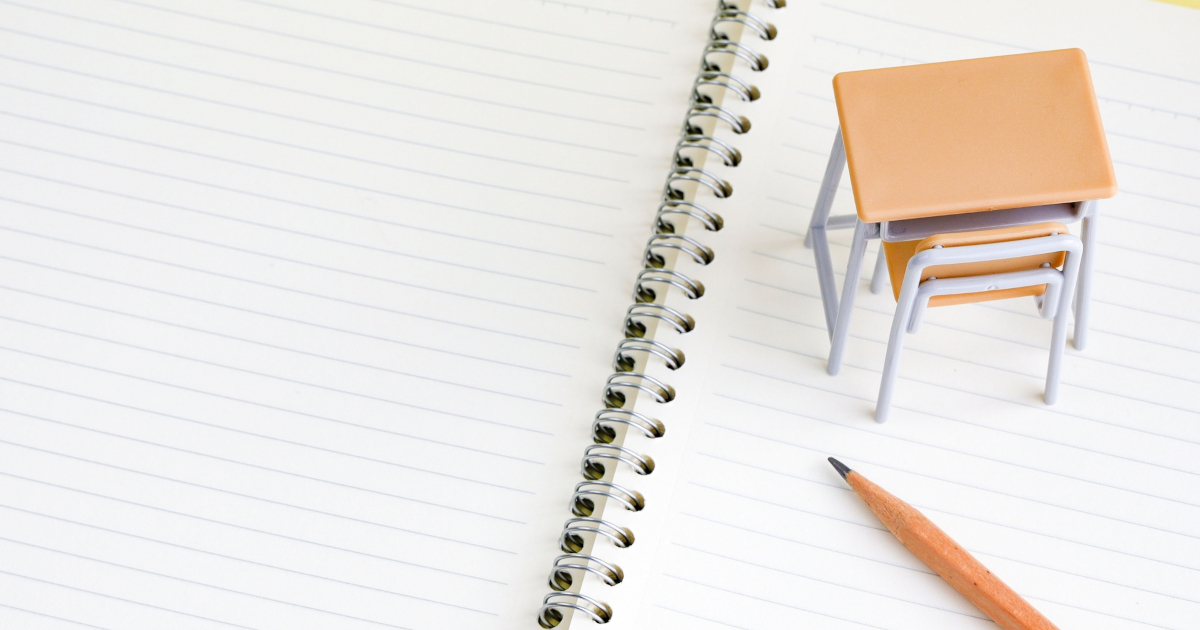こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。


通信教育は続かないという話をよく聞きます。
これから子どもに通信教育の教材を取り組ませようと検討されている保護者の方は、しっかりと続けられるか心配に思われているのではないでしょうか。
結論
通信教育やタブレット教材は、子どもに与えるだけではなかなか続けられません。
一方で、適切なサポートがあると、お金をあまりかけずに効率的に学力を伸ばすことができます。
今回は、通信教育やタブレット教材を継続的に活用して、塾以上の成果を得るためのコツを解説していきます。
最後まで読んでいただき、お子様が通信教育教材・タブレット教材を活用して、学力を伸ばしていくための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
通信教育・タブレット教材のメリット
通信教育・タブレット教材は、上手に活用することができれば、非常に効率よく学力を伸ばしていけます。
特に、最近のタブレット教材はテクノロジーやAIを活用していて、子ども一人ひとりが最適な学習に取り組めるようになってきています。
紙と鉛筆だけで勉強した時代に比べると、大きな進化を遂げています。
タブレット教材のメリット
- 復習や先取り学習がしやすい
- AIが勉強を効率化してくれる
- 場所と時間に縛られない
- 動画やアニメーションの解説がわかりやすい
- 自動採点なのですぐに復習できる
- 論理的思考力を育てられる
- 繰り返し勉強できる
- 楽しく勉強できる
紙の教材を提供している通信教育であっても、スマートフォンやタブレットも活用して学習するものが多いです。
適切に活用できれば、効率的で効果的な学習に取り組むことができます。
>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
通信教育・タブレット教材が続かない理由
通信教育・タブレット教材を続けられなかったという家庭は多いです。
各教材会社もその点には問題意識を持っているようで、いろいろな工夫を施しています。
それにも関わらず、未だに通信教育・タブレット教材を続けられない子どもが多いのも事実です。
現状では、通信教育・タブレット教材を続けられない理由を保護者がしっかりと把握して、対策を取る必要があります。
通信教育・タブレット教材が続かない理由は、主に次の6点です。
一つひとつ解説します。
理由1:自由度が高すぎる
通信教育・タブレット教材が続かない理由は、自由度が高すぎることです。
好きなときに好きなだけ取り組めるということは、嫌なときに嫌なだけサボれるということでもあります。
塾や学校であれば曜日や時間が決まっているため、簡単にサボることはできません。
サボれば先生に叱られるか、保護者に連絡が行き、保護者に叱られることになります。
一方で、通信教育やタブレット教材は、サボっても先生に叱られることはありません。
自由度が高いことは通信教育・タブレット教材の大きなメリットなのですが、逆に大きなデメリットでもあります。
理由2:一人でスケジュール管理するのは難しい
通信教育・タブレット教材は、子どもが一人でスケジュール管理するのが難しいです。
そもそも勉強のスケジュール管理はとても難しく、大人であっても苦戦するものです。
塾や家庭教師であれば、先生がカリキュラムを組んでスケジュール管理を行ってくれます。
通信教育では学習カレンダーのようなものがついてくることがありますが、子ども一人ひとりに個別に作られたスケジュールではありません。
最近のタブレット教材では、AIが子どもの学習データを集めながら個別に学習スケジュールを組んでくれるものもあります。
いろいろと便利なツールは提供されていますが、それでも学習スケジュールの管理を子どもに任せっきりにするのには無理があります。
理由3:一人で進捗管理をするのは難しい
学習スケジュールを作成できたとしても、スケジュール通りに学習を進めるための進捗管理をするのが非常に難しいです。
勉強が予定通りに進むことはほとんどありません。
学習スケジュールを作ることも大切ですが、学習進捗に合わせてスケジュールを修正していかなければ結局意味がありません。
このスケジュール修正は、スケジュールを作ることよりもずっと難しいです。
最近のタブレット教材では、AIがスケジュール修正をしてくれるものも多いです。
AIがサポートしてくれたとしても、子ども一人で進捗管理をするのは難しいです。
理由4:教材が難しすぎる
教材が難しすぎると、通信教育・タブレット教材は続きません。
わからなければ、おもしろくないからです。



勉強は、基礎基本を徹底してスモールステップで積み上げていったほうが効果的で効率的です。
基礎基本を徹底的に対策することが、応用問題や発展問題を解けるようにするための近道です。
理由5:教材に興味を持てない
教材に興味を持てないと、通信教育・タブレット教材は続きません。
興味がないものに継続して取り組むのは難しいです。
通信教育・タブレット教材にもいろいろなコンセプトの教材があるので、子どもが興味を持てそうなものを選ぶことが大切です。
理由6:モチベーションが続かない
通信教育・タブレット教材は、モチベーション管理もとても難しいです。
通信教育・タブレット教材では、人と直接会って指導してもらうことができないからです。
子どものモチベーションを上げるための工夫を各社頑張っていますが、まだまだ十分とは言えません。
現状では、子どものモチベーションを一番上げられるのは人による指導であるように感じます。
通信教育・タブレット教材で成果を得るためのコツ
通信教育・タブレット教材に継続して取り組むためには、続けられない原因をケアしていくことが大切です。
最近の通信教育・タブレット教材は非常に優秀なので、しっかりと取り組むことができれば、学習塾以上の成果が期待できます。
通信教育・タブレット教材で塾以上の成果を得るためのコツは、主に次の10個です。
成果を得るためのコツ
一つひとつ解説します。
コツ1:ルール作りをする
通信教育・タブレット教材に継続して取り組むためには、まずは家庭内でルール作りをする必要があります。
まずは学習習慣をつけることが大切であり、学習習慣をつけるためにはルール作りが効果的だからです。
「何曜日の何時から何時までは教材に取り組む時間で、もしも急な用事で取り組めない場合は、代わりにいつ取り組むのか」をルール化してしまってください。



コツ2:頑張っている部分を褒める
通信教育・タブレット教材を続けるためには、子どもが頑張っている部分をしっかりと褒めてあげることが重要です。
叱られて取り組むよりも、褒められて取り組んだほうが前向きになれるからです。
子どもが勉強をサボっているとついついイライラして叱ってしまいがちですが、イライラして叱るのは逆効果であることが多いです。
逆に、子どもを褒めるポイントを見つけるのは思ったよりも難しいので、褒めポイントを強く意識して探して、しっかりと見つけて褒めてあげる必要があります。
はじめが重要
通信教育・タブレット教材を新しくはじめた直後は、子どもは前向きに取り組む傾向があります。
ですので、取り組みはじめは褒めるポイントがたくさんあります。
取り組みはじめの時期にしっかりと褒めてあげられると、継続しやすくなります。
逆に、最初の褒めポイントをスルーしてしまうと、子どもはだんだんと飽きてきて取り組まなくなってしまいます。
教材によっては、褒めポイントを保護者宛にお知らせしてくれるものもあります。
それだけ、各教材会社も褒めることの大切さを意識しています。
コツ3:スケジュール管理をサポートする
通信教育・タブレット教材を続けるためには、保護者が子どもの学習スケジュール管理をサポートしてあげる必要があります。
先ほども解説した通り、子どもが一人で学習スケジュールを管理するのは難しいからです。
「ちゃんと取り組みなさい!」と言うだけでは子どもは取り組めません。
具体的に「いつ取り組むか」「どこからどこまで取り組むか」を、子どもと相談しながら一緒にスケジュール作りをする必要があります。
AIやアプリが自動でスケジュールを作ってくれるような教材であっても、すべてAI任せにするのではなく、自動作成されたスケジュールを親子で一緒に確認するようにしたほうが良いです。
慣れてきたら自由度を上げていく
スケジュール管理が難しい通信教育・タブレット教材ではあるのですが、逆に言えば、自分でスケジュール管理をする練習ができるとも考えられます。
はじめはキッチリとルール化して取り組ませる必要がありますが、学習習慣がついてきたら変則的なスケジュールも認めていくと良いです。
家の用事や部活、習い事のスケジュール、通信教育・タブレット教材に取り組む時間等を上手にやりくりできるようになれば、大人になっても困らないスケジュール管理能力を鍛えることができます。
スケジュール管理は親子で一緒に
学習スケジュールは毎回親子で相談しながら作るようにしてください。
保護者がスケジュール管理をまったくサポートしないのもダメですし、保護者がスケジュールをすべて作成してしまうのもダメです。
子どもが一人でスケジュール管理ができるように成長していくことが大切だからです。
スケジュール管理のすべてを子どもに任せられるようになるまでには、年単位での時間が必要になります。
保護者の負担は非常に大きくなりますが、通信教育・タブレット教材で成果を得るためには必ず必要な負担になります。
コツ4:学習進捗を確認する
通信教育・タブレット教材を続けるためには、保護者が子どもの学習進捗を確認する必要があります。
先ほども解説した通り、子どもが一人で学習進捗を管理するのは難しいからです。
最近のタブレット教材は、子どもがいつ何に取り組んだかというデータを、いつでも保護者が見られるようになっているものが多いです。
「今日はどこまで取り組んだの?」と子どもにいちいち聞かなくても進捗をチェックできるので、昔に比べるとずっと進捗管理をしやすくなりました。
予定通りに取り組めていれば褒めてあげられますし、予定が遅れてしまっていればすぐにスケジュールの修正をすることができます。
こまめなチェックが大切
子どもの学習進捗はこまめにチェックして、必要であればすぐにスケジュール修正をするようにすると良いです。
予定が大幅に遅れてしまうと、修正するのが難しいからです。
すぐに気がついてすぐに対処することで、予定が大幅に遅れてしまうことを防ぐことができます。
管理よりも対話
スケジュール作成も学習進捗管理も、保護者と子どもが対話をして一緒に考えるスタイルの方が良いです。
学習を計画通りに進めることも大切ですが、子どもが自分一人の力でスケジュールを作成し、自分自身の進捗を管理する力を育てることの方が大切だからです。
保護者が子どもに指示を出す形は良くないです。
いつまでも指示されたことをこなすだけではなく、自らの力で課題を解決する力をつけることが大切です。
常に保護者が指示を出す形にしてしまうと、自らの力で課題を解決する力を育てることができません。
保護者の負担は大きいですが、丁寧に取り組む価値があります。

このような意見をよく聞きますが、そもそも一人で勉強に取り組める子どもはほとんどいません。
大人でもほとんどいません。
大変だとは思いますが、ここは保護者の頑張りどころです。
各社、学習スケジュールや学習進捗管理をサポートするサービスをいろいろと提供してますので、上手に活用できると負担を減らすことができます。
必要なモノ
- スケジュールを書き込めるカレンダーがつく
- モデルスケジュールを提示してくれる
- アプリでスケジュールを自動生成
- AIがスケジュールを提案
- 保護者専用画面から子どもの学習履歴をチェックできる
- 子どもの学習状況をメールで報告
- 担当のコーチがつく
コツ5:学習環境を整える
通信教育・タブレット教材は自宅で取り組むことが多い以上、自宅の学習環境を整えてあげることはとても大切です。
勉強をするのに、「場」は非常に重要だからです。
自習室欲しさに塾や予備校に通う子どももいるほど、勉強する「場」は大切なものです。
少なくとも、子どもが勉強に取り組んでいる間は、集中して勉強に取り組める環境を作ってあげる必要があります。
コツ6:子どものやる気ポイントを考える
通信教育・タブレット教材を続けるためには、子どもが興味を持つポイントや、やる気が上がるポイントを考えることが大切です。
興味があるものや好きなもの、やる気が上がりやすいものほど継続して続けやすいからです。
各教材会社は、子どものやる気を上げられるようにいろいろな工夫をしています。
たとえば、次のような工夫をしている通信教育・タブレット教材が多いです。
やる気アップの工夫
- 子どもが興味を持ちやすいテーマを題材にする
- 子どもが「面白い!」と思えるような付録を付ける
- 子どもの頑張りを称賛する
- 勉強にゲーム性を持たせる
- 頑張るとプレゼントをもらえる
各社が様々な工夫をしてるので、子どものやる気ポイントを押してくれそうなものを探してみてください。
まずは子どものやる気ポイントを知ることから
まずは子どものやる気ポイントを見つけてください。
やる気ポイントを押してあげれば、子どもは驚くほど自分から勉強に取り組んでくれます。
「勉強しなさい!」と、言われて勉強に取り組むよりも、自分で興味を持って勉強に取り組んだほうが深い学びにつながります。
学習内容も定着しやすくなります。
上手に活用できれば、子どもの主体的な学びにつなげることもできます。
子どもが主体的に学べるようになれば、スケジュール管理や学習管理をする保護者の負担も小さくなります。
通信教育の「やる気アップの工夫」は、しっかりとチェックしておくと良いです。
>>勉強しない子どもに試してほしい!親子でできる“やる気アップの仕組み”
>>勉強のやる気を出す26のテクニックとモチベーションの上げ方
>>勉強のやる気が出ない時におすすめのアニメランキングBEST10【オタク元塾教室長選出!】
コツ7:適切なレベルの教材を選ぶ
通信教育・タブレット教材を続けるためには、適切なレベルの教材を選ぶことが大切です。
教材のレベルが子どもに合っていなければ、どんな工夫も無駄になってしまいます。
進研ゼミやZ会のように、レベル別のコースが設置されている教材もあります。
迷ったら簡単な方
難易度に迷ったら、「少し簡単すぎるかもしれない」というレベルからはじめるのが良いです。
最初のうちはスケジュール作成や学習進捗管理に慣れる必要もあるので、勉強に強い負担を感じてしまうと早い段階で挫折してしまうからです。
7割くらいはスラスラと理解できる内容で、3割くらいは少し考えないと理解できない内容というバランスが良いでしょう。
ある程度続けて、「やっぱり簡単すぎる!」と思ったら、別の教材に乗り換えるか、同じ教材の中でコース変更をすると良いです。
なお、コース変更は無料であることが多いです。
教材の乗り換えについては、1年契約などの長期契約になっている場合は、乗り換える時期を考える必要があります。
契約期間の途中で解約する場合、教材によっては途中解約料金が必要になることがあります。
コツ8:目的に合った教材を選ぶ
通信教育・タブレット教材は、教材によってコンセプトが異なりますので、子どもの目的に合った教材を選ぶことが大切です。
目的に合った教材を選べると、効果が高いです。
たとえば、次のようなコンセプトの通信教育・タブレット教材があります。
必要なモノ
- 学校の授業のサポート
- 受験対策中心
- 基礎基本を定着させる
- 難問まで解けるようにする
- 苦手を克服する
- 演習中心
- 授業中心
- 契約している学年の学習内容が中心
- 他学年の学習内容にも取り組める
- 思考力や発想力を育てる
コツ9:自由度の高さをフル活用する
通信教育・タブレット教材で大きな成果を得るために、自由度の高さをフル活用できると良いです。
自由度の高さが、学習塾と比べての大きなアドバンテージだからです。
取り組む時間は完全に自由ですし、取り組むスピードや、取り組む学習内容も自由が高いです。
小学校から高校までの内容をいつでも学習できるような教材もあります。
得意な教科は学年を超えて先取り学習をしたり、苦手な教科は学年をさかのぼって復習したりすることもできます。
本気で頑張れば、ずっとに苦手だった教科を1から復習して得意に変えることもできますし、得意な教科はずっと上の学年の学習内容まで先取りすることもできてしまいます。
自由度が高いからこそスケジュール作成や学習管理が大変なわけですが、自由度の高さをフル活用すれば、塾では絶対に得られないような成果を得ることができます。
最近はAI等を駆使して、子ども一人ひとりに最適な学習ができるようにサポートしてくれる教材が増えています。
保護者の負担が大きいのはネックになると思いますが、使いこなすことができれば塾よりも高い成果を得ることができます。
コツ10:体験受講を活用する

いろいろな通信教育・タブレット教材を比較して、「これだ!」と思ったサービスを見つけることができたとしても、必ず体験受講をしてください。
また、どちらの教材にすべきか迷ってしまったという場合は、どちらも体験受講してみることをおすすめします。
実際に手で触って肌で感じてみなければ、最後のところはわからないからです。
無料で体験受講ができる通信教育教材が多いので、必ず活用してください。
▼あわせて読みたい
>>小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
▼あわせて読みたい
>>中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
▼あわせて読みたい
>>高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
学習塾も検討する
学習塾は通信教育・タブレット教材と比べると費用が高いですが、勉強面や受験面でのサポートが手厚いです。
通信教育・タブレット教材では続けられなさそうということであれば、学習塾に通うことも検討すべきです。
料金を安く抑えようとするばかりに、効果のない勉強に取り組んでしまっては時間の無駄になってしまいます。
子どもと家庭にとってどのような学習方法が合っているのか、幅広い選択肢を検討してみてください。
大手学習塾の紹介
大手の学習塾をいくつか紹介します。
近所にあるようであれば、まずは資料請求や体験授業などの問い合わせをしてみると良いです。
便宜上大手の塾を紹介しますが、大手の塾が良い塾とは限りません。
同じ名前の塾でも、教室によって雰囲気も質もまったく異なります。
地元の小さな塾も含めて情報を集めて、必ず体験授業を受けてから入塾を決めるようにしてください。
※料金は地域や校舎によっても異なります。詳細は必ず公式サイトを確認してください。
▼この表は横にスクロールできます。
| 塾名 | 公式サイト | エリア | 指導タイプ | 料金 | 特徴 | 体験授業 |
| 森塾 | 【森塾】 |
関東 静岡 新潟 |
個別指導 |
週1回、月3回授業
|
|
▼最大1ヶ月無料の体験授業に申込む 【森塾】 |
| 個別指導塾WAYS | 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |
関東 近畿 |
個別指導 | 非公開 |
|
▼120分の無料体験指導に申込む 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |
| 個別教室のトライ | 【個別教室のトライ】 |
日本全国 | 個別指導 |
1コマ120分
|
|
▼無料体験に申込む 【個別教室のトライ】 |
| 明光義塾 | 個別指導の明光義塾 |
日本全国 | 個別指導 |
週1回税込み
|
|
▼無料 >>無料体験に申込む |
| 個別指導塾WAM | 個別指導塾WAM |
日本全国 | 個別指導 | 非公開 |
|
▼無料体験に申し込む 個別指導塾WAM |
| スクールIE | スクールIE | 日本全国 | 個別指導 |
週1回税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 京都 大阪 兵庫 福岡 |
個別指導 |
1コマ80分
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 東進ハイスクール 東進衛星予備校 |
東進ハイスクール・東進衛星予備校 |
日本全国 | 映像授業 |
税込み
|
|
▼無料1日体験に申し込む 東進ハイスクール・東進衛星予備校 |
| 湘南ゼミナール | 湘南ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
集団指導 |
税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 臨海セミナー | 臨海セミナー | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
集団指導 |
税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 栄光ゼミナール | 栄光ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 宮城 京都 |
集団指導 | 教室によって異なる |
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| Z会進学教室 | Z会進学教室 | 東京 神奈川 埼玉 大阪 兵庫 京都 奈良 静岡 宮城 |
集団指導 | コースによって異なる |
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
▼あわせて読みたい
>>個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】
-

-
個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】
続きを見る
▼あわせて読みたい
>>失敗しない個別指導塾の選び方!9つのポイント
-

-
失敗しない個別指導塾の選び方!9つのポイント
続きを見る
▼あわせて読みたい
>>集団指導の塾の選び方!失敗しないための15のポイント【元塾教室長が解説!】
-

-
集団指導の塾の選び方!失敗しないための15のポイント【元塾教室長が解説!】
続きを見る
まとめ
それでは、通信教育やタブレット教材を継続的に活用して、塾以上の成果を得るためのコツについての解説をまとめます。
結論
通信教育やタブレット教材は、子どもに与えるだけではなかなか続けられません。
一方で、適切なサポートがあると、お金をあまりかけずに効率的に学力を伸ばすことができます。
通信教育・タブレット教材は、上手に活用することができれば、非常に効率よく学力を伸ばしていけます。
通信教育:タブレット教材のメリット
- 復習や先取り学習がしやすい
- AIが勉強を効率化してくれる(タブレット)
- 場所と時間に縛られない
- 動画やアニメーションの解説がわかりやすい(タブレット)
- 自動採点なのですぐに復習できる(タブレット)
- 論理的思考力を育てられる
- 繰り返し勉強できる
- 楽しく勉強できる
通信教育・タブレット教材が続かない理由は、主に次の6点です。
通信教育が続かない理由
- 自由度が高すぎる
- 一人でスケジュール管理するのは難しい
- 一人で進捗管理をするのは難しい
- 教材が難しすぎる
- 教材に興味を持てない
- モチベーションが続かない
通信教育・タブレット教材で塾以上の成果を得るためのコツは、主に次の10個です。
成果を得るためのコツ
- ルール作りをする
- 頑張っている部分を褒める
- スケジュール管理をサポートする
- 学習進捗を確認する
- 学習環境を整える
- 子どものやる気ポイントを考える
- 適切なレベルの教材を選ぶ
- 目的に合った教材を選ぶ
- 自由度の高さをフル活用する
- 体験受講を活用する
今回の記事が、お子様が通信教育教材・タブレット教材を活用して、学力を伸ばしていくきっかけとなればとてもうれしいです。
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
-

-
個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】
続きを見る