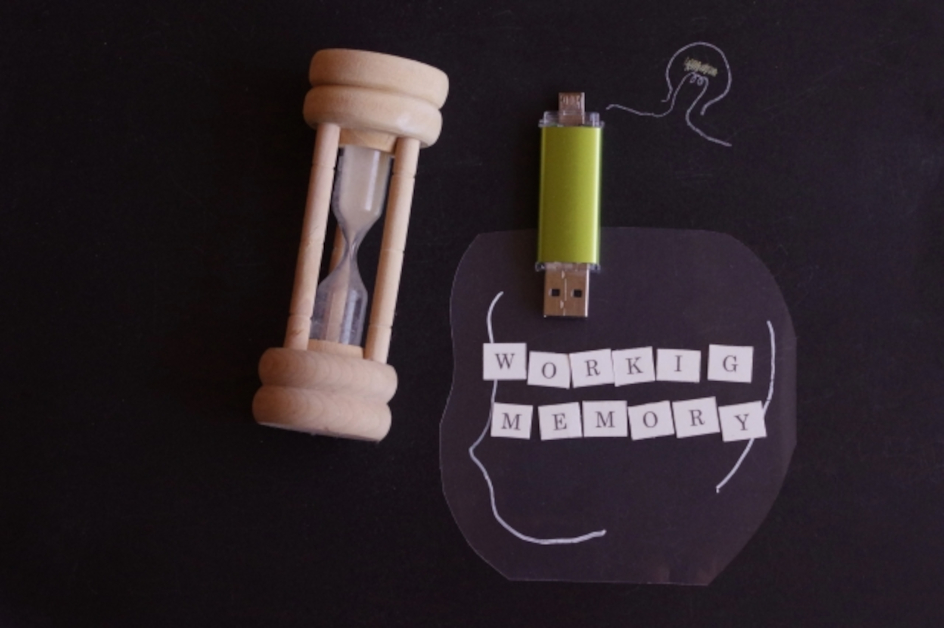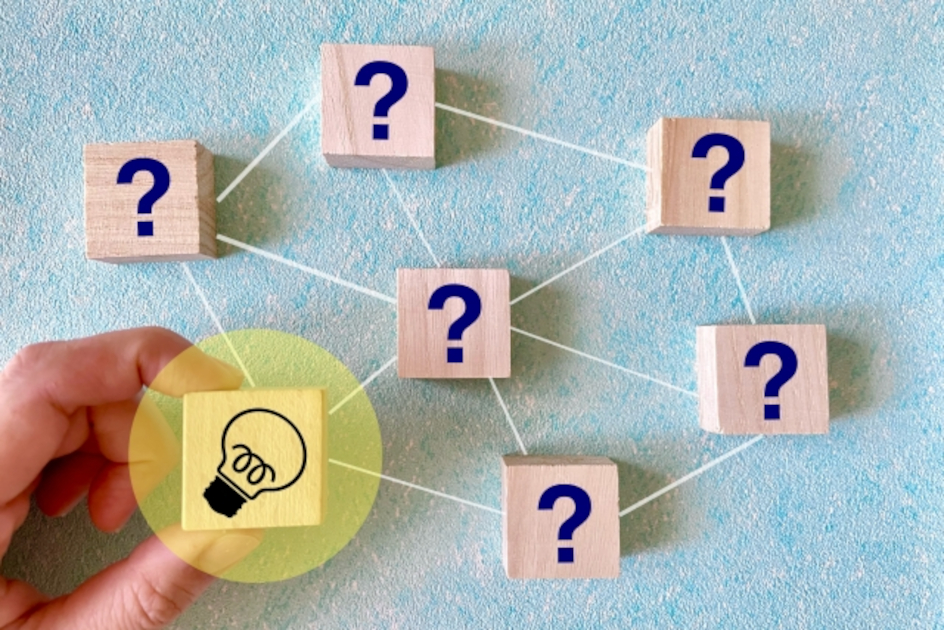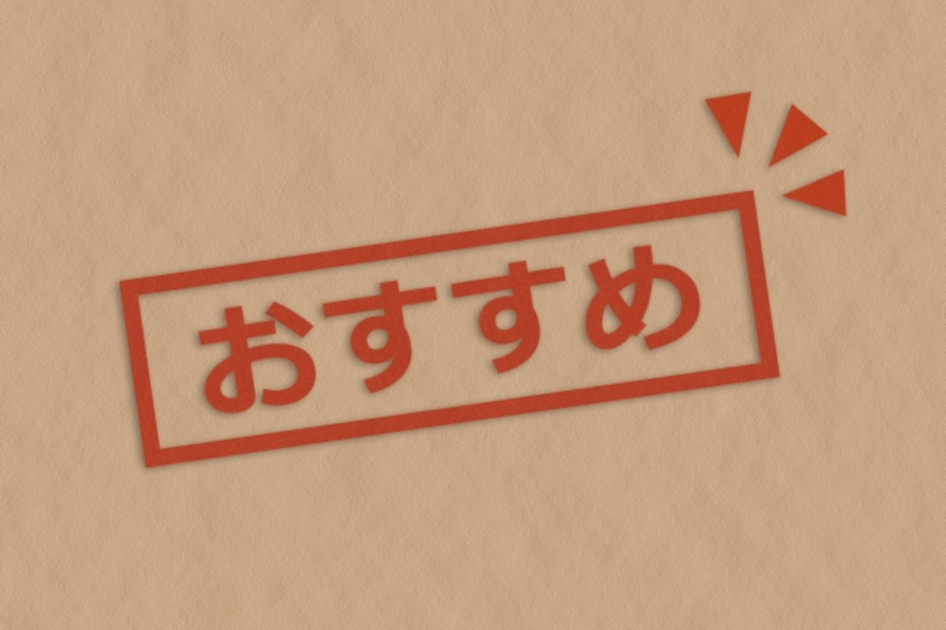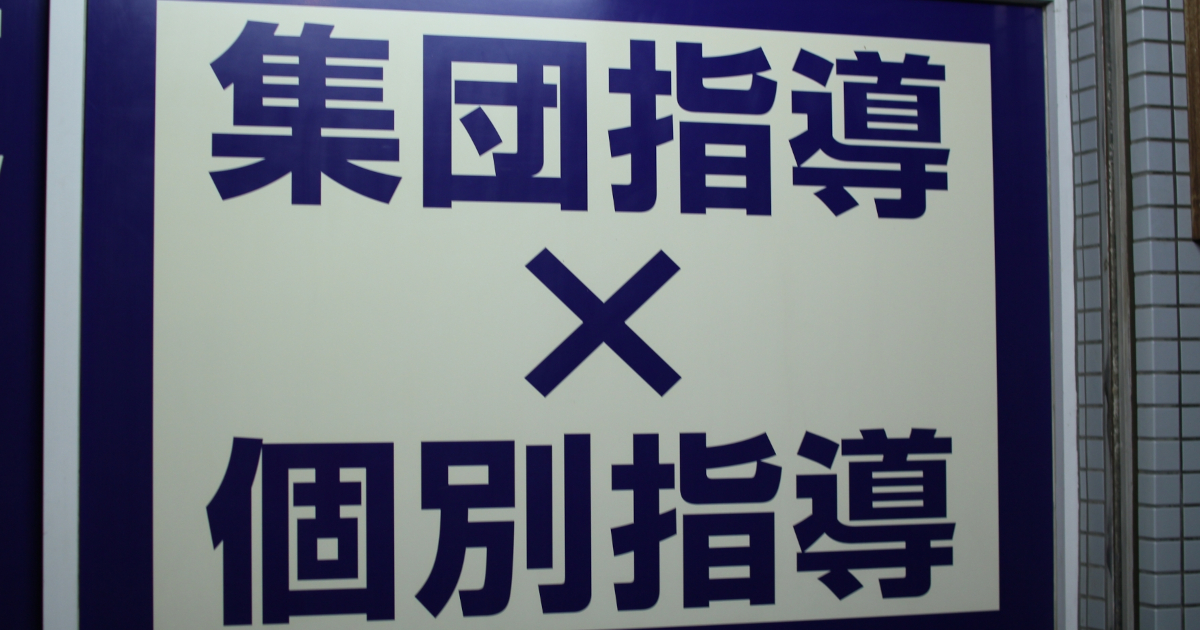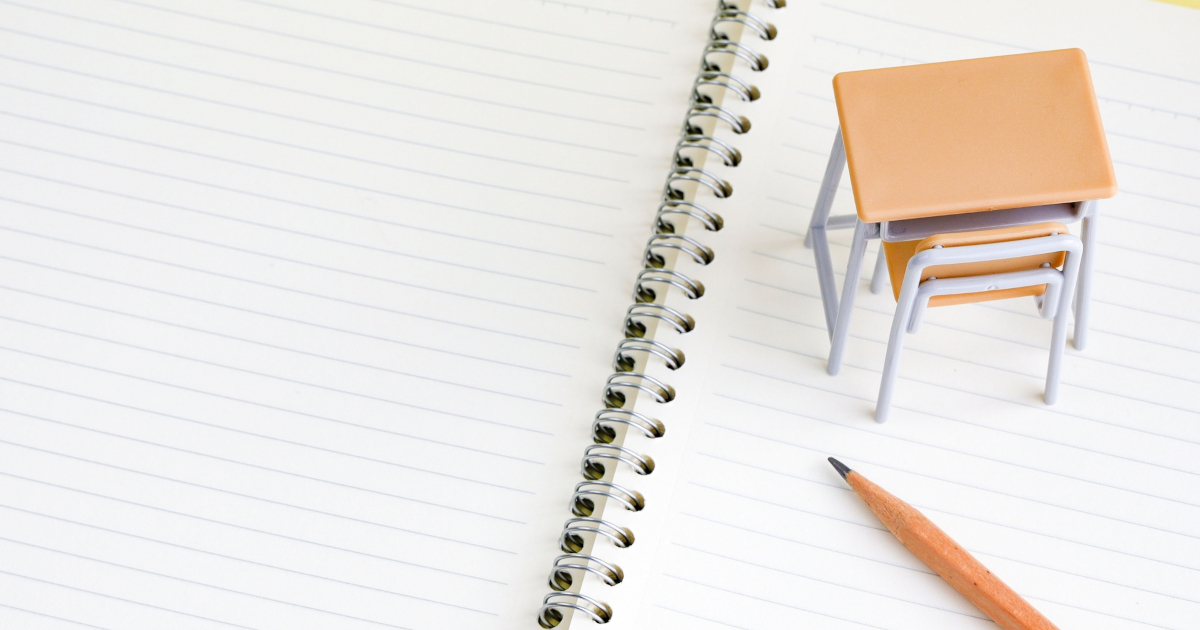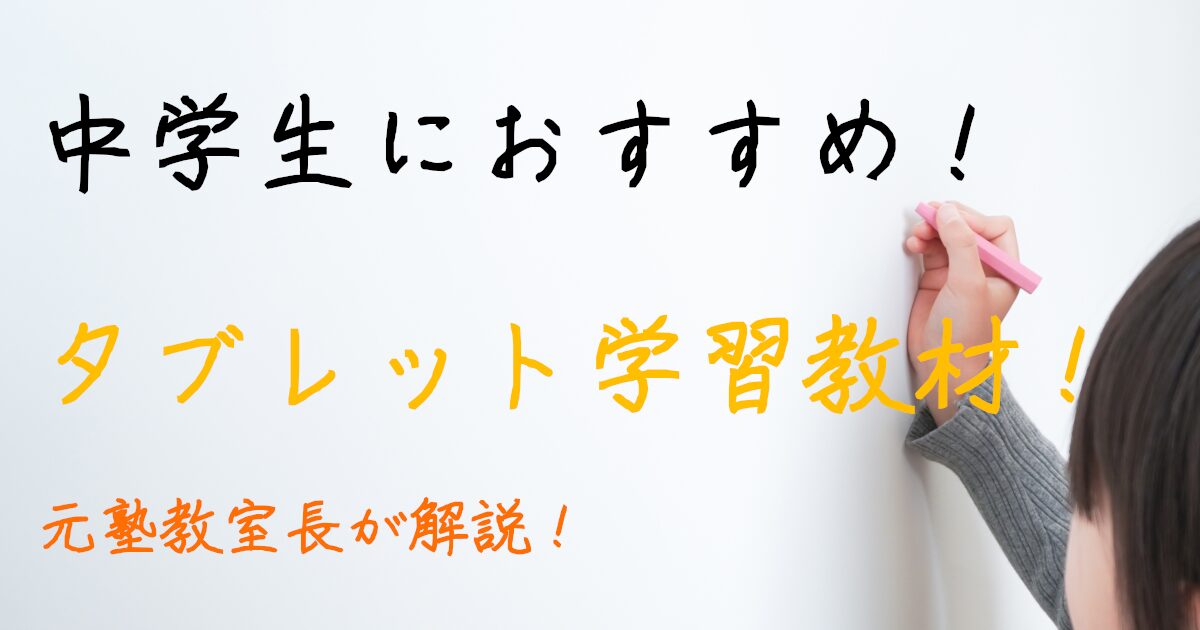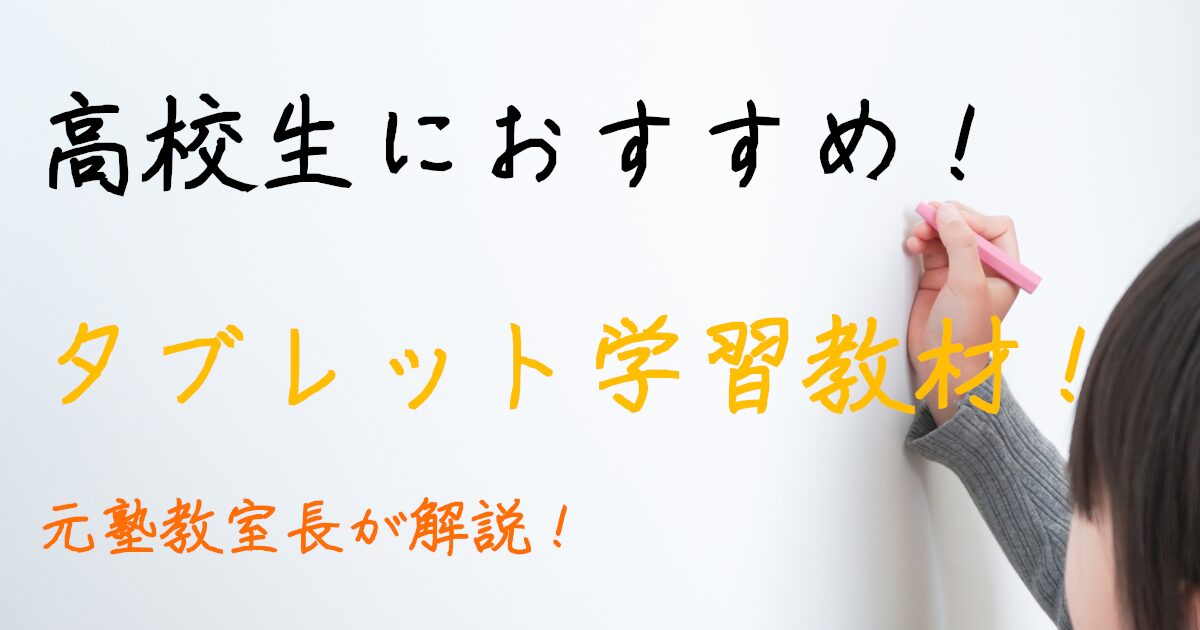こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。


勉強が難しくなってきて、覚えなければならないことも増えてきて、暗記が苦手になってしまったと悩む中学生は多いです。
保護者の方も、学校の成績のことや受験のことを考えると心配になってしまいますよね。
結論
暗記学習で一番大切なのは、勉強量と努力量です。
十分な努力量を確保したうえで『暗記のコツ』を意識できると、効率よく長期記憶にすることができます。
今回は、効率的な暗記方法や暗記のコツについて解説します。
最後まで読んでいただき、お子様が暗記を得意にして、勉強への自信を深めていただくための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
長期記憶を目指すべき理由
学校の勉強としての暗記学習では、『短期記憶』よりも『長期記憶』を目指すべきです。
長期記憶とは、年単位にわたって長期間保持される記憶のことです。
長期記憶を目指すべき理由は、主に次の5点です。
長期記憶を目指すべき理由
一つひとつ解説します。
理由1:その場でだけ使えても意味がない
暗記したものをその場でだけ使えても、そのあとすぐに忘れてしまっては意味がありません。
暗記テストで点数を取ることが目的ではないからです。
その場限りの暗記では、授業の小テストで点数を取れても定期テストでは点数を取れませんし、受験でも点数を取ることができません。
逆に、長期記憶にすることができれば、定期テストや受験でも役に立ちますし、大人になって社会に出てからも活用することができます。
記憶は、長期記憶になって初めて意味のあるものとなります。
理由2:知識が多いほど思考力が上がる
長期記憶としての知識が増えていくに従って、思考力も上がっていきます。
何かを論理的に考えるときには、前提として知識が必要になるからです。
「応用問題が苦手です!」と言う中学生も、ほとんどの場合は基礎知識が不足しています。
応用問題も基礎知識からです。
ネット検索では思考力にはつながらない



思考は基本的には頭の中で行います。
そのため、思考するための知識は頭の中に入っている必要があります。
必要に応じてネット検索もあわせて活用できると、さらに多くのことを深く思考できるようになります。
論理的な思考力は重要性を増している。
今の学校教育では、知識一辺倒ではなく、「探究的な学習」や「問題解決能力」が重要視されてきています。
社会でも学校でも、「言われたことを正確にこなす」よりも、「自ら課題を発見し、解決していく」ことが重視されるようになっています。
2021年に文部科学省から公表された「学習指導要領の趣旨の実現に向けた 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する 参考資料 (令和3年3月版) 」には、次のように記載されています。
問題発見・解決能力については、各教科等において、物事の中から問題を見いだし、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法を探して計画を立て、結果を予測しながら実行し、振り返って次の問題発見・解決につなげていく過程を重視した深い学びの実現を図ることを通じて、各教科等のそれぞれの分野における問題の発見・解決に必要な力を身に付けられるようにするとともに、総合的な学習(探究)の時間における横断的・総合的な探究課題や、特別活動における集団や自己の生活上の課題に取り組むことなどを通じて、各教科等で身に付けた力を統合的に活用できるようにすることが重要です。
これからは、学校でも社会でも、自ら論理的に考えて課題を解決していく力が評価されるようになります。
また、答えのない問いに向き合うような「探究的な学習」が重要視されています。
知識そのものももちろん大切ですが、思考力や想像力などの本質的な学力のほうが求められるようになってきています。
理由3:知識を積み上げるほど勉強がわかる
長期記憶が増えていって知識が積み上がってくると、勉強がどんどんわかるようになっていきます。
長期記憶が増えていくことで知識と知識が結びついていきますし、思考力も上がっていくからです。
勉強がわかるようになると勉強が楽しくなってきます。
勉強が楽しくなると、さらに勉強を頑張って知識を積み上げていくことができます。
理由4:知識を積み上げるほど暗記が得意になる
長期記憶が増えていって知識が積み上がってくると、暗記がさらに得意になっていきます。
知識と知識を結びつけることで、暗記がラクになるからです。
たとえば、「潮」という漢字を小学1年生の時点で覚えるのは難しいです。
画数が多く、複雑な字だからです。
しかし、「氵」と「朝」をあらかじめ知っている状態で「潮」という漢字を覚えるのであればどうでしょうか。
「氵」と「朝」をただ組み合わせるだけでよいので、簡単に暗記することができます。
このように、長期記憶を増やすことで暗記をさらに得意にすることができます。
理由5:自信になる
長期記憶を増やして知識を積み上げていくと、自信になります。
知っていることが増えていくことを実感できますし、テストでも点数を取れるようになるからです。
暗記や勉強に自信が持てるようになると、勉強面でも生活面でもいろいろな挑戦をしてみようと思えるようになります。
この自信を大人になるまで育てていければ、社会に出てからもいろいろなことに挑戦しながら活躍できるようになる可能性が高いです。
長期記憶にするための暗記のコツ
それでは、ここからは長期記憶にするための具体的な暗記方法のコツを19個紹介します。
暗記方法19個のコツ
一つひとつ解説します。
コツ1:まずは量
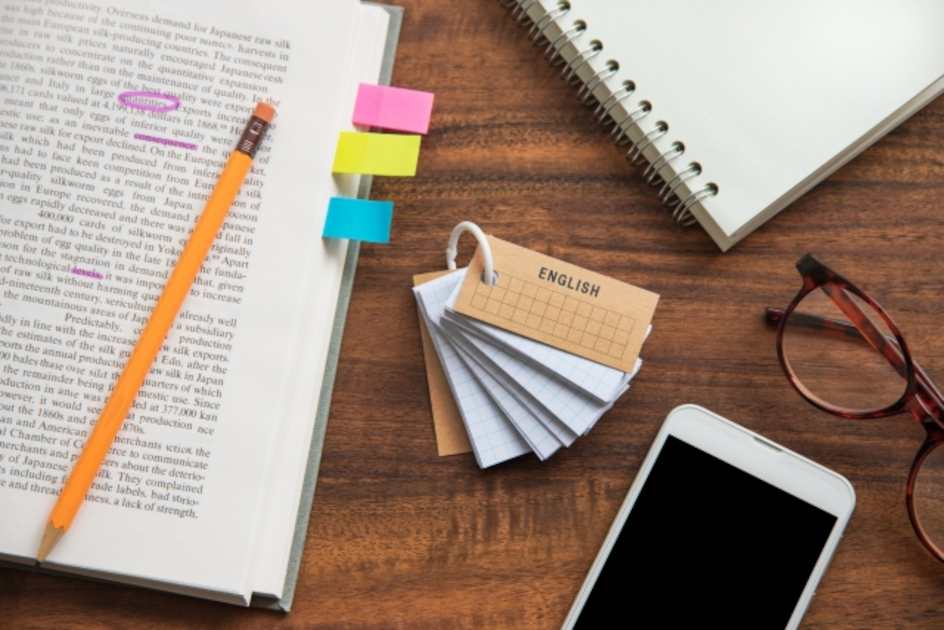
いきなり出鼻をくじいてしまいますが、暗記の苦手を克服する一番のコツは「勉強量」です。
つまり、「努力」です。
これで、勉強量を確保するだけで、体感でだいたい95%くらいの中高生が暗記の苦手を克服できます。
『これで全部完全解決!誰でもラクして暗記できる!』という記事を求められていた場合はごめんなさい、そんな方法はありません。
そんな教材が売られていたとしたら詐欺なので、絶対に購入しないでください。
必要な努力量を知らない
さて、塾では毎年、何度も何度も次のような会話を生徒と交わすことになります。




子どもたちは予想以上に、成果を得るために必要な努力量を知りません。
まずはそこを認識させる必要があります。
暗記が得意な生徒は量をこなしている
私が塾で働いていたときは、生徒の英単語アプリの学習履歴をチェックできました。
その履歴を見てみると、「暗記が得意です。」と言っている生徒は、しっかりと量をこなしていました。
多いときには、1日1000問以上取り組んでいました。
1日に2000問以上取り組む日もあります。
すごいですよね!
対して、「暗記が苦手です。」と言っている生徒の学習履歴はスカスカでした。
3日に1回、100問程度です。
まず前提として、子どもたちには正しい努力量を知ってもらわなければなりません。
目標を立てて取り組んでみる
「まずは1日100問!1週間続けてみよう!」と、目標を立てます。
1日100問は多いように感じますが、アプリなどを利用して取り組めばそれほどでもありません。
毎日取り組めると、生徒も目に見えて「覚えた!」という実感を持てます。
覚えたという実感が持てれば、「頑張ればちゃんと覚えられる!」という自信につながります。
コツの前に努力
もちろん、暗記を効率化するコツは存在します。
ですが、それらのコツは、前提として「勉強量」と「努力量」あってのものです。
正しい暗記の勉強方法を知ったうえで、しっかりと努力をするのがベストです。
コツ2:ルールを決めて習慣化する
暗記の勉強は、ルールを決めて習慣化することが大切です。
暗記は日々の積み重ねが大切だからです。
思い立ったときに突然たくさん取り組んでも覚えられませんし、長期記憶にすることはできません。
毎日毎日コツコツと覚えていく必要があります。
習慣化するのは思った以上に難しいので、ルールを決めてしまうことをおすすめします。
「毎日夕飯前の30分間は暗記学習に取り組む!」というようなルールを決めてしまいましょう。
夕飯や歯磨きやお風呂のように、暗記学習を日々の習慣として生活リズムの中に取り入れてしまうのが一番良いです。
歯磨きをしないと気持ち悪く感じるように、暗記学習に取り組まないと気持ち悪いと感じるまで習慣化できると良いです。
コツ3:スキマ時間を利用する
特に部活や学校行事が忙しい場合は、スキマ時間を活用できると習慣化しやすいです。
暗記は数分間のちょっとしたスキマ時間に取り組むだけでも効果があります。
「このスキマ時間は暗記学習に取り組む」と決めてしまうと取り組みやすいです。
スキマ時間の例
- 電車やバスなどの移動時間
- お風呂が空くまでの10分
- 夕飯ができるまでの10分
- 寝る直前の5分
- 学校の昼休み
コツ4:「暗記」よりも「理解」を目指す
長期記憶にするためには、「暗記」よりも「理解」を目指すことが大切です。
意味のない丸暗記では、すぐに忘れてしまうからです。
数学の公式を暗記するのであれば、その公式でどのようなことが求められるのかや、なぜその公式が成り立つのかといった、公式の意味を理解することが大切です。
歴史の人物の名前を暗記するのであれば、その人が「いつ」「何をして」「その結果どのようになったか」というような流れを理解することが大切です。
暗記が苦手な子どもは、ただ単に「徳川家康、徳川家康、徳川家康」と暗記してしまうので、「1603年に征夷大将軍に任じられ、江戸幕府を開いたの誰でしょう。」という質問に対して、「徳川家康」と答えることができません。
ただ単純な公式暗記や用語暗記には意味がありません。
少し遠回りに感じるかもしれませんが、暗記する用語や公式をしっかりと理解したほうが結果的には近道になります。
コツ5:書く・聞く・音読
暗記学習では、「書く」「聞く」「音読」が効果的です。
本や教科書を見て、黙読だけで覚えようとする子どももいるのですが、目以外の感覚も活用して覚えたほうが頭に残りやすいです。
耳や手を活用する
たとえば、英単語の暗記であれば、英語を読み上げてくれるアプリ等を使うと耳も使って暗記することができます。
そういったアプリを使わなくても、自分で音読すれば口を使って覚えられますし、自分の声を耳で聞いて覚えることができます。
用語や漢字を紙に書いて勉強すれば、手の感覚を使って覚えることもできます。
紙に書きながら音読するのも良いでしょう。
使い分けることも大切
書くのには時間がかかりますので、必ずしもすべてを書いて覚えるべきではありません。
特になかなか覚えられないものを書きながら覚えて、そうでないものは音読して覚えるなど、状況によって使い分けられるとより良いです。
コツ6:他のものと関連付けて覚える
暗記をするときは、他のものと関連付けて覚えると効果的です。
思い出したいものを忘れてしまったとしても、関連したものから連想して思い出すことができるからです。
私は人の名前を覚えるのが苦手なので、よく何かに関連付けて覚えています。
たとえば、「高崎さん」という方の名前は、「群馬県の高崎市(夏にすごく暑くなる場所です)」と関連付けて覚えています。
うっかり高崎さんの名前を忘れてしまった場合は群馬から連想できますし、うっかり夏にすごく暑くなる群馬県の都市の名前を忘れてしまった場合は高崎さんから連想することができます。
連想できそうなものと一緒に関連付けて暗記ができると、いざ忘れてしまったときも安心です。
コツ7:図や表にして覚える
暗記はただの文字情報だけでなく、図や表にして覚えると覚えやすいことも多いです。
特に、順序があるものや、種類ごとに分類して覚える必要があるものは図や表と相性が良いです。
植物の分類や、堆積岩や火成岩の分類、江戸時代の改革の特徴等の暗記で効果を発揮します。
図や表にすると、表のどの辺りに書いてあったかというような「場所の情報」も関連付けられるので、うっかり忘れてしまったときにも思い出しやすくなります。
コツ8:イメージと一緒に覚える
暗記は文字情報だけでなく、写真(画像)や動画で覚えるのも効果的です。
理科や社会の資料などは、画像や動画などのイメージで暗記したほうが覚えやすいです。
写真や動画のイメージは印象が強く、頭に残りやすいです。
最近はスマートフォンやタブレットを利用して勉強に取り組むことができるので、写真や動画に手軽にアクセスすることができます。
上手に活用して、「文字情報+イメージ情報」で暗記ができると、長期記憶にしやすいです。
コツ9:テストでアウトプット
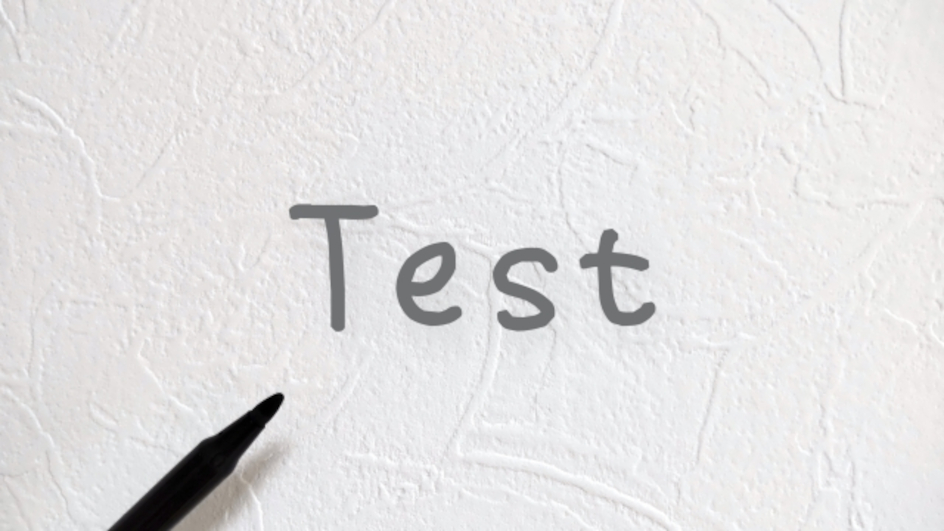
暗記は頭の中にインプットしていく勉強ではあるのですが、実際に頭の中から紙の上にアウトプットできるかどうか確認しながら取り組むと効率的です。
特に暗記が苦手な子どもは、ひたすら全部10回ずつ書き取りをして覚えようとします。
しかし、インプットだけでは絶対に勉強はできるようになりません。
切りの良いところでテストをして、アウトプットの練習をする必要があります。
アウトプットの方法
アウトプットの一番簡単な方法は、答えを手で隠した状態で思い出せるかどうか確認するという方法です。
一番手っ取り早くテストできます。
答えを蛍光ペンで塗りつぶして、赤シートや緑シートをかぶせてテストする方法でも良いです。
繰り返すことが大事
大事なことは、テストをしたあとに、できなかった問題をチェックしておくことです。
できなかった問題に付箋を貼っておくのも良いでしょう。
そして、できなかった問題だけをもう一度インプットしていきます。
それが終わったら、できなかった問題だけを再びテストします。
再テストでできなかった問題をチェックしておきます。
チェックした問題だけをもう一度インプットします。
これの繰り返しです。
すべての正解できたら完了です!
コツ10:人に教える
暗記のアウトプットにために、覚えた内容を人に教えるというのもとても効果的です。
人に教えることで、覚えたことを口からアウトプットできるからです。
また、人に教えていると、自分では完璧に暗記できたと思っていたことも、思ったよりもちゃんと暗記できていなかったことに気づけることもあります。
暗記や理解が浅いことに気づいたら、改めて復習して暗記し直すこともできます。
相手が聞いていなくても大丈夫


相手が話を聞いていなくても、背中に向かって話しても、壁に向かって独り言として話しても効果があります。
声に出してアウトプットすることが重要です。
コツ11:最初から完璧を目指さない

暗記は、最初は「大体覚えた」程度を目指しましょう。
最初から何度も何度も繰り返して書いて、「これでもう完璧絶対に二度と忘れない絶対に二度と忘れない絶対に二度と忘れない!!!」を目指す必要はありません。
完璧を目指してしまうと、5個くらい覚えたところで辛くなってしまうと思います。
最初から思いつめてはいけません。
コツ12:一度忘れて思い出す





このように、忘れてしまっとことを思い出したときが一番覚えますし、長期記憶になりやすいです。
暗記学習をしていると、覚えたことを何度も忘れてしまってイライラすることもありますが、一度忘れることは大切なことです。
一度忘れてから思い出すことで、記憶はより強くなります。
コツ13:何度も繰り返す

「大体覚えた⇒テストする⇒忘れた⇒思い出す⇒大体覚える⇒テストする⇒忘れる⇒思い出す⇒大体覚える⇒テストする⇒忘れる⇒・・・・・」
これを何度も繰り返すことで、どんどん頭の中に強い記憶として刻まれていきます。
長期記憶にするためには、忘れては思い出すを何度も繰り返すことが大切です。
テスト前日に覚えても意味がない
生徒に暗記の宿題を出すと、小テストの前日か当日だけ勉強してくる生徒が多いのですが、これは非常に効率が悪いです。
当日だけ頑張って勉強しても、「一度忘れてから思い出す」ということができないからです。
仮にその場では暗記できて小テストの点数が良かったとしても、次の日にはもう忘れてしまいます。
小テストで点数を取るために暗記の勉強をしているわけではありません。
今の勉強方法で定期テストの時にも答えられるかどうか、入試のときにも答えられるかどうか、もっと先でも覚えていられるかどうかをよく考えて取り組む必要があります。
繰り返しになりますが、一度で完璧に覚えることを目標にするのではなく、「大体覚えた」を何度も何度も繰り返すほうが効率的に暗記することができます。
コツ14:目に触れるところに貼っておく
特に暗記したいことは、部屋の壁やドアなどの目に触れやすいところに貼っておくと効果的です。
日常的に目に触れるので、自然と何度も何度も繰り返し暗記することができます。
貼ってある内容を覚えられたら別のものを貼ったりと、貼っておく内容を定期的に取り替えるとより効果的です。
コツ15:アプリを活用する

暗記学習はアプリを活用することをおすすめします。
最近の暗記アプリは非常に優秀で、暗記の効率がとても良いからです。
アプリを使って学習すると、自然とインプットとアウトプットを繰り返すことができます。
アプリにもよりますが、間違えた問題を一覧にして表示してくれたり、正答率の悪い問題を集中して出題してくれるようなアプリもあります。
また、程よいタイミングで復習できるように問題を自動で選んで出題してくれるようなアプリもあります。
電車の移動時間や、ちょっとしたスキマ時間にも取り組めるので非常に便利です。
最近はタブレット教材や通信教育教材の暗記アプリも優秀です。
おすすめの英単語アプリ
暗記アプリの中でも特に人気が高いのは、英単語暗記アプリです。
たとえば、中高生が普段の勉強や英検対策として英単語を暗記ができる、『英単語アプリ mikan』というアプリが便利です。
大学入試へ向けての英単語暗記であれば『ターゲットの友 英単語アプリ』が便利です。
無料でダウンロードできるので、試してみることをおすすめします。
コツ16:語呂合わせで覚える

順序や並び順を覚える場合や、グループ分けして覚えなくてはいけないものは、語呂合わせで覚えることをおすすめします。
元素周期表の、「水兵リーベ僕の船・・・」というのは有名ですね。
「水(水素H)兵(ヘリウムHe)リ(リチウムLi)ーベ(ベリリウムBe)僕(ホウ素B、炭素C)の(窒素N、酸素O)船(フッ素F、ネオンNe)・・・」と、覚えるやつですね。
これで原子番号1から順番に、元素の並びを覚えることができます。
もちろん、ベリリウムという元素の名前や、ホウ素の元素記号がBであることなどは別途覚える必要がありますが、語呂合わせがあるだけで暗記はグッとラクにになります。
年号の語呂合わせは自作がおすすめ
年号なども、語呂合わせで覚える人が多いです。
「いよ!国だ!(1492年)アメリカ大陸発見!」といったように暗記すれば、「せんよんひゃくきゅうじゅうにねんアメリカ大陸発見」と覚えるよりもずっとラクです。
年号に関しては、自分で語呂合わせを考えることもおすすめします。
自分で語呂合わせを考えると愛着もわきますし、忘れづらいです。
QuizKnockさんの動画で、年号の語呂合わせを作る動画があるので参考にしてみてください。
この動画を見れば、「1221年承久の乱」は二度と忘れないでしょう!
コツ17:以前覚えたものと関連させる

暗記は、以前覚えたことと関連付けて覚えると効果的です。
特に、歴史はストーリーになっているので、一つ思い出せれば芋づる式にいろいろと思い出せることがあります。
「織田信長」という名前だけを覚えるのではなく、「桶狭間の戦いで今川義元を討ち取った」「長篠の戦いで鉄砲を活用して武田軍に勝利した」「本能寺の変で明智光秀に裏切られた」のように関連情報と一緒に暗記しておくと良いです。
以前覚えたことと関連付けて暗記できると、たとえばテストの時に「明智光秀」をド忘れしてしまったとしても、織田信長から関連させて記憶を辿っていけば思い出せるかもしれません。
繰り返すという意味でも良い
関連させて暗記することは、「何度も繰り返す」という意味でも良いです。
新しいことを暗記しながら、以前に覚えた関連事項と結びつければ、以前に覚えたものを繰り返し暗記し直すことにもなります。
一見遠回りに思われるかもしれませんが、以前覚えたものと関連させて新しいこと覚えると、効率的に長期記憶にすることができます。
コツ18:体を動かす

有酸素運動をしながら暗記の勉強をすると暗記しやすいと言われています。
それほど大きな違いがあるわけではありませんが、試してみると良いでしょう。
たとえば、ただ英単語を音読するのではなく、歩き回りながら音読してみるとよいでしょう。
また、ランニング中にアプリなどで覚えたい用語などの音声を流してみると良いのではないでしょうか。
コツ19:寝る前に取り組む

記憶は寝ている間に整理されると言われています。
そのため、寝る前に暗記学習に取り組んで、寝ている間に脳が記憶を整理できるようにすると良いです。

このように言って、一夜漬けをしようとする子どもも多いです。
一夜漬けの暗記は、テストが終わったらきれいサッパリすべて忘れても良いという場合には効果があります。
ただし、テストが終わったらきれいサッパリすべて忘れてしまいます。
短期記憶にしかなりません。
長期記憶にする必要がある
確かな長期記憶にするためには、一夜漬けではまったく効果がありません。
寝て忘れてしまったら、また復習をして思い出せばよいのです。
先程も解説した通り、一度忘れて思い出すことはとても大切です。
覚えて寝て、忘れてまた思い出して寝て、また忘れて繰り返して繰り返して、そうして確かな長期記憶にしていきましょう。
暗記学習を習慣化するためにおすすめの学習サービス
暗記学習は、習慣化してコツコツと努力を重ねていくことが大切です。
一方で、部活や学校行事で忙しくしている中学生が、自分だけの力で勉強を習慣化させるのは難しいです。
勉強を習慣化させるために、塾などの学習サービスを利用するのも効果的です。
ここからは、暗記学習を習慣化するためにおすすめの学習サービスを紹介していきます。
おすすめ1:学習塾

暗記学習を習慣化するのであれば、学習塾がおすすめです。
学習塾に通えば宿題が毎回出ますし、英単語暗記や漢字暗記等の宿題も出してもらえます。
毎回の授業で小テストがある塾も多いので、自然とインプットとアウトプットを繰り返しながら暗記学習に取り組むことができます。
また、学習塾であれば、学校の勉強や受験についてもトータルでサポートしてもらえるので安心です。
デメリットは、費用がかなり高額になることです。
毎月かかる固定費となりますので、無理なく続けられる料金かどうかよく検討する必要があります。
また、部活が忙しい子どもにとっては、塾に通う時間を作れるかどうかもポイントになります。
学習塾の特徴
- 毎回暗記の宿題が出る
- 授業ごとに小テストでアウトプットできる
- 勉強や受験をトータルでサポートしてもらえる
- 費用が高い
- オンラインという選択肢もある
大手学習塾の紹介
大手の学習塾をいくつか紹介します。
近所にあるようであれば、まずは資料請求や体験授業などの問い合わせをしてみると良いです。
便宜上大手の塾を紹介しますが、大手の塾が良い塾とは限りません。
同じ名前の塾でも、教室によって雰囲気も質もまったく異なります。
地元の小さな塾も含めて情報を集めて、必ず体験授業を受けてから入塾を決めるようにしてください。
※料金は地域や校舎によっても異なります。詳細は必ず公式サイトを確認してください。
▼この表は横にスクロールできます。
| 塾名 | 公式サイト | エリア | 指導タイプ | 料金 | 特徴 | 体験授業 |
| 森塾 | 【森塾】 |
関東 静岡 新潟 |
個別指導 |
週1回、月3回授業
|
|
▼最大1ヶ月無料の体験授業に申込む 【森塾】 |
| 個別指導塾WAYS | 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |
関東 近畿 |
個別指導 | 非公開 |
|
▼120分の無料体験指導に申込む 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |
| 個別教室のトライ | 【個別教室のトライ】 |
日本全国 | 個別指導 |
1コマ120分
|
|
▼無料体験に申込む 【個別教室のトライ】 |
| 明光義塾 | 個別指導の明光義塾 |
日本全国 | 個別指導 |
週1回税込み
|
|
▼無料 >>無料体験に申込む |
| 個別指導塾WAM | 個別指導塾WAM |
日本全国 | 個別指導 | 非公開 |
|
▼無料体験に申し込む 個別指導塾WAM |
| スクールIE | スクールIE | 日本全国 | 個別指導 |
週1回税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 京都 大阪 兵庫 福岡 |
個別指導 |
1コマ80分
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 東進ハイスクール 東進衛星予備校 |
東進ハイスクール・東進衛星予備校 |
日本全国 | 映像授業 |
税込み
|
|
▼無料1日体験に申し込む 東進ハイスクール・東進衛星予備校 |
| 湘南ゼミナール | 湘南ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
集団指導 |
税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 臨海セミナー | 臨海セミナー | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
集団指導 |
税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 栄光ゼミナール | 栄光ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 宮城 京都 |
集団指導 | 教室によって異なる |
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| Z会進学教室 | Z会進学教室 | 東京 神奈川 埼玉 大阪 兵庫 京都 奈良 静岡 宮城 |
集団指導 | コースによって異なる |
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
▼あわせて読みたい
>>個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】
-

-
個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】
続きを見る
▼あわせて読みたい
>>失敗しない個別指導塾の選び方!9つのポイント
-

-
失敗しない個別指導塾の選び方!9つのポイント
続きを見る
▼あわせて読みたい
>>集団指導の塾の選び方!失敗しないための15のポイント【元塾教室長が解説!】
-

-
集団指導の塾の選び方!失敗しないための15のポイント【元塾教室長が解説!】
続きを見る
オンライン個別指導・オンライン家庭教師もおすすめ!
通える距離に良い塾がないということであれば、オンライン家庭教師・オンライン個別指導のようなサービスを選ぶこともできます。
オンラインであれば、住んでいる場所に関係なくいろいろな講師の授業を受けることができるため、子どもにピッタリの先生に出会える可能性が高いです。
また、授業時間に融通が利くサービスも多いので、部活が忙しい子どもでも利用しやすいです。
オンライン個別指導塾・オンライン家庭教師の特徴
- 日本全国の講師から先生を選べる
- マンツーマン授業
- 費用が高い
- 特化塾もある
おすすめのオンライン家庭教師
- オンライン家庭教師WAM

※対面型個別指導塾に近い指導! - 【e-Live】

※やる気とモチベーションを育てる! - オンライン家庭教師ガンバ

※勉強のやり方から手取り足取り指導!
オンライン個別指導・オンライン家庭教師については、『オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】』で詳しく解説しています。
-

-
オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】
続きを見る
おすすめ2:タブレット教材

暗記学習を習慣化するのであれば、タブレット教材もおすすめです。
最近のタブレット教材はAIを活用しているので、非常に効率的に暗記学習に取り組むことができるからです。
AIが定期テストに向けての学習計画を作成してくれたり、普段の取り組みから学習到達度を測って今取り組むべき問題を選んで出題してくれたりと、昔に比べて遥かに効率的になっています。
1回の学習時間が15分や30分などの短い時間で設定されている教材が多いので、スキマ時間を活かして勉強に取り組むことができます。
暗記学習にとどまらず、学校の授業の予習復習から定期テスト直前の対策まで幅広く利用することができます。
タブレット教材は費用がそれほど高くないのも魅力的です。
タブレット教材の特徴
- 料金が安い
- AIによって演習を効率化
- スキマ時間を活かせる
▼あわせて読みたい
>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
-

-
タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
続きを見る
成績目標点別おすすめのタブレット教材
- 平均点を目指すなら
塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】
※苦手克服に特化!担当コーチがつく! - 学年上位を目指すなら
【進研ゼミ中学講座】
※学校の予習復習・定期テスト対策に特化! - 学年最上位を目指すなら
Z会
※学年最上位を目指せる!
タブレット学習教材については、『小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】』『中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』『高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】』で解説しています。
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
まとめ
それでは、効率的な暗記方法や暗記のコツについての解説をまとめます。
結論
暗記学習で一番大切なのは、勉強量と努力量です。
十分な努力量を確保したうえで『暗記のコツ』を意識できると、効率よく長期記憶にすることができます。
学校の勉強としての暗記学習では、『短期記憶』よりも『長期記憶』を目指すべきです。
長期記憶とは、年単位にわたって長期間保持される記憶のことです。
長期記憶を目指すべき理由は、主に次の5点です。
長期記憶を目指すべき理由
- その場でだけ使えても意味がない
- 知識が多いほど思考力が上がる
- 知識を積み上げるほど勉強がわかる
- 知識を積み上げるほど暗記が得意になる
- 自信になる
長期記憶にするための具体的な暗記方法のコツを19個紹介しました。
暗記方法19個のコツ
- まずは量
- ルールを決めて習慣化する
- スキマ時間を利用する
- 「暗記」よりも「理解」を目指す
- 書く・聞く・音読
- 他のものと関連付けて覚える
- 図や表にして覚える
- イメージと一緒に覚える
- テストでアウトプット
- 人に教える
- 最初から完璧を目指さない
- 一度忘れて思い出す
- 何度も繰り返す
- 目に触れるところに貼っておく
- アプリを活用する
- 語呂合わせで覚える
- 以前覚えたものと関連させる
- 体を動かす
- 寝る前に取り組む
暗記学習を習慣化するためにおすすめの学習サービスも紹介しました。
今回の記事が、お子様が暗記を得意にして、勉強への自信を深めていくきっかけとなればとてもうれしいです。
-

-
オンライン家庭教師おすすめ人気13選!【2025年最新版!】
続きを見る
-

-
小学生におすすめのタブレット学習教材10選!【2025年最新版徹底比較!】
続きを見る
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!【2025年最新版!】
続きを見る