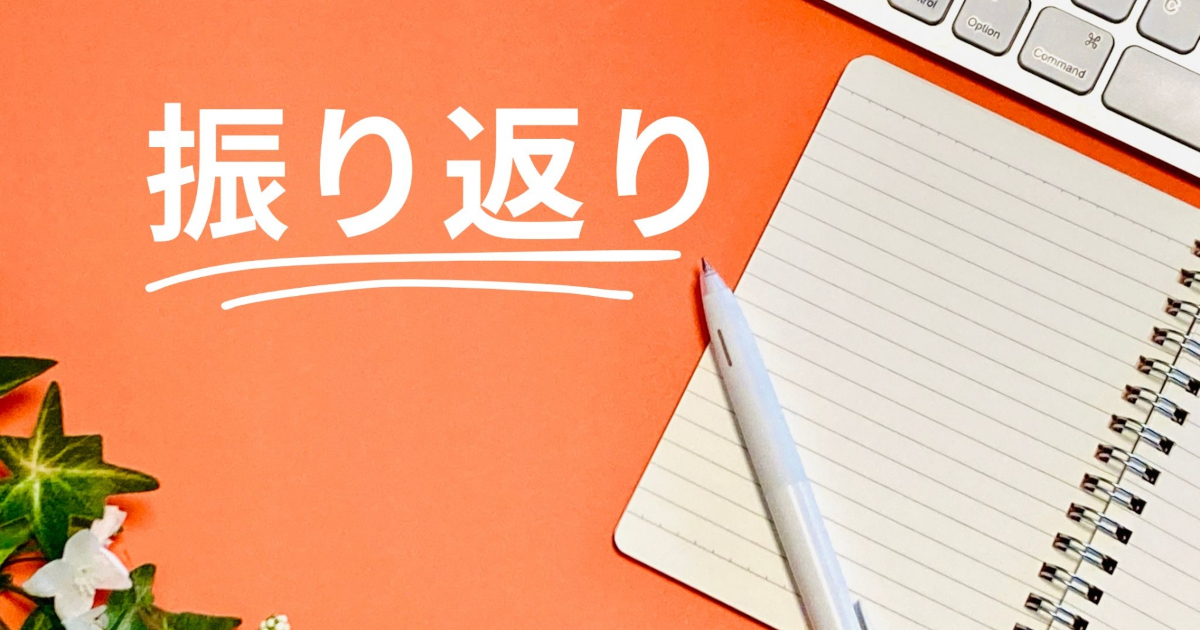こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

定期テストで悪い点数を取ってしまうと落ち込んでしまうのです。
いつもよりも勉強を頑張った教科がうまくいかなかった場合はなおさらです。
保護者の方としては、どのようにしてあげれば良いのかと悩まれているのではないでしょうか。
結論
定期テストで点数が落ちてしまっても大丈夫です。
むしろ成績アップのチャンスなので、ステップアップの材料としてしまいましょう!
今回は、定期テストでうまくいかなかったらどうするかというお話を解説します。
最後まで読んでいただき、お子様が次回の定期テストで最高得点を取るための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団指導塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
定期テストでうまくいかなかったとしても大丈夫な理由

定期テストでうまくいかなかったとしても大丈夫です。
全然問題ありません。
定期テストでうまくいかなかったとしても大丈夫な理由は、主に次の3つです。
定期テストでうまくいかなかったとしても大丈夫な理由
理由1:1回のテストで何かが決まるわけではない
今回の定期テストでうまくいかなかったとしても、それで何かが決まってしまうわけではありません。
1回の定期テストの結果で受験できる高校が決まるわけではありませんし、内申点(通知表の評定)が決まるわけでもありません。
通知表の評定だって、複数回の定期テストや普段の授業態度、提出課題などを総合的に見て決められます。
定期テストがちょっとうまくいかなかったことくらい、大したことではありません。
▼あわせて読みたい
>>高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!
もっと未来も考えてみる



学校の成績も、受験の合否も、人生の通過点でしかありません。
そして、辿り着きたい場所への道は一つではありません。
一つの道が閉ざされてしまったとしても、他の道を選ぶこともできます。
たった1回の定期テストの結果で、人生が決定づけられるわけではありません。
理由2:ずっとうまくいき続けることはない



一度も失敗せずにずっとうまくいき続ける人はいません。
むしろ、成功者こそ多くの失敗を経験しているものです。
うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。
そういうものです。
理由3:次のテストに向けてのステップアップにできる
成功するためには失敗が必要です。
失敗は成功の母です。
何かを改善するためには、一度失敗する必要があるからです。
失敗しないための一番の方法は、挑戦しないことです。
しかし、挑戦しなければ成長しません。
挑戦して、失敗して、改善することで成長することができます。
「定期テストでうまくいかなかったと落ち込んでいる」ということは、少なくとも挑戦したのです。
頑張ったから悔しさを感じているのです。
それは素敵なことです。
今回はうまくいかなかったかもしれませんが、これは成長のチャンスです。
うまくいかなかったことを上手に利用して、次の定期テストで過去最高得点を目指しましょう!
定期テストでうまくいかなかったときのNGな行動

定期テストでうまくいかなかったときに取ってはいけない行動は、主に次の3つです。
NG行動1:叱る・責める
定期テストでうまくいかなかったときに一番してはいけないことは、叱ること・責めることです。
特に、本人が試験前の勉強を頑張っていた場合は、叱ったり責めたりすることでどんどん成績が落ちていきます。
「頑張ったのにうまくいかなかった」と、
既に本人が落ちこでいる上に、追い打ちをかけることになるからです。
子どもは、叱られたり責められたりすることで、勉強やテストに対する感情がどんどんネガティブになっていきます。
その結果、前向きに勉強に取り組むことができなくなってしまいます。
勉強しない大人にしないために
学生のときに叱られながらイヤイヤ勉強に取り組んでいると、大学受験が終わった途端にまったく勉強しない大人になってしまう可能性が高いです。
今までの社会とは異なり、これからの社会では、大人になってからも勉強し続けなければ生き残れません。
社会の変化が激しく、常に新しいことをアップデートしていく必要があるからです。
大人になってからも勉強し続けるためには、勉強の楽しさを知ったり、勉強に関する成功体験を積んだりする必要があります。
子どもを叱ったり責めたりすると、その両方を台無しにしてしまいます。
まずは勉強する意味を考える


そもそも全然勉強に取り組めないようであれば、まずは勉強する意味を一緒に考える必要があるかもしれません。
人は、意義を感じないことには前向きになれないものです。
将来どのようなことをしたいか、どのように生きたいか、親子で対話する機会を作り、努力することの意味を探すことが大切です。
時間はかかりますが、「なぜ勉強するのか」「なんのために勉強するのか」を、子どもと一緒に考えてみてください。
▼あわせて読みたい
>>将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント
▼あわせて読みたい
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
NG行動2:落ち込み続ける
定期テストでうまくいかなったときであっても、落ち込み続けるのは良くありません。
落ち込んでいるだけでは何も変わりませんし、前に進むことができないからです。
先程解説したとおり、定期テストでうまくいかなかったとしても全然問題ありません。
何度も何度も励まして、気持ちを前向きにしてあげてください。
NG行動3:現実から目を背ける
「定期テストでうまくいかなかった」と、
落ち込み続けるのもNGですが、だからといって現実から目を背けてもいけません。
自暴自棄になって、全部投げ出してしまってもいけません。
うまくいかなかったという現実をしっかりと見つめなければ、次に向けての改善ができないからです。
すっかり落ち込んでしまっているときは難しいかもしれませんが、ある程度回復してきたら、まずは現実を直視しなければなりません。
現実を直視することができれば、逆に次の定期テストで大きな飛躍ができるチャンスになります。
定期テストでうまくいかなかったときにするべきこと
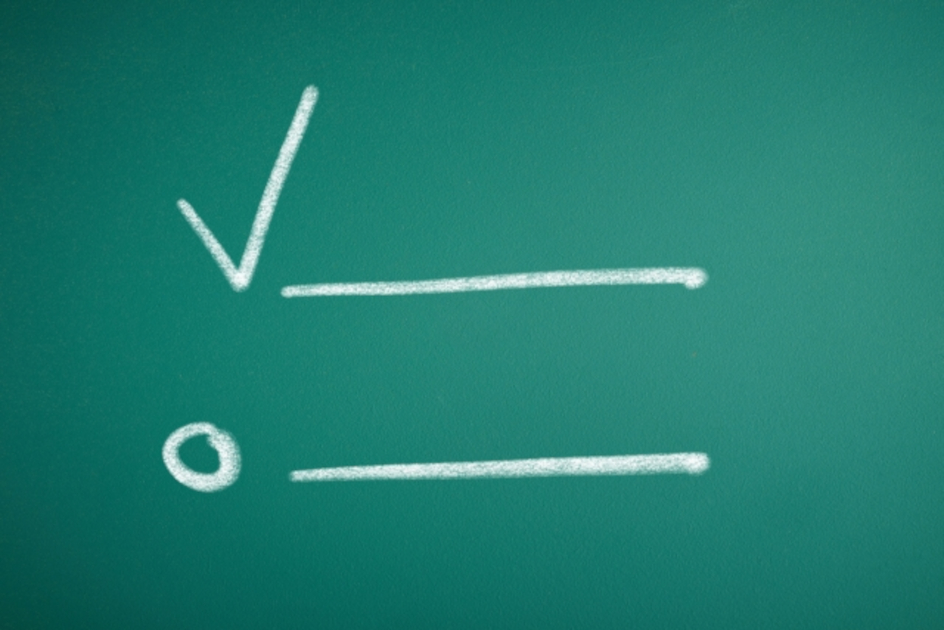


定期テストでうまくいかなかったときにすべきことは、主に次の5つです。
定期テストでうまくいかなかったときにすべきこと
すべきこと1:励ます・認める
定期テストでうまくいかなかったときに一番最初にすべきことは、励ますこと・認めることです。
子どもは、認めてもらえると自信を持って前に進むことができるからです。
定期テストの振り返りでは、できなかったところばかりを探してしまいますが、できたところや頑張ったところを探して認めてあげることも大切です。
落ち込むのは頑張った証拠
「定期テストでうまくいかなかった」と、
子どもが落ち込んでいたり、悔しがっていたりしているのであれば、それは本当は良いことです。
落ち込んだり悔しがったりするということは、それだけ努力をした証拠だからです。
そもそも頑張っていなければ、落ち込んだり悔しがったりすることもありません。
失敗するリスクを負って、成長するための努力をしたのです。
その点をしっかりと認めて、励ましてあげてください。
結果や点数に褒めるポイントが見つからない場合は、過程や努力を褒めるようにすると良いです。
すべきこと2:復習と解き直しをする
定期テストでうまくいかなかったときにまず取り組むべき勉強は、定期テストの復習と解き直しです。
できなかったところをできるようにすることが、本当の勉強だからです。
丸付けをしてからが勉強です。


勉強は積み上げていくものです。
以前学習した内容が理解できていないと、これから学習する内容を理解することが難しくなります。
そのため、一つひとつの学習内容をしっかりとマスターして苦手を残さないように進んでいくことが、成績アップの一番の近道になります。
定期テストでできなかった問題は、ここまでの勉強でしっかりと理解することができなかった問題です。
定期テストごとに復習に取り組んで苦手を残さないようにすることで、次に新しく学ぶことをスムーズに理解することができます。
定期テストの復習についての詳細は、『定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント』で解説しています。
-

-
定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント
続きを見る
すべきこと3:振り返りと分析をする
定期テストの復習と解き直しが終わったら、振り返りと分析にも取り組んでいきます。
振り返りをして勉強方法を改善していくことで、これからの勉強を効率化していくことができるからです。
解けなかった問題はなぜ解けなかったのか、どのような勉強をしていれば解けたのかを考えます。
逆に、しっかり解けた問題はなぜ解けたのか、どのような勉強をしたから解けたのかを考えます。
定期テスト後の振り返りと分析にしっかりと取り組むことで、自分に合った勉強法を作り上げていくことができます。
定期テストの振り返りについての詳細は、『定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント』で解説しています。
-

-
定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント
続きを見る
振り返りシートを活用する
定期テスト後に振り返りシートを書くように、学校から課題が出される場合もあります。
「課題だから」と適当に取り組むのではなく、しっかりと考えて記入することが大切です。
学校の先生も、次の試験に向けて学力を伸ばしてほしいと考えて振り返りシートを課題に出しています。
面倒くさがらずに、丁寧に取り組めると良いです。
定期テストの振り返りシートの活用方法についての詳細は、『【例文付き】定期テスト振り返りシートで差をつける!効果的な書き方と活用法』で解説しています。
-

-
【例文付き】定期テスト振り返りシートで差をつける!効果的な書き方と活用法
続きを見る
すべきこと4:次のテストの作戦を考える
定期テストの分析が終わったら、続いて次の定期テストに向けての作戦を考えます。
定期テスト対策の取り組み方を改善していくためです。
次の定期テスト対策ではどのような勉強に力を入れて、今回の定期テスト対策で点数に結びつかなかった勉強をどのように改善して、どれくらいの時間をかけていくか考えます。
定期テストのたびに結果を分析をして、新たな作戦を考えることで、勉強の効率を上げていくことができます。
うまくいかなかった定期テストは、改善点をたくさん見つけられるデータです。
したがって、定期テストがうまくいかなかったときこそ成績アップの大チャンスです。
次の定期テストで過去最高点を取るための材料にしてしまいましょう。
次のテストに向けての作戦を、中学生が一人で考えるのは難しいので、親子で対話しながら考えていけると良いです。
保護者の方が子どもに質問を投げかけながら、子ども主体で考えていくようにすると効果的です。
すべきこと5:学校の授業の予習復習をする
次の定期テストにむけての作戦を考えたら、まずは学校の授業の予習復習にしっかりと取り組みます。
勉強は、普段の積み重ねが一番大切だからです。
「予習→学校の授業→復習」という形で、短期間で同じ学習内容に繰り返し取り組むことで、学習内容を一層定着させることができます。
定期テスト対策は、普段の授業からはじまっています。
普段の授業で学習内容をしっかりと定着させることができれば、基礎力が定着した状態で定期テスト前の勉強に取り組むことができます。
余計な復習に時間をかける必要がなくなるので、充実した定期テスト対策に取り組むことができます。
今後の定期テストで点数を伸ばしていくための対策
中学校の定期テストでは、現状の成績に関係なく、正しく努力をすることで点数を伸ばしていくことができます。
正しい努力の仕方を知り、実践していくことが大切です。
中学生の定期テスト対策については、『中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド』に詳しくまとめてあります。
ぜひチェックして、定期テストの成績アップを目指してください。
-

-
中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド
続きを見る
まとめ
それでは、定期テストでうまくいかなかったらどうするかというお話をまとめます。
結論
定期テストで点数が落ちてしまっても大丈夫です。
むしろ成績アップのチャンスなので、ステップアップの材料としてしまいましょう!
定期テストでうまくいかなかったとしても大丈夫な理由は、主に次の3つです。
定期テストでうまくいかなかったとしても大丈夫な理由
定期テストでうまくいかなかったときにとってはいけない行動は、主に次の3つです。
定期テストでうまくいかなかったときにすべきことは、主に次の5つです。
定期テストでうまくいかなかったときにすべきこと
今回の記事が、お子様が次回の定期テストで最高得点を取るきっかけとなればとてもうれしいです。
-

-
中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド
続きを見る
-

-
定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント
続きを見る
-

-
定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント
続きを見る
-

-
【例文付き】定期テスト振り返りシートで差をつける!効果的な書き方と活用法
続きを見る