こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

子どもの定期テストの勉強で、親はどのようにサポートすれば良いものかと悩まれている保護者の方は多いです。
子どもの勉強態度や勉強方法を見ていると、ヤキモキしたり、イライラしたりして、ついつい口を出したくなってしまいますよね。
結論
中学生が自力で定期テストの勉強に取り組むのはとても難しく、保護者の方のサポートが必要になる場合は多いです。
保護者の方は勉強を教えることよりも、モチベーション管理と学習管理でサポートしてあげられると良いです。
今回は、子どもの定期テストの成績アップのためにできる、保護者の方のサポートについて解説します。
中学生を対象に解説していきますが、高校生も参考にしていただけます。
最後まで読んでいただき、お子様が定期テストの成績をアップさせたうえで、自分一人でも勉強に取り組める力を身につけるための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
1対1の個別指導!
【個別教室のトライ】![]() は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
は、毎回同じ講師が担当する専任制!一人ひとりの理解度に合わせた授業を受けられます!
- マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット
- 120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法
▼公式サイトで詳細をチェックする
【個別教室のトライ】![]()
定期テスト成績アップのために親がすべきサポート
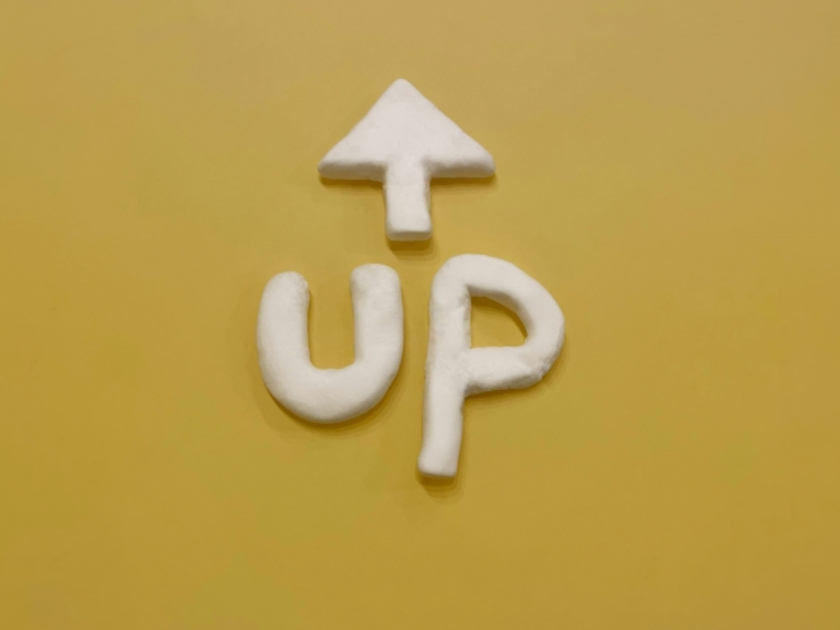
定期テストの勉強のサポートと聞くと、「勉強を教えること」と考える保護者の方が多いです。
しかし、子どもの定期テストの勉強のサポートとして親がすべきことは、「勉強を教えること」ではありません。
定期テスト成績アップのために保護者の方がすべきサポートは、主に次の2つです。
親がすべきサポート
サポート1:モチベーションアップのサポート
定期テストの成績アップのために保護者の方がすべきサポートの中で一番大切なのは、子どものモチベーションアップのサポートです。
前向きに勉強に取り組めるようになれば、自然と成績は上がるからです。
逆に、モチベーションが低い状態で勉強に取り組んでも、意味のないただの作業になってしまう可能性があります。
勉強量を増やすためにも、勉強効率を上げるためにも、まずは勉強に対するモチベーションを高める必要があります。
サポート2:学習管理のサポート
定期テストの成績アップのために保護者の方がすべきサポートで、すぐに結果につなげることができるのは、学習管理のサポートです。
中学生の子どもは、勉強そのものよりも、学習管理が苦手な場合が多いからです。
学校や塾に通っていれば、やるべきことはすべて課題や宿題という形で与えられます。
そのため、言われた課題に取り組むことはできるようになりますが、自分で何をすべきかを考えて、課題を設定することができるようになりません。
いきなり、「定期テストのための勉強を、自分で考えてやりなさい。」と言われても、
「何からやればいいかわからない!」という中学生も多いです。
最初は、保護者の方が学習管理のサポートをしてあげる必要があります。
定期テスト成績アップのためのモチベーション管理

定期テストの成績アップのために保護者の方がすべきモチベーション管理は、主に次の4つです。
モチベーションのサポート
モチベ管理1:褒める・認める
保護者の方がすべきモチベーションアップのサポートで一番優先すべきは、「褒めること」と「認めること」です。
子どもは、認めてもらうことで努力できるようになるからです。
子どもを褒めること・認めることは、勉強における保護者の方のサポートの一番重要な部分になります。



定期テストはついつい点数という「結果」に注目してしまいますが、長い目で見れば結果そのものはそれほど重要ではありません。
定期テストを通して子どもが成長することを考えるのであれば、結果よりも過程の方こそが重要です。
結果よりも過程に注目すれば、褒めるポイントや認めるポイントはたくさん見つかります。
「見ていてもらえる」ことは、子どもにとっては大切なこと
子どもたちにとって、自分が努力していることを見ていてもらえていること、認めてもらえていることは、とても重要なことです。
誰にも見てもらえないまま、誰にも認めてもらえないまま努力を続けることは、子どもでなくても難しいです。
保護者の方がが子どもの努力を「ちゃんと見ていること」「ちゃんと認めていること」は、言葉に出して伝えなければ、子どもには伝わりません。
声に出して子どものことを褒めること・認めることは、勉強に取り組む子どもたちにとってはとても大切なことです。
モチベ管理2:目標設定
保護者の方がすべきモチベーションアップのサポートとしては、目標設定を子どもと一緒に考えることも重要です。
明確な目標を設定できれば、前向きに勉強を頑張ることができるからです。
目標を設定できないと闇雲に前に進むことしかできなくなるため、子どもは「何を頑張ればいいのかわからない」という状態になってしまうことが多いです。
目標という到達点が具体的にイメージできると、頑張るべきことが見えてきます。
可能であれば、「目標を達成したらどうなるか」、「目標を達成したらどんな気持ちになるか」などの、目標達成後を具体的にイメージさせてあげられると良いです。
届きそうな目標を具体的に
目標は、頑張れば届きそうなものを設定します。
頑張っても全然届かなそうな無理な目標は、設定しても意味がありません。
逆に、簡単に達成してしまうようなハードルの低い目標も意味がありません。
目標は、数字などを使って具体的に決められると更に良いです。
目標例
- 学年順位を前回よりも20位上げる
- 5教科合計400点
- 苦手な数学で平均点を取る
目標や親子で一緒に考えられると良い
目標は、親子で一緒に考えて、一緒に設定することが大切です。
他人が設定した目標は、他人事のように感じてしまうからです。
また、目標や課題を自分で設定する力を育てることも大切です。
最終的には、親のサポートなしに、子ども自身が適切な目標を設定できるようになることを目指します。
▼あわせて読みたい
>>中学校の定期テスト平均点は?確実に超えるための勉強法と教科別対策
▼あわせて読みたい
>>中学校の定期テストで400点を目指す!学年上位に入るための勉強法と教科別対策
▼あわせて読みたい
>>定期テストで450点取る方法!一段上の勉強法と科目別攻略ポイント
モチベ管理3:応援していることを伝える
子どものことを応援しているということをしっかりと伝えることも、保護者の方がすべきモチベーションアップのサポートの一つです。
子どもにとって、自分自身を肯定できるようになることは大切なことだからです。
自分自身を肯定できれば、自分が取り組んでいることに自信が持てます。
子どもが自分自身に自信を持てるよう、子どもの目標や、子どもが取り組んでいることを応援してあげてください。
モチベ管理4:将来のことについて話し合う
子どものモチベーションアップのためには、将来のことについて親子で話し合う機会を作ることも大切です。
勉強する目的や、努力をするための理由があると、前向きに頑張ることができるからです。
何のために勉強をしているのかがわからないと、なかなか努力できないものです。
定期的に親子で対話する機会を設けて、将来どのようなことをしたいのかを考えられるようにすると良いです。
▼あわせて読みたい
>>将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント
▼あわせて読みたい
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
定期テスト成績アップのための学習管理

定期テストの成績アップのために保護者の方がすべき学習管理は、主に次の4つです。
学習管理のサポート
学習管理1:学習計画を立てる
保護者の方がすべき学習管理のサポートとして一番最初に取り組むことは、子どもと一緒に学習計画を立てることです。
中学生の子どもにとって、一人でゼロから学習計画を立てるのは難しいからです。
定期テストの時期が近づいてきたら、定期テスト3週間前からの学習計画を一緒に考えてあげてください。
学習計画表は学校で配られると思いますので、そちらに記入していきます。
もし学校で配られないようであれば、エクセルやGoogleスプレッドシートで簡単な物を作成すると良いでしょう。
なお、学習計画を作成するときは、次のように作成すると良いです。
学習計画の作成方法
作成方法1:定期テスト対策全体の達成目標を作る
学習計画を立てるときは、まずは定期テスト対策全体の達成目標を考えます。
定期テスト対策でやるべきことを洗い出して、それぞれのタスクをいつからいつまで取り組むべきか、おおまかな達成目標を書き出していきます。
たとえば、「学校のワークは定期テスト1週間前までに3周終わらせて、残りの1週間は購入してある問題集を解く」などです。
あまり細かなことは決めずに、おおまかな期間を考えると良いです。
細かく考えすぎると時間がかかってしまい、時間を無駄にしてしまいます。
作成方法2:1週間ごとに学習計画を作る
定期テスト対策全体の達成目標を決めたら、1週間ごとの学習計画を毎週考えます。
定期テスト3週間前、定期テスト2週間前、定期テスト1週間前のタイミングで、3回に分けて考えるようにします。
1週間ごとの学習計画では、何曜日に何に取り組むか、具体的に考えていきます。
比較的細かな学習計画を作るので大変そうに感じますが、定期テスト対策全体の達成目標を見ながら作ると、思ったよりも簡単に作ることができます。
学習管理2:学習進捗を管理
保護者の方がすべき学習管理のサポートとして次に取り組むべきことは、子どもの学習進捗の管理です。
学習計画を立てても、それを実行できなければ意味がないからです。
定期テスト勉強に取り組んでいると、計画通りに学習が進まないことも多いです。
勉強を計画通りに進めるためには、細かく学習進捗を確認して、計画の修正をしていく必要があります。
学習計画の修正については、中学生が一人で取り組むのは難しいです。
保護者の方がサポートして、一緒に考えて修正していく必要があります。
毎日チェックする時間を作る
定期テストの勉強中は、1日に5分~10分で良いので、子どもと一緒に学習進捗をチェックする時間を毎日作れると良いです。
計画の修正は、早ければ早いほどやりやすいからです。
学習進捗が学習計画から大きく外れてしまうと、学習計画をイチから作り直さなければならなくなります。
そうなる前に、細かく修正をしながら勉強を進めていけると良いです。
計画通りに取り組めなかった部分については、いつどのように取り組むか、子どもに考えさせます。
「こうしなさい。」と指示を出すのではなく、「どうしようか。」と問いかけて、本人に考えさせることが大切です。
学習管理3:管理から自立を目指す
最初のうちは、学習計画の作成も、学習進捗のチェックも、保護者の方が手取り足取りサポートしてあげて問題ありません。
しかし、だんだんと子どもに任せるようにしていき、最終的には子どもが自力で勉強に取り組めるようにしていく必要があります。
いつまでも手取り足取りサポートしていては、子どもが自分で課題を設定して、それを達成するための過程を考える力を育てられないからです。
最初はしっかりと管理してしまって大丈夫ですが、いずれ自立できるようにすることを意識しながらサポートしてあげることが大切です。
指示を出すのではなく、一緒に考えて、一緒に決めていくことが大切です。
学習管理4:学習環境を整える
保護者の方がすべき学習管理のサポートには、学習環境を整えるというものもあります。
子どもが集中して勉強に取り組める環境を作るのは、思った以上に難しいものです。
ずっと自室にこもって勉強していると、人目がないのを良いことについついマンガを読んでしまったり、スマホをいじってしまったりしてしまうかもしれません。
人目のあるところはうるさくて勉強に集中できないかもしれません。
どのような環境であれば勉強に集中できるか、子どもと相談しながら環境を整えられると良いです。
家で勉強に取り組むのが難しいようであれば、学習塾の自習室の利用を検討してみるのも良いでしょう。
▼あわせて読みたい
>>【元塾教室長の本音】自習室目当てで塾に通うのはアリか
定期テスト成績アップのために親がすべきでないこと

ここからは、定期テストの成績アップのために保護者の方がすべきでないことを8つ解説していきます。
すべきでないこと
NG1:子どもに任せっきりにする
定期テストの成績をアップさせるためには、子どもに任せっきりにしてはいけません。
中学生の子どもが、課題設定から目標達成までを一人でコントロールするは非常に難しいからです。
とりあえず塾に任せっきりにしてしまう保護者の方も多いですが、たとえ塾に通っていたとしても、保護者の方のサポートは必要です。
学習塾などの学習サービスを利用すれば保護者の負担は減りますが、丸投げして良いわけではありません。
▼あわせて読みたい
>>塾に通っているのに成績が上がらない理由3パターンと解決策【元塾教室長が解説!】
NG2:「勉強しなさい」と言う
勉強しない子どもを見ていると、ついつい「勉強しなさい!」と言ってしまいますが、
「勉強しなさい!」と言われてやる気が出る子どもはいません。
むしろ、やる気が下がってしまうことのほうが多いです。
子どもには、「勉強しなさい!」と命令するよりも、「頑張ろう!」と応援してあげたほうが良いです。
保護者の方は指示役ではなく、同じ目標に向かって一緒に頑張るパートナーという役割りを目指せると良いです。
NG3:感情的に叱る・否定する
定期テストの勉強に限らず、感情的に叱ったり、子どもを否定したりしてはいけません。
「おまえは何をやってもダメだ。」や、「こんなこともできないのか。」などの言葉で子どもを否定すると、子どもは自分を肯定できなくなってしまいます。
自分を肯定できなければ、何かに前向きに取り組むことは難しいです。
感情的に叱るのもNGです。
恐怖のようなネガティブなモチベーションで勉強に取り組んでも長続きしませんし、いつまで経っても自立できなくなってしまいます。
大人になってからも、「怒られないように」と受け身で行動しているようでは「大人」とは言えません。
NG4:人と比べる
兄弟や友人など、他の子どもと比べるようなことを言うのもNGです。
「お兄ちゃんはこうだったのに」や、「〇〇さんは立派な大学に行ったのに」といった発言は、こちらが想像している以上に子どもを傷つけます。
向き合うべきは、目の前にいる子どもです。
人にはそれぞれ、良いところも悪いところもあるものです。
NG5:勉強を教える
子どもがわからないところがあると、ついつい自分で教えたくなってしまうことがあるものですが、可能な限り保護者の方は勉強を直接教えないほうが良いです。
「教わること」だけが勉強ではないからです。
指導経験が豊富な先生ほど、生徒の質問に対していきなり丁寧な解説をしたりしません。
わかりやすく解説するよりも、子どもに考えさせたほうが良い場合が多いからです。
どうしてあげることが目の前の子どもの学力を一番伸ばしてあげられるかという判断は、非常に難しいものです。
保護者の方が、ちょっとした質問に答えたり、問題の出し合いっ子をしたりする程度であればまったく問題ありませんが、つきっきりで勉強を教えるのは避けるべきです。
保護者の方は、基本的にはモチベーションアップのサポートや学習管理のサポートに徹し、勉強の中身については学校の先生などのプロに頼るべきです。
NG6:完璧を求める
子どもの定期テストの勉強に、完璧を求めてはいけません。
中学生は、大人が思っている以上に子どもだからです。
経験は浅いですし、うまくできないこともたくさんあります。
失敗することも、とても大事な経験です。
失敗を許容し、その後どうすればよいか、子どもと一緒に対話することが大切です。
NG7:罰を与える
子どもの定期テストの勉強において、罰を与えるようなルールを作るのはNGです。
「罰」はネガティブなモチベーションだからです。
親子の信頼関係にも影響します。
「〇〇点以下だったらスマホ没収」や、「〇〇をサボったらピアノを辞めさせる」などの罰は、一瞬その場では効果があるように見えますが、長い目で見れば大きな大きなマイナスになります。
NG8:報酬を与える
罰を与えることはもちろNGですが、報酬を与えることにも慎重になる必要があります。
特に、高価なものをご褒美に設定するのは危険です。
「もの」のご褒美はエスカレートしやすく、より高価なものを買い与えなければ、頑張れなくなってしまうからです。
ご褒美を設定するのであれば、「今日の夕飯は大好きなハンバーグにする」や、「気分転換に〇〇(子どもが好きなこと)をしに行く」などの、気軽な「こと」や「経験」にしたほうが良いです。
定期テスト成績アップのための試験が終わったあとのサポート

定期テストの成績アップのための保護者の方のサポートとしては、試験が終わったあとのサポートも大切です。
定期テスト後の保護者の方のサポートとしては、次の4点が重要です。
試験後1:努力を褒める・認める
定期テストが終わったら、まず真っ先に、子どもが努力したことを認めて褒めてあげてください。
テストの結果ではなく、努力したことを褒めてあげられると良いです。
子どもにとっては、自分が努力していることを誰かに見てもらえているかどうかはとても大切なことです。
子どもの努力をしっかりと見て、認めてあげてください。
試験後2:復習と解き直しに取り組ませる
テストが返却されたら、すぐに復習と解き直しに取り組ませます。
定期テストの復習に取り組むメリットは、主に次の5つです。
定期テストの復習に取り組むメリット
- 苦手を早期発見して克服できる
- 正しい勉強方法が身につく
- 次の定期テストの点数アップを狙える
- 受験対策につながる
- 入試直前期に点数を爆上げするための準備になる
定期テストの復習についての詳細は、『定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント』で詳しく解説しています。
-

-
定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント
続きを見る
試験後3:テストの振り返りをさせる
定期テストは復習と解き直しだけでなく、振り返りにも取り組めると良いです。
定期テストの振り返りが、次のテストの点数アップに大きく役立つからです。
定期テストの振り返りをすべき理由
- 苦手を残さないようにするため
- 正しい勉強方法を身につけるため
- 受験勉強を有利に進めるため
- 物事を改善できる力を育てるため
定期テストの振り返りに取り組むことで、テスト対策の取り組み方を毎回改善していくことができます。
定期テストの振り返りについての詳細は、『定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント』で解説しています。
-

-
定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント
続きを見る
▼あわせて読みたい
>>【例文付き】定期テスト振り返りシートで差をつける!効果的な書き方と活用法
試験後4:学校の予習復習に取り組ませる
定期テストが終わったら、学校の予習復習に取り組む習慣を身につけさせることが大切です。
勉強は、結局は普段の積み重ねが一番大切だからです。
「予習→学校の授業→復習」のように、短期間で同じ学習内容を3回繰り返すと、学習内容が定着しやすくなります。
普段の授業で毎回学習内容をしっかりと定着させることができれば、基礎力が定着した状態で定期テスト直前の勉強に取り組むことができます。
余計な復習に時間をかける必要がなくなるので、充実した定期テスト対策に取り組むことができます。
普段の学校の授業の予習・復習から、次の定期テストに向けての対策がはじまっています。
第三者のサポートに頼る


保護者が子どもを「褒める・認める」を意識していれば、反抗期であっても親のサポートを快く受け入れる中学生は多いです。
一方で、中学生は感情的にも不安定であり、本人にも理由が分からずに親に反発してしまう場合もあります。
そのような場合は、第三者のサポートを頼れると良いです。
幸いにも、日本には学校の勉強や受験勉強をサポートしてくれるサービスがたくさんあります。
大人には反発しても、大学生の家庭教師や塾講師には素直になれる中学生も多いです。
塾などの学習サービスにすべて丸投げにしてしまうのはいけませんが、ご家庭だけで抱え込まないことも大切です。
▼あわせて読みたい
>>【中学生】いつから塾に通う?高校受験対策の入塾のタイミングは費用と効果のバランスが大事!
▼あわせて読みたい
>>高校受験の塾にかかる年間費用はいくら?相場とコスパ良く利用する方法を解説!
心のサポートは親が適任

モチベーションのサポートや学習管理については、学習塾などで手厚くサポートしてもらうこともできます。
一方で、心のサポートについては保護者の方が一番の適任です。
子どもの一番近くで一番多くの時間を共有してきたのは、他の誰でもない保護者の方だからです。
第三者には気づけないことでも、保護者の方であれば気がつくことができます。
保護者の方が、子どもの細かな心の変化を見逃さず、サポートしてあげられると良いです。
定期テスト対策のポイント



中学校の定期テスト対策では、正しい努力の仕方を知り、実践していくことが大切です。
現状の学習理解度から取り組むべきことを決め、一つひとつ丁寧にやり切ることで成績を伸ばすことができます。
中学生の定期テスト対策については、『中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド』に詳しくまとめてあります。
ぜひチェックして、定期テストの成績アップを目指してください。
-

-
中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド
続きを見る
まとめ
それでは、子どもの定期テストの成績アップのためにできる親のサポートについての解説をまとめます。
結論
中学生が自力で定期テストの勉強に取り組むのはとても難しく、保護者の方のサポートが必要になる場合は多いです。
保護者の方は勉強を教えることよりも、モチベーション管理と学習管理でサポートしてあげられると良いです。
定期テスト成績アップのために保護者の方がすべきサポートは、主に次の2つです。
親がすべきサポート
定期テストの成績アップのために保護者の方がすべきモチベーション管理は、主に次の4つです。
モチベーションのサポート
定期テストの成績アップのために保護者の方がすべき学習管理は、主に次の4つです。
学習管理のサポート
定期テストの成績アップのために保護者の方がすべきでないことを8つ解説しました。
すべきでないこと
定期テスト後の保護者の方のサポートとしては、次の4点が考えられます。
今回の記事が、お子様が定期テストの成績をアップさせたうえで、人間的にも大きく成長するきっかけとなればとてもうれしいです。
-

-
中学生の定期テスト対策完全まとめ!点数アップのための全ガイド
続きを見る
-

-
定期テストの復習で学力を伸ばす!効果的な取り組み方とポイント
続きを見る
-

-
定期テストの振り返り完全ガイド!苦手克服と効率学習のポイント
続きを見る









