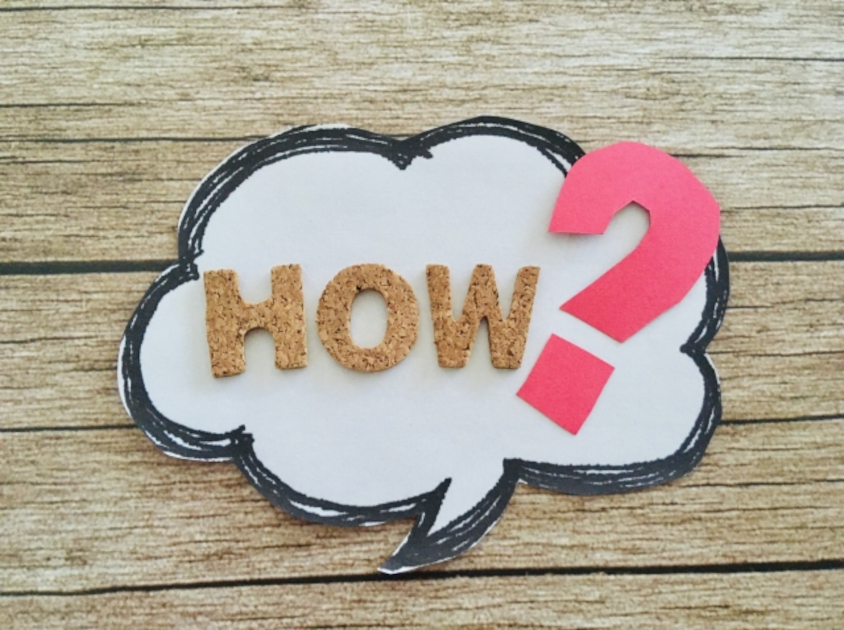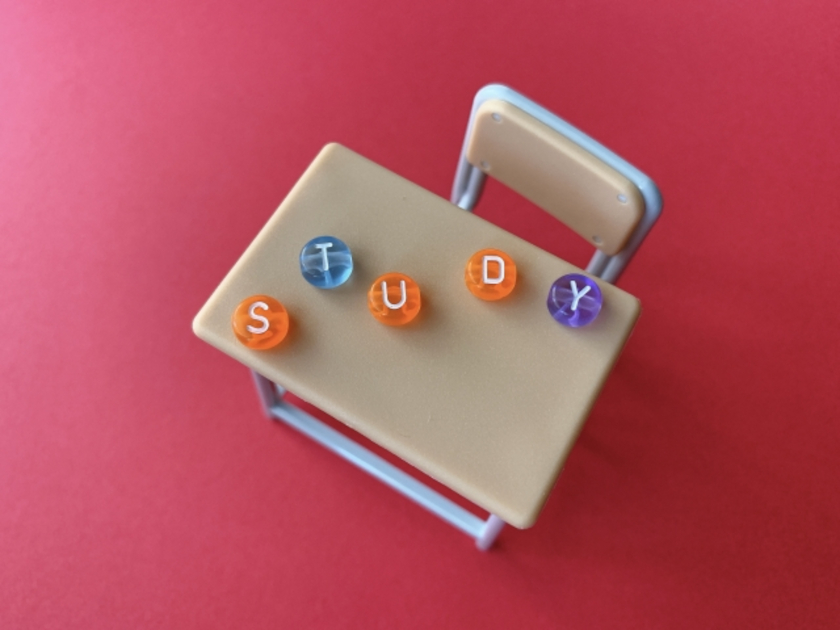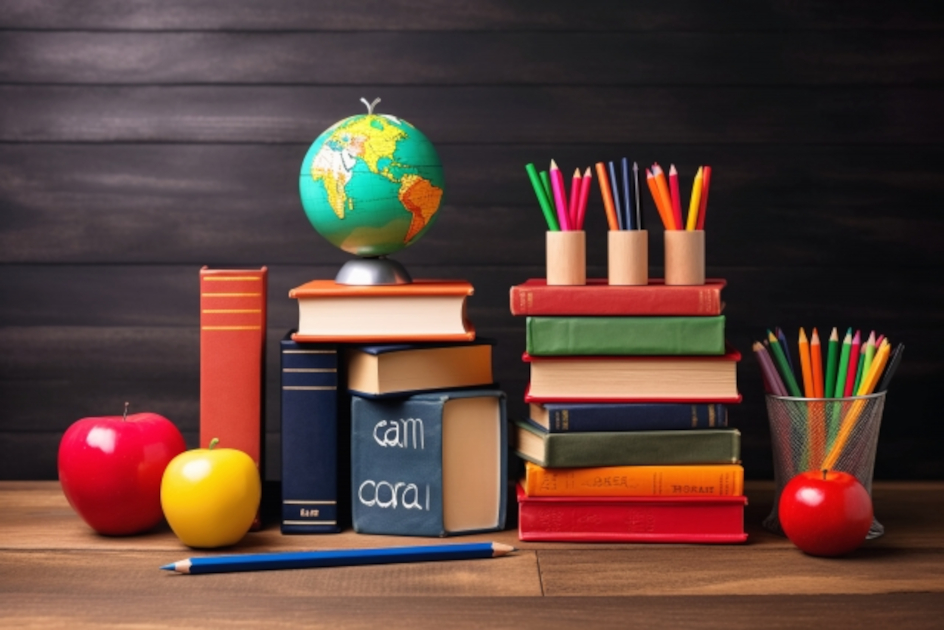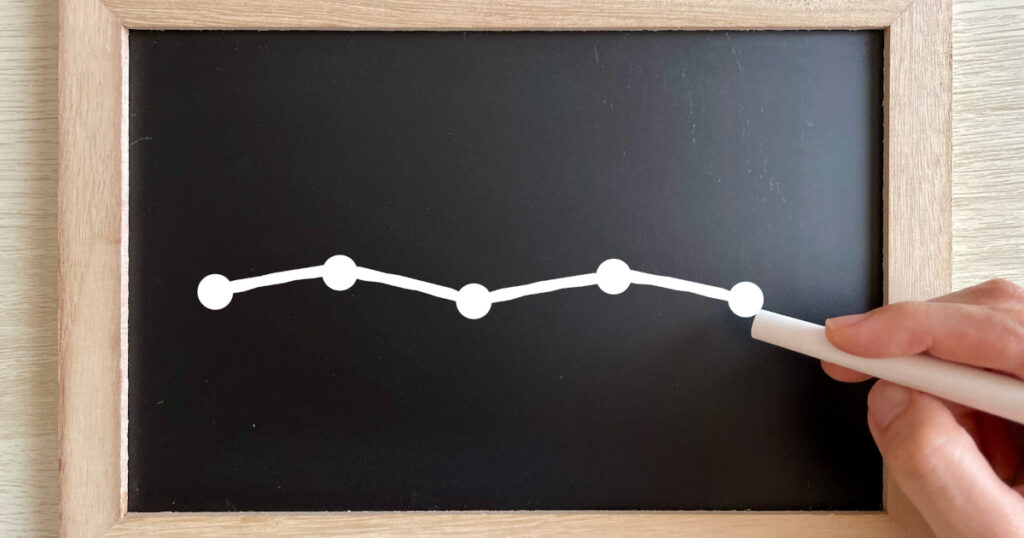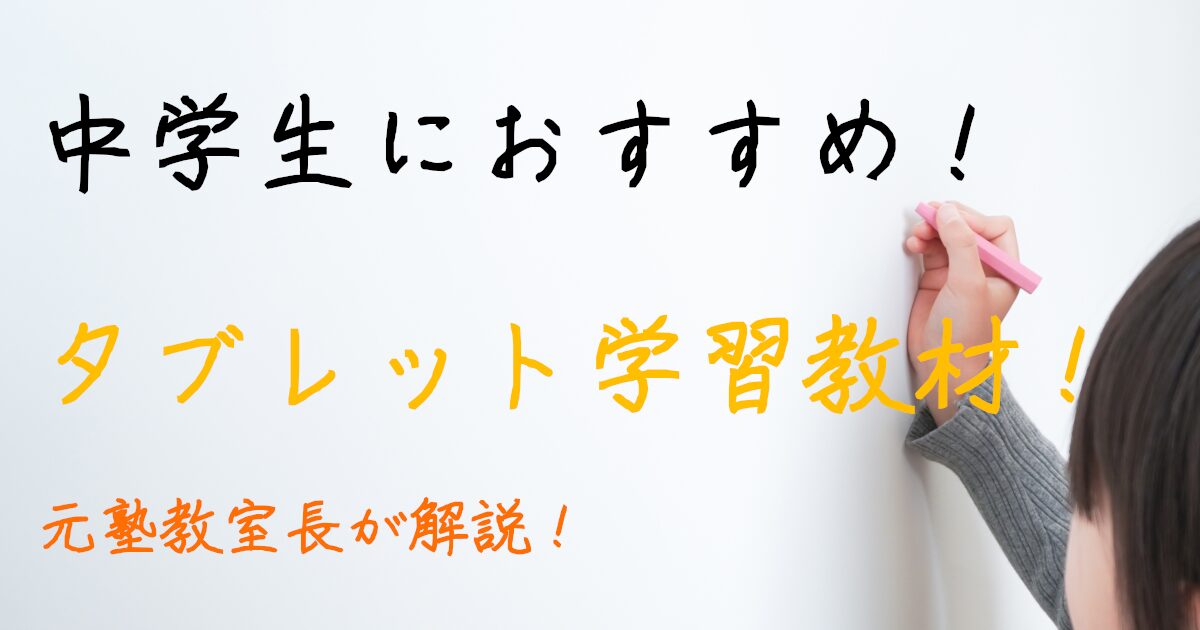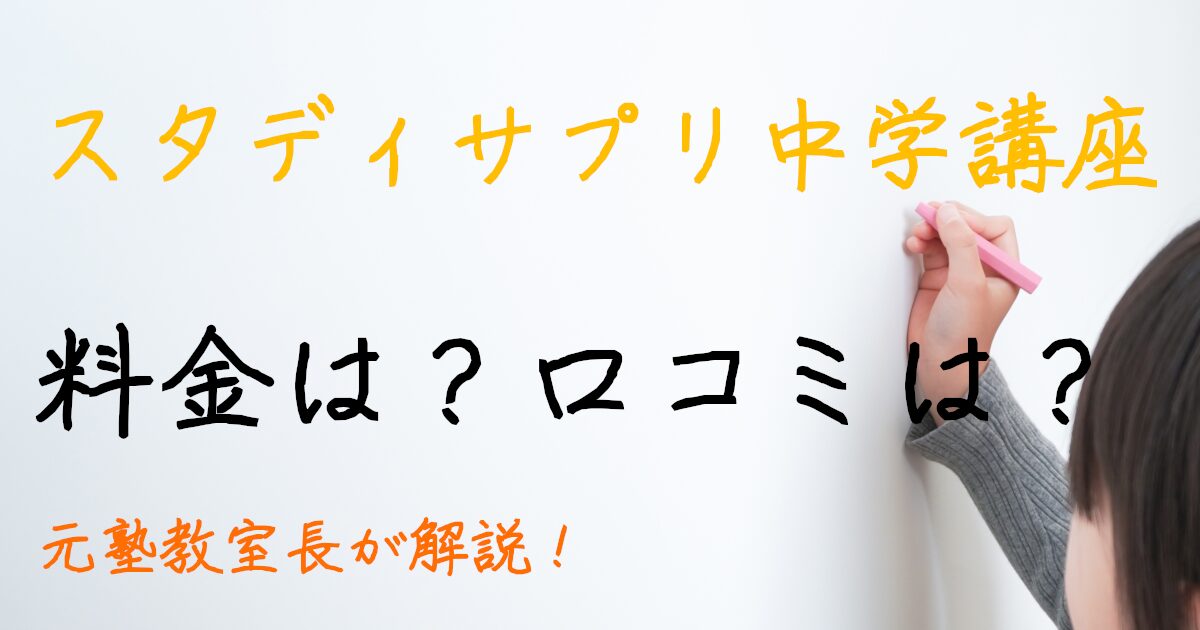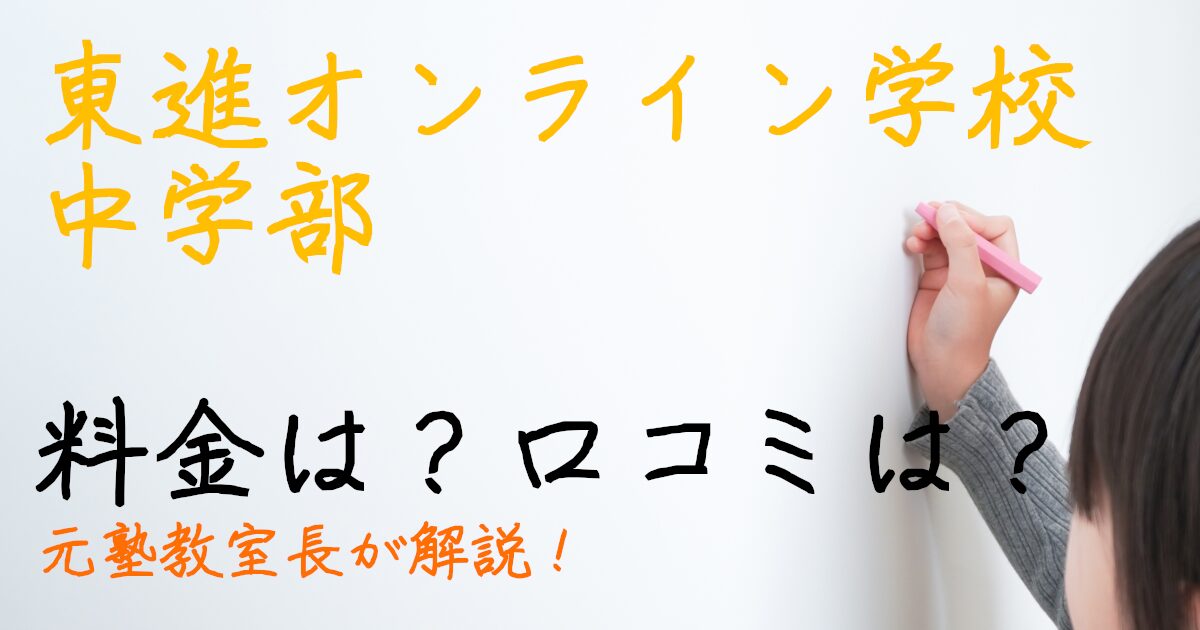こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

塾に通っているのに全然成績が上がらない中学生も多いです。
なかなか成績が上がらないと、別の塾に変えたほう良いのではないかと悩んでしまいますよね。
結論
塾に通っているのに成績が上がらないからといって、安易に塾を変えても問題は解決しません。
成績が上がらない理由を見極めて、適切な解決策を考える必要があります。
今回は、中学生が塾に通っているのに成績が上がらない3パターンの理由と解決策について解説します。
最後まで読んでいただき、お子様が塾を活用して学校の成績をグイグイ上げるための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
対面型の個別指導のような授業をオンラインで!
「オンライン家庭教師WAM![]() 」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!
」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!
安心の返金保証・成績保証!
▼詳しくはこちらから!
>>オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・特徴は?
塾に通っても成績が上がらない理由3パターン
塾に通わせたら、それで子どもの成績が上がるわけではありません。
塾はあくまでも子どもの勉強をサポートするだけで、実際に勉強を頑張るのは子ども自身だからです。
私が塾の教室長をしていたときに感じていた「塾に通っても成績が上がらない理由」には、主に3つのパターンがありました。
成績が上がらない理由
一つひとつ解説します。
理由1:勉強時間が足りない
勉強の成績に直結するのは、結局は勉強時間です。
どんなにわかりすい授業を受けても、勉強時間が足りなければ成績は上がりません。
授業を聞いて学習内容が「わかる」ようにするだけではなく、自分で問題を解いて「できる」ようにしなければ、テストでは正解できないからです。
授業を聞くことが勉強だと思っている中学生は多いのですが、自分で勉強する時間をしっかりと確保しなければ成績は絶対に上がりません。
最後は家庭学習

塾の講師は、生徒が宿題をしっかりとやってきているかどうかや、暗記テストでしっかりと点数が取れているかどうかに目を光らせています。
それでも、宿題をやってこない生徒や、暗記テストのための勉強をサボる生徒はいます。
生徒が真面目に取り組めているか、塾の講師が家庭学習の時間までつきっきりでチェックすることはできないからです。
実際に子どもたちが宿題や自習に取り組むのは、ご家庭の中でになります。
塾に任せっきりにするのではなく、保護者の方も積極的に子どもの勉強に関わらなければなりません。
理由2:勉強方法が間違っている
どんなに勉強時間が長くても、勉強方法が間違っていれば成績は上がりません。
学習内容を学ぶことも大切ですが、正しい勉強方法も学ぶことも大切です。



小学生までは勉強量だけである程度の成績は取れてしまうのですが、中学生以降は勉強量だけでは良い成績が取れなくなっていきます。
中学生以降の成績は、正しい勉強方法を身につけられるかどうかが大きな分かれ道となります。
>>【元塾教室長が解説!】中学数学を復習するための効率的な勉強方法
理由3:塾が子どもに合っていない
他のみんなにとっての良い塾が、必ずしも自分の子どもにとっても良い塾とは限りません。
子どもにはそれぞれ得意・不得意があり、合う・合わないがあるからです。
塾が子どもに合っていなかった場合、子どもが悪いわけでも塾が悪いわけでもありません。
ただ単純に相性が悪いだけです。
子どもの性格に合った塾を選ぶべき
塾を選ぶときは、評判や口コミ等を参考にしながら選ぶと思います。
評判の良い塾や、有名な塾を選ぶご家庭が多いのですが、最終的には自分の子どもに合うかどうかで選ぶべきです。
幸いなことに、今の日本には多くの種類の学習サービスが存在します。
しっかりとリサーチをすれば、子どもにピッタリの塾やサービスを見つけられるはずです。
先入観や周りの評判にとらわれずに、子どもにピッタリの塾を選ぶべきです。
塾に通っても成績が上がらないときの解決策
塾に通っても成績が上がらないときに最初に考えることは、塾を変えることではありません。
成績が上がらない理由が、「塾」や「環境」であるケースは少ないからです。
塾ができるのは、あくまでも子どもの勉強をサポートすることです。
塾は子どもの成績を上げるために力を尽くしてくれますが、塾だけではどうにもできないことも多いです。
「塾・生徒・保護者」の三者がお互いに協力し合うことで、子どもの成績を大きく伸ばすことができます。
まずは、ご家庭でできる解決策を試してみるべきです。
塾に通っても成績が上がらないときにご家庭でできる解決策は、主に次の6つです。
成績が上がらないときの解決策
一つひとつ解説します。
解決策1:自己流の勉強方法は捨てる
正しい勉強方法を身につけるために、まずは自己流の勉強方法を捨てる必要があります。
子どもに限らず、自分のやり方を変えるのは難しいものです。
しかし、子ども自身が「このやり方がやりやすい」と思っている勉強方法は、間違った勉強方法であることのほうが多いです。
子どもの言う「やりやすい」は、「負担が少ない」や「ラクができる」という意味であることが多いからです。
決して「結果につながる」という意味で「やりやすい」と言っているわけではありません。
まず取り入れることが大事
塾では、事あるごとに正しい勉強方法のアドバイスをしています。
まずはアドバイスを取り入れて、実際にやってみることが大切です。
一方で、塾講師は子どもがご家庭で勉強している様子を見ることができません。
塾にいるときにどんなにアドバイスや注意をしても、家までついていって注意をし続けることはできません。
保護者の方も子どもの勉強方法をときどきチェックして、アドバイスや注意をしてください。
ただし、事細かく注意をすると子どもは反発してしまいます。
「ときどき」くらいの頻度がちょうど良いです。
正しい勉強方法は人それぞれ
正しい勉強方法で勉強することが大事である一方で、子どもによって正しい勉強法が異なるのも事実です。
子どもにはそれぞれ得意・不得意があり、合う・合わないがあるからです。
学校の先生や塾の先生のアドバイスを試してみて、良いものは採用して、良くないものは不採用にして、子ども自身にとっての正しい勉強方法を研究していかなければなりません。
試してみた勉強方法が正しいかどうかは、定期テスト等の試験を活用して判断すると良いです。
結果が「点数」という数値で評価されるので、正しいかどうかの判断がつきやすいです。
>>【成績アップのチャンス!】定期テストでうまくいかなかったらどうする?
解決策2:塾の宿題をやる
当たり前のことかもしれませんが、塾の宿題にはキッチリと取り組まなければいけません。
塾の授業は、宿題に取り組むことを前提として設計されているからです。
宿題に取り組まなければ、授業を受けなかったのと同じです。
塾の宿題に真面目に取り組まない子どももいます。
塾の宿題に取り組まない子どもは、学校の宿題にも取り組んでいない可能性が高いです。
学校の宿題にも取り組んでいないということは、学校の授業も真面目に受けていない可能性が高いです。
学校の授業を真面目に受けていないということは、勉強そのものを全然していない可能性が高いです。
塾に通っていれば、宿題が出ないことはありません。
子どもが学校や塾の宿題に取り組んでいるかどうかは、保護者の方が必ずチェックしてください。
宿題を「作業」にしていないか。
宿題を真面目にやっているように見えても、実は真面目にやっていないパターンもあります。
宿題をただの「作業」としてこなしているだけで、内容はまったく頭に入っていないというパターンです。
解答を写しているだけだったり、テレビを見ながら適当に漢字の書き取りをやっているだけだったりすることがあります。
小テスト系に特に注意
宿題を「作業」としてこなしているだけかどうかは、英単語や漢字の小テストの結果を見るとわかりやすいです。
宿題に取り組んだ結果がすぐに「点数」という結果で評価されるので、宿題に対する真面目さを測ることができます。
塾によっては、小テストの結果を月例レポートなどで報告してくれることもあるので、点数に注目してみてください。
小テストの点数が悪いようであれば、宿題をサボっているか、宿題をただの「作業」としてこなしている可能性が高いです。
その場合は、正しい勉強方法を指導していく必要があります。
解決策3:学習習慣をつける
勉強時間をしっかりと確保するためには、学習習慣をつけることが大切です。
勉強は、普段からコツコツと積み上げていくことが一番大切だからです。
試験直前期だけ焦って勉強しても、勉強時間を確保することは難しいです。
1日はみんな平等に24時間しかないからです。
普段からコツコツと勉強に取り組めているかどうかが、全体の勉強時間を確保できるかどうかの分かれ道となります。
塾の宿題だけでも十分に習慣化できる
塾の宿題は、学習習慣をつけるのに利用することができます。
学校の宿題+塾の宿題で、普段の勉強時間としては十分に確保できるからです。
いろいろな教材や問題集を用意するよりも、学校の宿題と塾の宿題に真面目にキッチリと取り組むことが大切です。
習慣化にはルール作りが良い
勉強を習慣化するためには、ルールを決めてしまうのが一番です。
「何時から何時までは勉強に取り組む時間」というように、お風呂や歯磨きのようにルーティーン化してしまうのが簡単です。
毎日の生活リズムに取り入れてしまえば、逆に勉強に取り組まないと気持ちが落ち着かなくなります。
最初から長時間の勉強を生活リズムに組み込むのは難しいかもしれないので、まずは1日30分程度からはじめられると良いでしょう。
それから少しずつ時間を長くしていけると良いです。
>>定期テストで点数を取れない3つの理由と8つの対処法【元塾教室長が解説!】
解決策4:授業の予習復習をする
学習内容を効率的に頭に定着させるために、塾の授業の予習復習に取り組めると非常に良いです。
勉強は、同じ内容に繰り返し取り組むことで頭に定着するからです。
「予習→塾の授業→復習」で、同じ学習内容を3回繰り返すことができます。
塾の授業は学校の授業より進んでいるので、のちほど学校の授業でも同じ学習内容を繰り返すことができます。
更に、定期テスト前にもう一度同じ学習内容を勉強し直すこともできます。
これだけ繰り返せば頭の中に残りやすいですし、定期テストでも高得点を狙うことができます。
学校の授業の予習復習にも取り組めると良い
学校の授業の予習復習にも取り組めると、更に繰り返し取り組むことができます。



勉強は、繰り返せば繰り返すほど頭に残りやすいです。
何度も繰り返し勉強できる仕組みを作ることが大切です。
解決策5:何のために勉強するのかを考える


子どもが勉強しない理由は、勉強することに意味を感じられていないからです。
意味や意義を感じないことに労力をかけ続けるのは、誰にとっても難しいことです。
時間がかかりますが、「何のために勉強するのか」を、子どもと一緒に考えることが大切です。
大人の価値観を一方的に押し付けるのではなく、子どもと一緒に対話をしながら考えていくことが大切です。
子ども自身が自分の頭で考えて答えを出さなければ、納得して勉強に取り組むことはできないからです。
将来のことを話し合う
「何のために勉強するのか」を考えるためには、子どもの将来のことを一緒に考える必要があります。
勉強は、子どもの夢を実現させるための手段だからです。
やりたいことをやるためには、勉強する必要があります。
なりたい自分になるためには、勉強する必要があります。
子どもが、「将来こんなことをしたい」「将来こんなふうになりたい」という思いを具体的にすればするほど、自分から進んで勉強するようになります。
勉強することを目的にするのではなく、将来の目的を達成するための手段として勉強に取り組めるようになると成績は大きく上がります。
自主性は成績アップの鍵
自主的に勉強に取り組めるようになると、成績は大きく上がります。
自主的に勉強できるようになると、単純に勉強時間が長くなるだけでなく、勉強の質も上がるからです。
子どもたちが「作業」のような意味のない勉強に取り組んでしまうのは、課題や宿題を終わらせることを目的にしてしまうからです。
しかし、将来の目的を達成するために勉強できる子どもは、課題や宿題よりももっと先のことを考えて勉強することができます。
どのようにすれば学力を伸ばせるのかを本気で考えるので、効率の良い勉強方法を考えながら取り組むことができます。
将来の目標や目的を考えることは、勉強そのものよりもずっと大切です。
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
解決策6:4ヶ月は様子は見る
ここまで解説してきた解決策に取り組みながら、最低でも4ヶ月は成績の推移を観察してください。
いろいろと対策をしても、結果に反映されるまでは時間がかかるからです。
定期テスト2回程度は様子を見てから、塾を辞めたり変えたりする判断をしたほうが良いです。
すぐに結果が出ないからといって、判断を焦ってしまうと失敗します。
それでも成績が上がらないときは
ここまで解説してきた解決策に取り組んでみても成績が上がらないときは、今の塾の勉強が子どもに合っていない可能性が高いです。
この段階でやるべきことは、主に次の3パターンです。
成績が上がらないとき
一つひとつ解説します。
パターン1:通っている塾に相談する
塾を辞めたり塾を変えたりする前に、今通っている塾に一度相談してみることをおすすめします。
子どもの勉強に関しては、「塾・生徒・保護者」の三者がお互いに協力し合うことが大切だからです。
子どものことをよく見てくれている塾であれば、子どもの現状の課題を把握しているはずです。
その課題を「塾・生徒」の二者だけでは解決できなくても、「塾・生徒・保護者」の三者であれば解決できる可能性もあります。
塾の面談の時期でなくても、保護者が希望すればいつでも面談を組んでくれます(組んでくれない場合は、その塾をダメな塾なので辞めてしまって問題ありません)。
まずは、今通っている塾とよく話し合ってみることをおすすめします。
パターン2:塾を変えることを検討する
通っている塾に相談しても状況が変わらないようであれば、塾を変えることを検討してください。
塾が子どもに合っているかどうかは、とても重要です。
集団授業から個別指導に変えただけで、成績が突然上がる子どももいます。
転塾先に子どもとの相性がピッタリの講師がいて、成績が上がりはじめる子どももいます。
いずれにしても、子どもの得意・不得意をよく考えて、成績をしっかりと上げてくれそうな塾を探すと良いです。
>>個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】
オンライン個別指導も検討すべき
塾を変えることを検討するのであれば、オンライン個別指導・オンライン家庭教師も検討してみてください。
オンライン個別指導・オンライン家庭教師は、住んでいる地域に関わらず、日本全国に住む講師から子どもにピッタリの講師を探すことができるからです。
特に、地元に子どもにピッタリの塾が見つからないときは、オンラインを検討すべきです。
一方で、オンライの授業にはオンラインの授業のデメリットもあります。
たとえば、オンライの塾では自習室を利用することができません。
「塾に何を求めるか」をよく考えて検討する必要があります。
>>オンライン家庭教師おすすめ10選!元塾教室長が徹底比較!
>>オンライン個別指導・家庭教師の4つのメリットとデメリット
パターン3:塾以外の選択肢も検討する
「勉強すること」を考えると、ついつい「塾」に絞って考えてしまいますが、塾以外の選択肢も検討してください。
そもそも、「塾に通うこと」が合わない子どももいるからです。
塾に通わないのであれば、次の2つの学習サービスがおすすめです。
おすすめ1:タブレット教材
参考書や問題集を使って自分で勉強することが得意な子どももいます。
そのような場合は、参考書や問題集ではなく、タブレット教材を利用することを強くおすすめします。
最近のタブレット教材は、とても効率的に勉強に取り組めるように作られているからです。
AIを利用しているタブレット教材が多く、昔の通信教育教材よりも遥かに効率的に勉強に取り組むことができます。
一方で、タブレット教材を子どもに与えるだけでは、子どもは上手に取り組むことができません。
子どもと一緒に学習目標を立てたり、学習進捗をチェックしたりと、保護者の方がサポートしてあげる必要があります。
タブレット教材・通信教育教材の特徴
- 学習内容や時間の自由度が高い
- AIの活用で効率化されている
- 費用が安い
- 保護者のサポートが必要
▼あわせて読みたい
>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
-

-
タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
タブレット教材は効率よく勉強できるのでおすすめですが、デメリットも多いので適切なケアが必要です。この記事では、タブレット教材の8つのメリット・デメリットについて解説しています。
続きを見る
定期テスト目標点別おすすめのタブレット教材
- 平均点を目指すなら
塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】
※苦手克服に特化!担当コーチがつく! - 400点以上を目指すなら
【進研ゼミ中学講座】
※学校の予習復習・定期テスト対策に特化! - 450点以上を目指すなら
Z会の通信教育 中学生コース
※学年最上位を目指せる!
中学生向けのタブレット学習教材については、『中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!』で解説しています。
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!
この記事では、中学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。
続きを見る
おすすめ2:映像授業
参考書や問題集を使って自分で勉強する場合は、映像授業も利用すると良いです。
映像授業であれば、人気講師によるわかりやすい授業を、いつでも自分が必要なときに受講できるので便利です。
子どもが自分で必要だと思う授業を受けて、必要ない部分は参考書だけで進めていくこともできます。
映像授業は、一流講師の授業を格安で受けることができるのが大きなメリットです。
あまり注目されませんが、1.5倍速等の倍速視聴できるのもメリットです。
一方で、映像授業は「授業だけ」のサービスであることが多いので、問題演習については別途対策する必要があります。
映像授業の特徴
- 料金が格安
- 人気講師の授業を受けられる
- 先取りをどんどん進められる
- わからないとこは戻って復習できる
中学生におすすめの映像授業
- スタサプ
 (中学講座)
(中学講座)
※演習問題も充実!担当コーチをつけられる! - 東進オンライン学校 中学部

※「先取り+定期テスト対策」ができる!
各映像授業サービスについては、『スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?』『東進オンライン学校中学部は映像授業で「先取り+定期テスト対策」ができる!料金・口コミは?』で詳しく解説しています。
-

-
【2024年版】スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?
スタサプ中学講座は、子どもに任せっきりではなかなか続けられません。一方で、上手に活用できれば、映像授業と演習問題で学習内容をしっかりと定着させていくことができます。この記事では、スタサプ中学講座について詳しく説明しています。
続きを見る
-

-
【2024年版】東進オンライン学校中学部は映像授業で「先取り+定期テスト対策」ができる!料金・口コミは?
東進オンライン学校中学部は、授業中心で「先取り学習+定期テスト対策」に取り組める映像授業・通信教育教材です。この記事では、東進オンライン学校中学部について詳しく解説しています。
続きを見る
まとめ
それでは、塾に通っているのに成績が上がらない3パターンの理由と解決策についての解説をまとめます。
結論
塾に通っているのに成績が上がらないからといって、安易に塾を変えても問題は解決しません。
成績が上がらない理由を見極めて、適切な解決策を考える必要があります。
塾に通っても成績が上がらない理由には、主に3つのパターンがあります。
成績が上がらない理由
- 勉強時間が足りない
- 勉強方法が間違っている
- 塾が子どもに合っていない
塾に通っても成績が上がらないときにご家庭でできる解決策は、主に次の6つです。
成績が上がらないときの解決策
- 自己流の勉強方法は捨てる
- 塾の宿題をやる
- 学習習慣をつける
- 授業の予習復習をする
- 何のために勉強するのかを考える
- 4ヶ月は様子は見る
6つの解決策に取り組んでみても成績が上がらないときにやるべきことは、主に次の3パターンです。
成績が上がらないとき
- 通っている塾に相談する
- 塾を変えることを検討する
- 塾以外の選択肢も検討する
いろいろな選択肢を検討して、子どもにピッタリの学習サービスを選ぶことが大切です。
今回の記事が、お子様が塾を上手に活用して、学校の成績をグイグイ上げるきっかけとなればとてもうれしいです。
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!
この記事では、中学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。
続きを見る
-

-
オンライン家庭教師おすすめ10選!元塾教室長が徹底比較!
オンライン家庭教師はわかりやすい授業だけでなく、特徴的なサービスを提供している場合が多いです。料金だけで比較するのではなく、利用目的に合わせて子どもに合ったサービスを選べると、学力を伸ばすことができます。
続きを見る
-

-
【2024年版】スタディサプリ中学講座は『授業+演習』で理解度アップ!料金・口コミは?
スタサプ中学講座は、子どもに任せっきりではなかなか続けられません。一方で、上手に活用できれば、映像授業と演習問題で学習内容をしっかりと定着させていくことができます。この記事では、スタサプ中学講座について詳しく説明しています。
続きを見る
-

-
【2024年版】東進オンライン学校中学部は映像授業で「先取り+定期テスト対策」ができる!料金・口コミは?
東進オンライン学校中学部は、授業中心で「先取り学習+定期テスト対策」に取り組める映像授業・通信教育教材です。この記事では、東進オンライン学校中学部について詳しく解説しています。
続きを見る