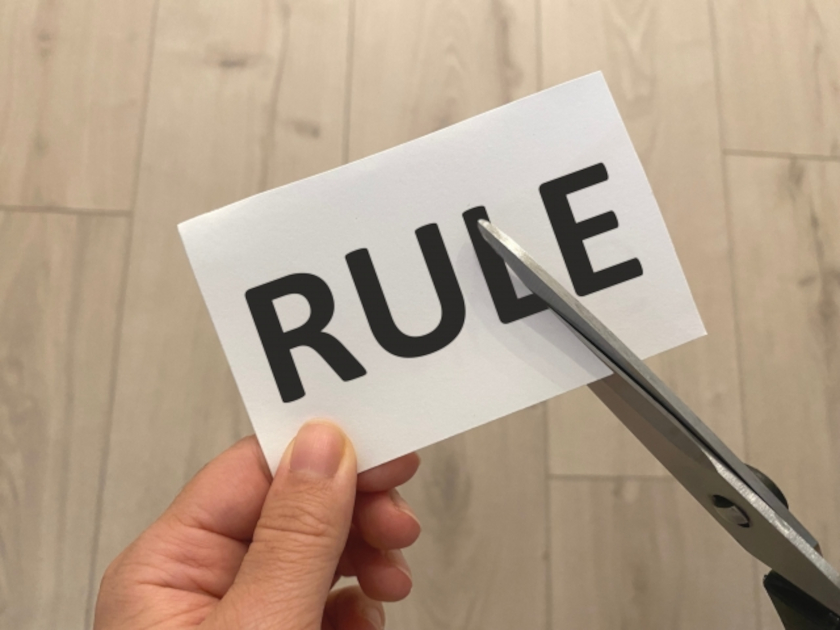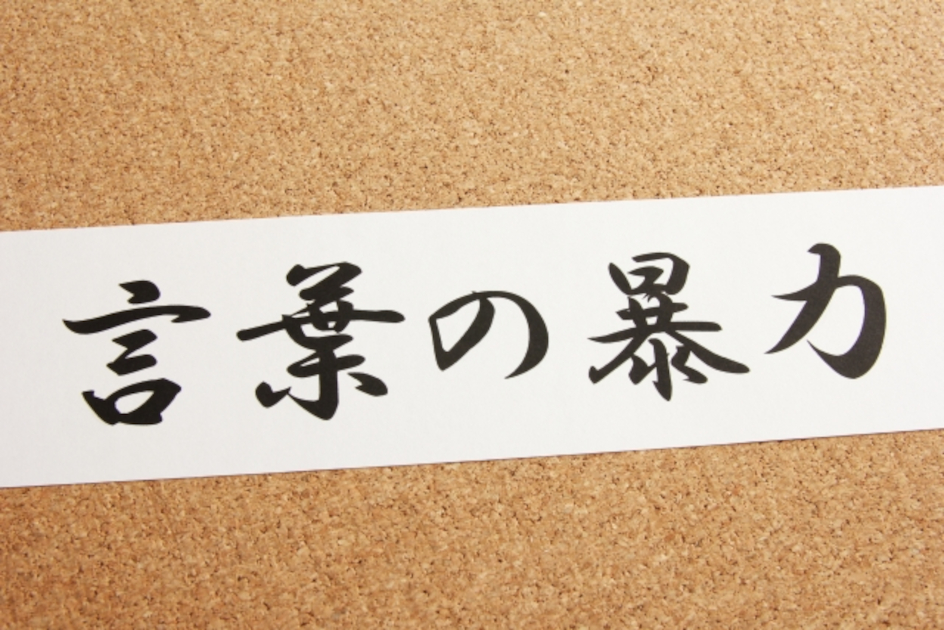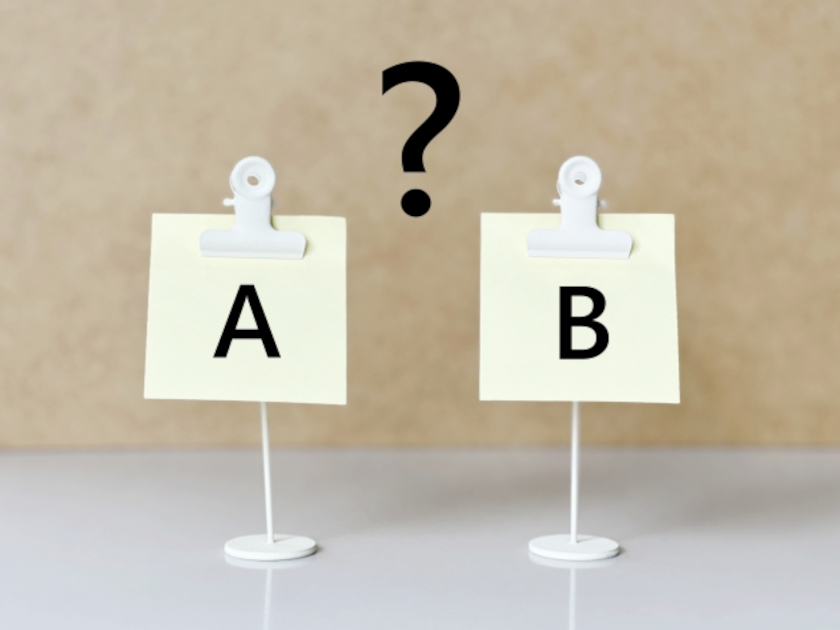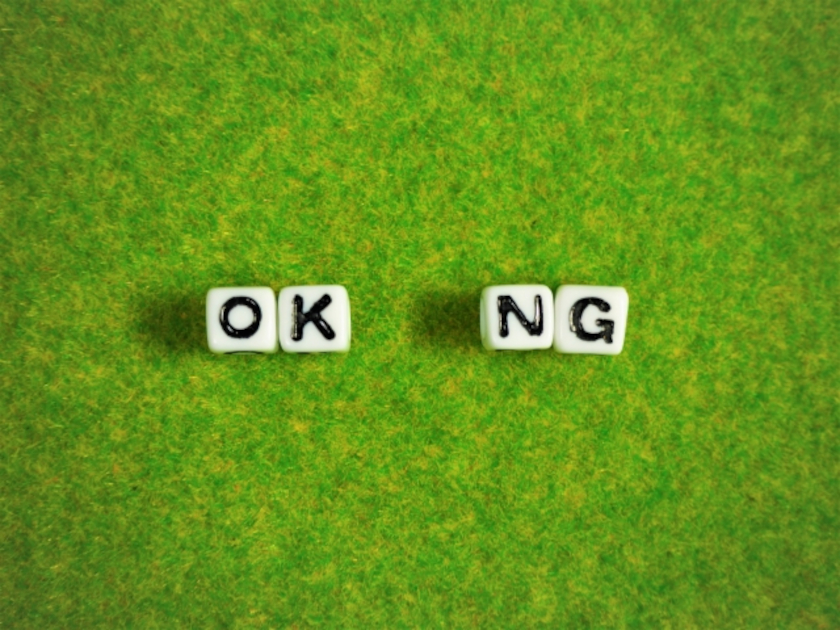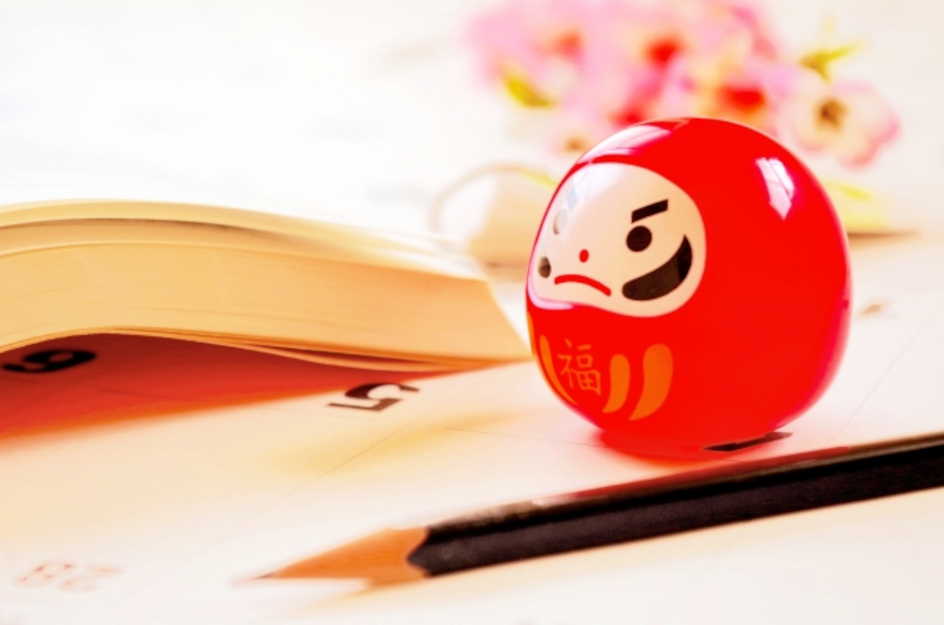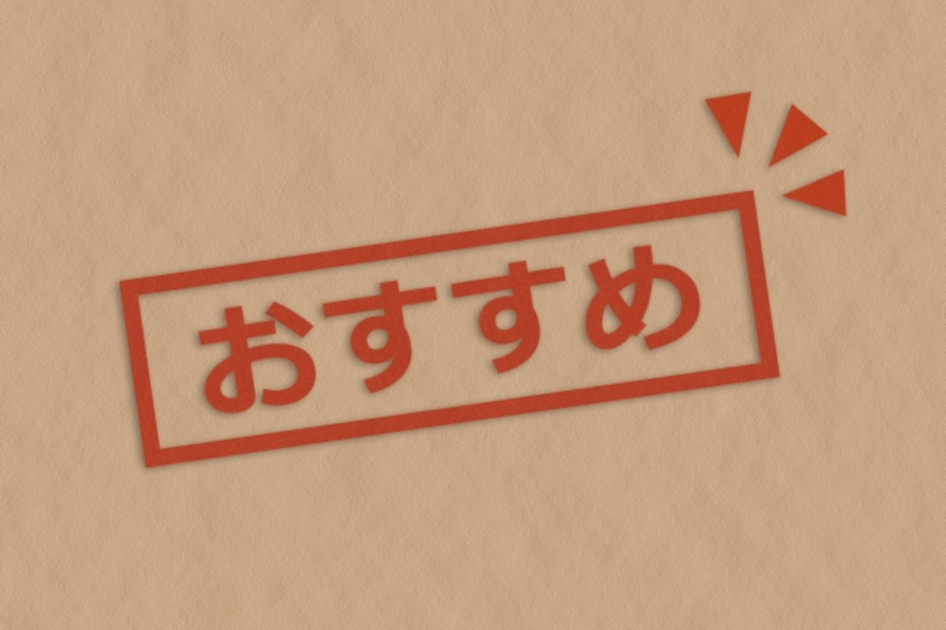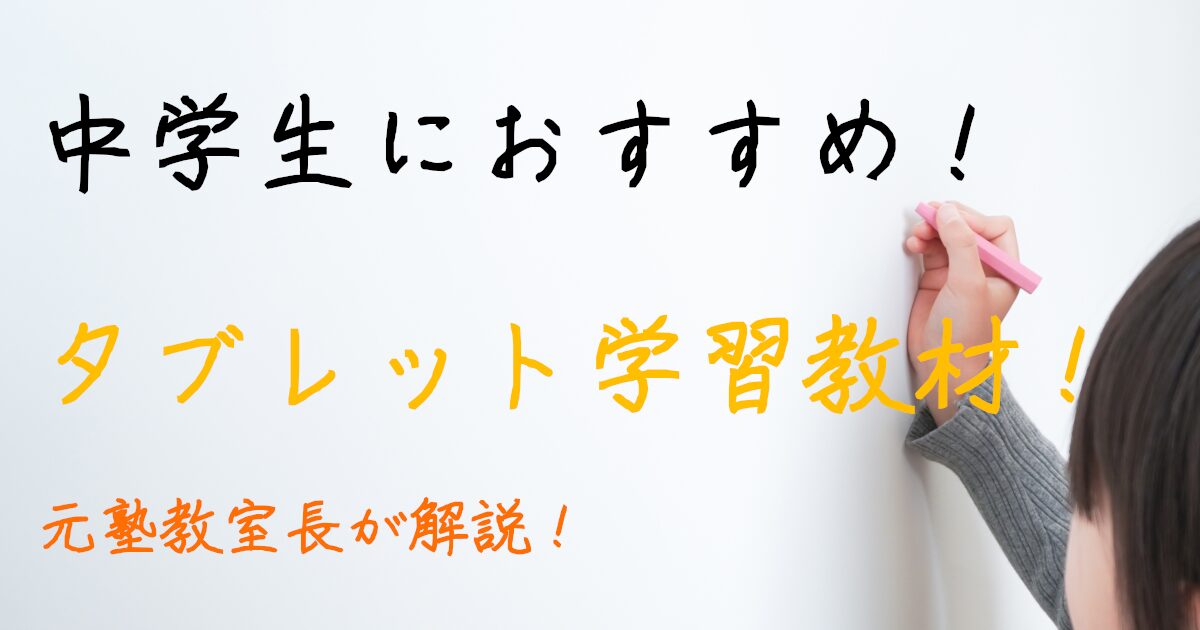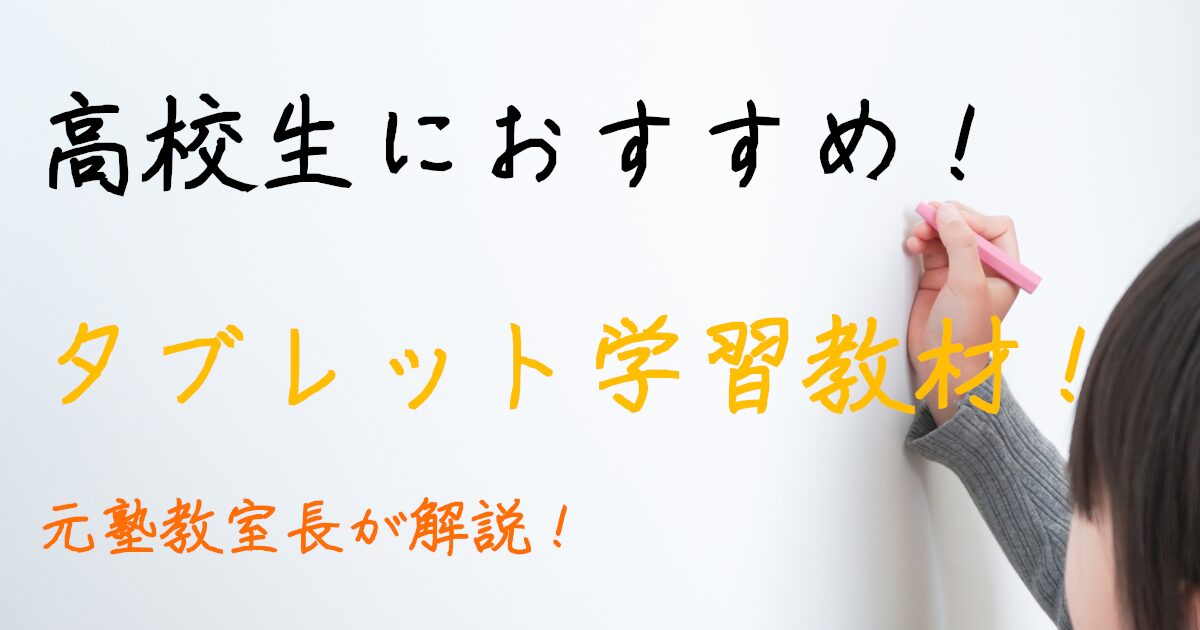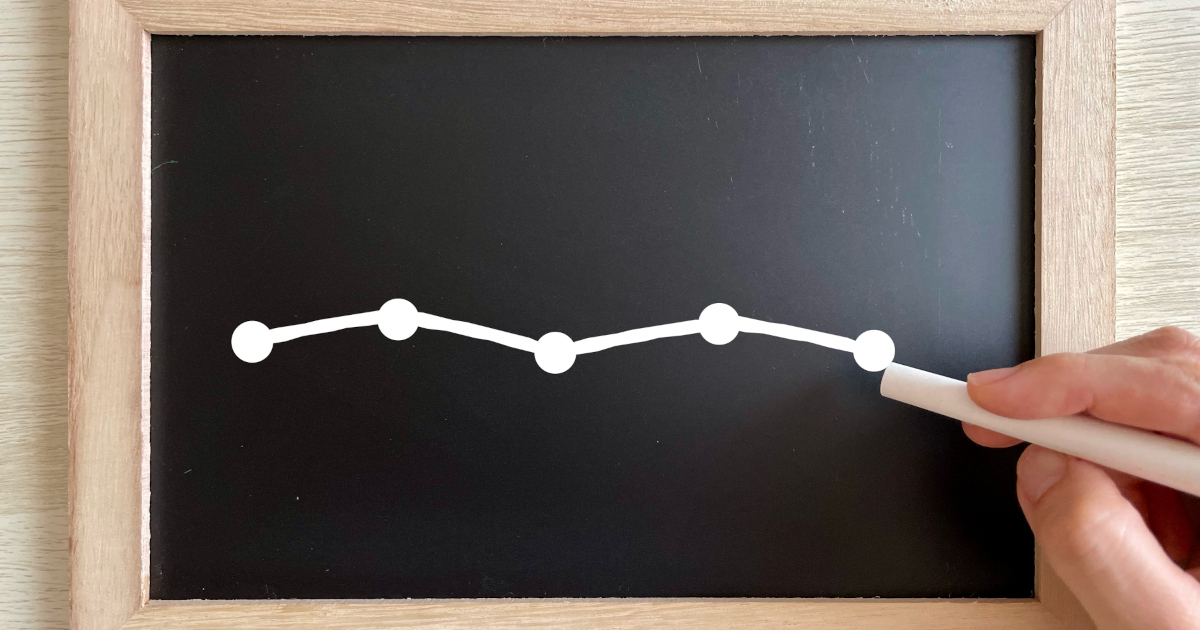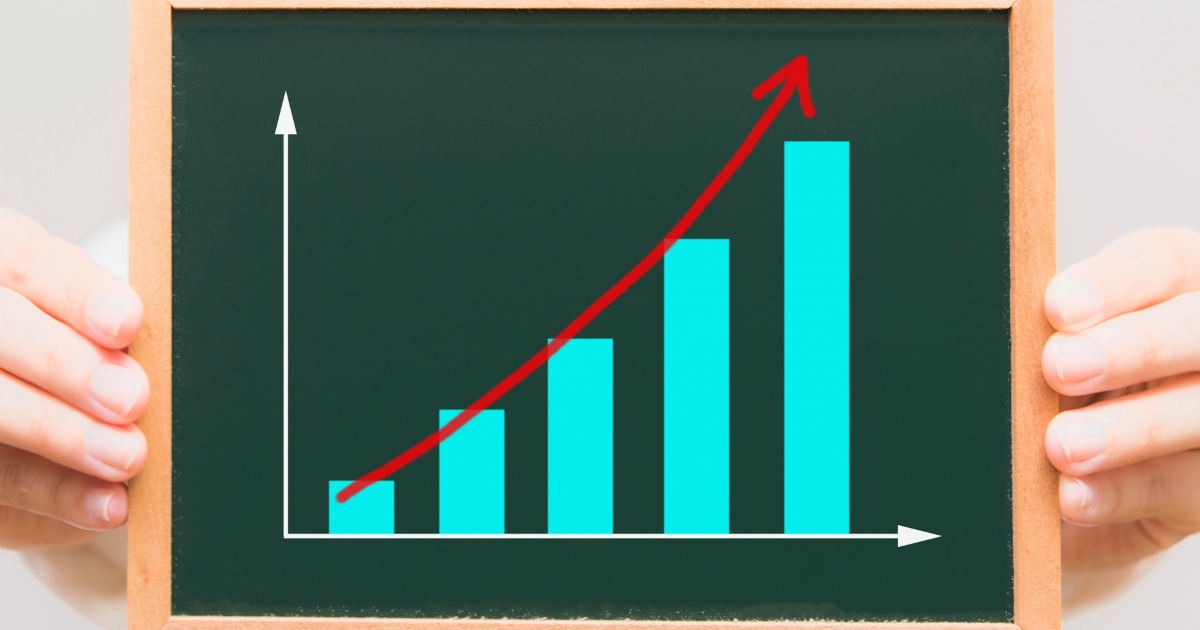こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

「部活を辞めたいと子どもに言われて判断に迷っている。」と、相談に来られる保護者の方は多いです。
部活を途中で辞めて逃げグセがついてしまわないか、内申に影響して受験が不利になってしまわないかと、いろいろな不安がよぎってしまいますよね。
結論
部活を辞めるべきかどうかの判断ポイントは、部活を続けることが子どもの成長につながるかどうかという1点だけです。
他に不安を感じる必要はありません。
今回は、部活を辞めることについて解説します。
部活を辞める際の注意点やポイントについても解説します。
最後まで読んでいただき、お子様が有意義な学校生活を送るための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
対面型の個別指導のような授業をオンラインで!
「オンライン家庭教師WAM![]() 」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!
」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!
安心の返金保証・成績保証!
▼詳しくはこちらから!
>>オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・特徴は?
まずは子どもの話を深掘りする
子どもに「部活を辞めたい。」と相談されたら、まずは子どもの話をよく聞いて深掘りしてあげてください。
深掘りした先で、子どもの本音に触れられる可能性があるからです。
部活を辞めたい表面上の理由の先に、子どもの本音が隠れていることが多いからです。
子どもが話す部活を辞めたい理由には、たとえば次のようなものがあります。
部活を辞めたい理由
- 勉強との両立ができない
- 顧問による暴力(言葉の暴力含む)
- 部員との人間関係
- 他にやりたいことがある
- レギュラーになれない
- 体力的につらい
子どもがたくさん話せるように
どんな理由を話してきたとしても、否定せずにいろいろと聞いてみてください。
大人に何かと反発する時期の中学生や高校生が大人に相談しに来たということは、本人の中で相当悩んで考えてきたはずです。
もしかしたら、勇気を振り絞って相談しに来たかもしれません。
「なぜ」「いつから」「どういった経緯で」といった質問を挟みながら、子ども主導で話を進められるのが理想です。
言語化が苦手な子どもも多い
中学生や高校生は、上手に言語化できない子どもも多いです。
特に、「気持ち」や「感情」のような抽象的な概念は言葉にできないかもしれません。
それでもあきらめずにいろいろと聞いてみてください。
たくさん話していると、思ってもいなかった事実が発覚することもあります。
以前、言語化が苦手な生徒と話をしていて、次のようなことがありました。
ある日




別の日





この生徒は、積極的な理由で部活を続けたいと言ってわけではなく、顧問の先生が怖くて「辞める」と言えないから「部活を続けたい」と言っていたのでした。
この生徒はその後、結局部活を辞めました。
子どもたちとは、先入観にとらわれずに丁寧に対話することが大切だと感じたエピソードです。
部活を辞めるべきかどうかの判断ポイント1つだけ
子どもの話を深掘りしたら、部活を辞めるべきかどうかを判断するポイントは1点だけです。
部活を続けることが子どもの成長につながるかどうかという点だけです。
子どもが成長することが一番大切で、それ以外のことは大したことではないからです。
部活を続けることが子どもの成長につながらないようであれば、すぐに辞めてしまって問題ありません。



生徒から部活に関する話を機会は多かったのですが、一般的な社会常識から大きく外れるような特殊なエピソードも多かったです。
学校の部活というコミュニティーでは、非常に特殊な社会が形成されていることも多いです。
ブラック部活が多いのも事実です。
ブラック部活は子どもの成長をさまたげる


ブラック部活というと、「拘束時間が長い」ことに焦点が当てられることが多いですが、本当のポイントは時間の長さではありません。
子どもの人間的な成長をさまたげるような部活がブラック部活です。
たとえば、ブラック部活には次のような特徴があります。
ブラック部活の特徴
一つひとつ具体例を挙げながら解説します。
特徴1:学校全体のルールを守っていない
多くの学校には部活動についてのルールがあります。
学校としては、子どもたちに勉強と部活のバランスを取ってもらいと思っているからです。
部活動についての学校のルール例
- ○月から△月までの完全下校は18時
- 週に○日は部活の休日を作る
- 定期テスト△日前からは部活動は禁止
こういった学校全体の規則を守っていないようであればブラック部活です。
生徒からは、次のような話をよく聞きました。




顧問が積極的にルールを破っているようであれば、子どもの成長には悪影響です。
特徴2:ルールの抜け穴を見つけて練習する
部活動についての学校のルールには、例外があることが多いです。
ブラック部活は、その例外を上手に利用して部活の時間を増やします。
抜け穴を利用する例
- 学校外に集まって活動
- 自宅でリモート筋トレ
- 定期テスト直後に試合を入れる
- 早朝練習
学校外に集まって活動
生徒から一番よく聞くルールの抜け穴を利用する例は、学校外に集まって活動するというものです。
完全下校の時間までは学校で活動し、その後は学校外の運動場や体育館を借りて練習します。
あくまでも生徒が自主的に集まっているから、部活動ではないということらしいです。
自宅でリモート筋トレ
Zoom等のオンラインミーティングを利用して筋トレをするそうです。
カメラオフでの参加は認められないので、こっそりサボることはできません。
家でやっているから部活動ではないということらしいです。
定期テスト直後に試合を入れる
ほとんどの学校で定期テスト前は部活停止期間となりますが、定期テストの前後に試合がある場合は、部活動をしてもよいという例外があることが多いです。
どういう仕組みかはわかりませんが、定期テストの直後に毎回試合がある部活があります。
つまり、例外を利用して、定期テスト前もずっと練習を続けている部活があります。
例外が認められているから、ルールは破っていないということらしいです。
早朝練習
多くの学校では完全下校時刻が決められていますが、朝の時間に規則が決められている学校は少ないようです。
それを利用して、朝練ならぬ早朝練を行う部活があります。
朝6時頃に集合するそうです。
完全下校は守っているので、ルールは破っていないということらしいです。
特徴3:暴力
殴る蹴るなどの物理的な暴力を振るう部活の顧問はほとんどいなくなりましたが、精神的な暴力を振るう顧問は未だに多いです。
大きな声や音を出して怒ったり、大勢の前で叱責したり、心を傷つけるような言葉を投げつけたりする顧問は未だに多いです。
「厳しい」と「怖い」は異なります。
顧問自身が、「厳しい」と「怖い」の違いを理解していないことも多いです。
暴力による指導は、子どもの人格形成に悪影響があるので危険です。
特徴4:いじめ
部員の間でいじめがある場合もあります。
いじめは部活や顧問ではなく、一緒に活動している部員の問題だと思われるかもしれません。
しかし、いじめが起こりやすい環境も存在します。
特に、旧態依然とした運動部ではいじめが発生しやすい傾向にあります。
先輩後輩の関係に極端な上下関係があったり、顧問による物理的、または精神的な暴力があるような部活ではいじめが発生しやすいです。
いじめも、子どもの人格形成に悪影響があるので危険です。
ブラック部活は秒で辞めるべき
ブラック部活は今すぐ辞めるべきです。
ルールを平気で無視したり、ルールの抜け穴を探すような行為が、子どもの成長にプラスになるとは到底思えないからです。
暴力やいじめが、子どもに決定的な心の傷を残す可能性が高いからです。

大人の行動を見て、子どもはこのように思うでしょう。
部活の良いところの1つは、人とのつながりや社会性を学べることです。
その部活、人とのつながりや社会性を学べていると言えますか?
その部活、子どもの学びや子どもの成長に有益な部活ですか?
その答えが「ノー」であるのならば、今すぐその部活を辞めましょう。
部活を辞めることを再考すべき場合
部活を辞めるべきかどうかの判断ポイントは、子どもの成長につながるかどうかの1点ですが、次のような場合には部活を辞めるかどうか一度立ち止まって再考したほうが良いです。
再考したほうが良い場合
一つひとつ解説します。
ケース1:部活と勉強の両立ができない
部活と勉強の両立ができないと感じて部活を辞めようと考えているのであれば、少し立ち止まって考えてみるべきです。
探してみると、勉強するための時間は思った以上にあることが多いからです。
まずは、次のような時間を勉強時間にできないか考えてみてください。
勉強時間チェックリスト
- テレビや動画サイトを見ている時間
- ゲームやSNSで遊んでいる時間
- 部活がオフの日
- 寝る前の30分
- 夕食前の30分
- 夕食後の30分
- 電車などの移動時間
まずはタイムマネージメント
部活が忙しい中でも勉強に取り組むことができると、タイムマネージメントの力を育てることができます。
忙しい中でもスキマ時間を見つけて勉強に取り組む事スキルを身につけておくと、部活引退後の本気の受験勉強のときに役立ちます。
部活と勉強の両立に悩んだときは、まずはスキマ時間を探してみてください。
スキマ時間を探さずに部活を辞めてしまうと、部活を辞めたあとも結局ダラダラして勉強に取り組めないことが多いです。
ただし、タイムマネージメントにも限界があります。
「睡眠時間を削らないと勉強時間を確保できない!」というような長時間部活の場合は辞めてしまって問題ありません。
ケース2:他にやりたいことがある
他にやりたいことがあって部活を辞める場合には、具体的に何をしたいのかよくよく話し合ってみたほうが良いです。
隣の芝が青く見えているだけかもしれないからです。
新しくやりたいことについて、どれくらい本気で取り組みたいと考えているのか、どれくらいの時間を使いたいと思っているのか、しっかりと話を聞いてあげると良いでしょう。
対話は、子どもにとっても頭の中のモヤッとした考えをしっかりと言語化できるというメリットがあります。
必要であれば、親子で一緒に考えたり調べたりして、具体的な未来像をイメージできるようにすると良いです。
そのうえで、部活を続けたほうが子どもの成長につながるのか、新しくやりたいことに取り組んだほうが子どもの成長につながるのか、よく話し合って判断すると良いです。
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
ケース3:レギュラーになれない
「試合に出たいのにレギュラーになれない」ということが部活を辞めたい理由であれば、安易に部活を辞めないほうが良いことが多いです。
安易に辞めてしまえば、成功するための思考を放棄することになるからです。
人生なんてうまくいかないことのほうが多いです。
それでもなんとかうまくいくために試行錯誤して努力してみることで、人は成長していきます。
環境を言い訳にして何も手を打たないようであれば、人としての成長は難しいでしょう。
レギュラーになれないのであれば、どうすればレギュラーになれるかを考えるべきです。
ただ、中学生や高校生の子どもが一人で抱えるには難しすぎる悩みかもしれません。
友人や大人にアドバイスをもらいながら考えられるようサポートしてあげられると良いです。
「得意・不得意」「好き・嫌い」で判断しても良い
レギュラーになれないという理由で部活を辞めてしまっても良い場合もあります。
人には得意・不得意があり、好き・嫌いがあります。
不得意なものに無理やり取り組む必要はありませんし、嫌いなものを無理して続ける必要もありません。
まして、部活は自由参加です。
部活に強制参加の学校であっても、所属する部活は自分で選ぶことができます。
わざわざ不得意で嫌いなものを選ぶ必要はありません。
「レギュラーになれない」ことが部活を辞めたい理由なのか、「不得意で嫌い」であることが部活を辞めたい理由なのか、切り分けて考える必要があります。
理不尽な理由な場合は辞める
理不尽な理由でレギュラーになれないようであれば、部活を辞めてしまったほうが良いです。
たとえば、次のような理由でレギュラーに選ばれないようであれば辞めてしまいましょう。
理不尽な理由
- 実力があっても1年生は試合に出られない
- 顧問に嫌われていて試合に出られない
- いじめ
ケース4:体力的につらい
体力的につらいから部活を辞めたいということであれば、少し立ち止まって考えたほうが良いです。
続けていればそのうちつらくなくなる可能性があるからです。
特に、新しい部活に入って日が浅いようであれば、もう少し頑張ってみるべきです。
続けていれば体力も持久力も向上して、それほどつらいと感じなくなってくる可能性があります。
ただし、トレーニングの負荷があまりにも高くて、学校の授業中にいつも寝てしまったり、家に帰ったらお布団に直行してしまうという状況が何ヶ月も続くようであれば、部活を辞めてしまって良いでしょう。
部活を辞めるときに心配なこと


部活を辞めるときには、受験のことや人間関係のことも心配です。
今までの生徒から相談されたことをベースに、よく相談される悩みとその対処法を解説します。
一つひとつ解説します。
心配事1:辞めさせてもらえない


部活を辞めるときに、顧問が辞めさせてくれないという相談はとても多かったです。
「辞めさせてくれない」なんて、まるでブラック企業です。
そもそも自由参加である部活に「辞める許可」は必要ないはずなのですが、顧問の許可制がまかり通っているブラック部活は多いです。
子どもたちも、顧問の許可が必要であると思いこんでいる場合が多いです。
顧問が怖くて「辞めたい」と言い出せずに、イヤイヤ部活を続けている生徒も多いです。
部活は辞めたければ辞めれば良いですし、行きたくなければ行かなくても良いです。
他の大人にも相談


教師にもいろいろな教師がいて、大人にもいろいろな大人がいるものです。
それに、できる限り「ちゃんと正式に」部活を辞めたいものです。
顧問と一対一の交渉が難しいようであれば、他の大人や先生に相談してみるべきです。
クラスの担任や教頭先生、校長先生に相談してみても良いです。
教頭先生や校長先生に相談しに行くのは少し敷居が高く感じるかもしれませんが、教頭先生や校長先生も、生徒が想像している以上に生徒の話を聞いてくれます。
顧問の同僚では話が進まない場合も、顧問の上司に当たる人間に相談すると話が進む場合もあります。
保護者が仲介しても良い
大人との交渉に、子ども一人だけで臨むのは少し酷です。
状況によっては、保護者の方が交渉に加わっても良いでしょう。
子どもの学校のことに大人が口を挟むのは、お世話になっている学校にクレームを出すようで嫌だという保護者の方も多いのですが、子ども一人できることにも限界があります。
「子どものサポート」という意味合いで助けてあげられると良いです。
それぞれの先生にそれぞれの考え方があります。
顧問の先生との一対一の話し合いでは行き詰まってしまっても、顧問以外の大人に相談してみると意外とすんなりと話が進むこともあります。
困ったときは第三者の力を借りるということは重要です。
理由は言わなくてもいい
部活を辞める理由が、顧問には言いづらい理由であることもあります。
部活を辞める理由は、顧問の先生に必ずしも説明する必要はありません。
もちろん、部活を辞めたい理由をしっかりと説明して、生徒と顧問双方が納得したうえで部活を辞めた方が良いです。
ですが、「そんな理由では退部は認められない!」と、交渉にならないこともあります。
そういった場合は、部活を辞める理由を無理に説明する必要はありません。
「家庭の事情」や「勉強時間を確保するため」で十分です。
心配事2:他の部員に迷惑がかかる

責任感が強い子どもは、他の部員に迷惑がかかるのではないかと悩んでしまうことも多いです。
そう思う気持ちは非常に良くわかります。
他者を思いやる気持ちはとても大切です。
それと同時に、自分自身を思いやる気持ちもとても大切です。
チームメイトのことを思いやるばかりに、自分自身の気持ちをないがしろにしてしまっていないか、子どもに問いかけてみてください。
心配事3:元部員との人間関係

部活を辞めた元チームメイトをいじめるような部活は健全とは思えないので辞めてしまって正解ではあるのですが、それでも無視をされて孤立してしまうとつらいです。
ですので、部活の中だけの狭いコミュニティーに依存せずに、もっと広く人付き合いをしておくことをおすすめします。
部活のメンバーとは長い時間を一緒に過ごすので、自然とつながりが強くなります。
それはとても良いことですが、部活のメンバーとのつながりだけになってしまうと視野が狭くなってしまいます。
同じクラスの友達や、部活以外の趣味などのつながりも持っておくべきです。
そうすれば、部活の元チームメイトから無視されるようになったとしても孤立してしまうことはありません。
心配事4:受験に影響はないか


勘違いされている方は多いのですが、高校受験における内申点とは通知表の評定の数字のことです。
5段階で評価されるあの数字のことです。
「生徒会長を務めていた」や「部活を3年間続けた」は、一般入試では内申点に含まれません。
高校受験の推薦入試には影響する
推薦入試では「3年間部活を続けたこと」が評価される場合があります。
数は少ないですが、「同一部活3年間継続で内申点+1」としている高校もあります。
面接試験でもアピールポイントとして話すことができるでしょう。
しかし、その程度のことです。
「内申点+1」は他の学校活動でももらえますし、英検や漢検などの検定でももらえます。
そもそも、定期テストの成績を上げて通知表の評定を上げれば済むことです。
面接試験のアピールポイントも、部活以外の活動を頑張れば問題ありません。
>>高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!
大学受験では影響は皆無
大学受験においては、部活を3年間続けたことが評価されることはありません。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)や総合型選抜(旧AO入試)では調査書が評価対象になることが多いので、もしかしたら一部で部活の継続が評価されているのかもしれません。
しかし、私が見てきた生徒の中で、部活を続けたことが評価されて合格したと実感したことはありません。
逆に、部活を途中で辞めたことが原因で不合格になったと感じた生徒もいません。
部活を辞めたあとの時間の使い方は事前に話し合う
部活を辞める前から、空いた時間で何をするか、子どもと話し合っておくことが大切です。
1日の多くの時間を占めていた部活に行かなくなると、ポッカリと時間の穴が空いてしまいうからです。
突然時間に余裕ができてしまうと、大人でも戸惑ってしまいます。
塾に通いはじめるのも良いですし、以前からやってみたかったことをはじめるのも良いでしょう。
新しいことをはじめるのであれば、部活を辞めた瞬間からはじめられるように準備しておいたほうが良いです。

このように思っていると失敗します。
物事は、スタートするときに最も大きなエネルギーを必要とします。
部活を辞めたあとにしばらく休んでしまうと、そのままダラダラと過ごしてしまい、結局何もはじめられなかったということになってしまう可能性があります。
間髪入れずに新しいことにチャレンジしましょう!
何から始めればよいかわからないときは


勉強の基本は、学校の授業です。
学校の授業の予習復習に取り組むだけで、学習内容の理解度が一気に上がります。
勉強は、同じ内容を繰り返すことで頭に定着するからです。
学校の予習復習に取り組むのであれば、学校の教科書と授業中に書いたノートで十分に対応できます。
自分一人では取り組めるか心配な場合や、学校の授業以上のことをもっと頑張りたいという場合は、塾や学習サービスを利用すると良いです。
学校の予習復習におすすめの学習サービスは、次の3つです。
おすすめの学習サービス
- 地元の学習塾
- タブレット教材・通信教育教材
- 映像授業
地元の学習塾が一番おすすめですが、家庭の事情や子どもの得意・不得意によっては、タブレット教材・通信教育教材や映像授業が良い場合もあります。
以下に関連記事へのリンクを貼っておきますので、そちらもぜひ参考にしてください。
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!
この記事では、中学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。
続きを見る
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!
この記事では、高校生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。
続きを見る
-

-
オンライン家庭教師おすすめ10選!元塾教室長が徹底比較!
オンライン家庭教師はわかりやすい授業だけでなく、特徴的なサービスを提供している場合が多いです。料金だけで比較するのではなく、利用目的に合わせて子どもに合ったサービスを選べると、学力を伸ばすことができます。
続きを見る
-

-
定期テストで点数を取れない3つの理由と8つの対処法【元塾教室長が解説!】
定期テストで点数を取れないと悩む中学生・高校生は多いです。この記事では、定期テストで点数を取れない理由と具体的な対策について解説しています。
続きを見る
-

-
タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
タブレット教材は効率よく勉強できるのでおすすめですが、デメリットも多いので適切なケアが必要です。この記事では、タブレット教材の8つのメリット・デメリットについて解説しています。
続きを見る
-

-
定期テストで450点取って高校受験でも勝つための勉強法
学校の定期テストで5教科450点の壁をなかなか突破できないという中学生は多いです。この記事では、定期テストで450点以上取って高校受験でも勝つための勉強法を解説しています。
続きを見る
-

-
塾に通っているのに成績が上がらない理由3パターンと解決策【元塾教室長が解説!】
成績が上がらないからといって安易に塾を変えるのはおすすめしません。この記事では、塾に通っているのに成績が上がらない3パターンの理由と解決策について解説しています。
続きを見る
-

-
【段階別】中学生の数学の伸ばし方を元塾教室長が徹底解説!
数学は意識や取り組み方を変えると一気に伸びる教科です。この記事では、学習段階別に数学の成績の伸ばし方を解説しています。
続きを見る
まとめ
それでは、部活を辞めることについての解説をまとめます。
結論
部活を辞めるべきかどうかの判断ポイントは、部活を続けることが子どもの成長につながるかどうかという1点だけです。
他に不安を感じる必要はありません。
子どもに「部活を辞めたい。」と相談されたら、まずは子どもの話をよく聞いて深掘りしてあげてください。
子どもが部活を辞めたいと思ったときに話す理由は、主に次のようなものがあります。
部活を辞めたい理由
- 勉強との両立ができない
- 顧問による暴力(言葉の暴力含む)
- 部員との人間関係
- 他にやりたいことがある
- レギュラーになれない
- 体力的につらい
いろいろな理由で部活を辞めたいと思っていると思いますが、部活を辞めるべきかどうかの判断ポイントは、部活を続けることが子どもの成長につながるかどうかという1点だけです。
特に、所属している部活がブラック部活であれば、すぐに辞めさせるべきです。
ブラック部活は、子どもの人間的な成長をさまたげてしまうからです。
たとえば、ブラック部活には次のような特徴があります。
ブラック部活の特徴
- 学校全体のルールを守っていない
- ルールの抜け穴を見つけて練習する
- 暴力
- いじめ
次のような場合には部活を辞めるかどうか一度立ち止まって再考したほうが良いです。
再考したほうが良い場合
- 部活と勉強の両立ができない
- 他にやりたいことがある
- レギュラーになれない
- 体力的につらい
部活を辞めるときには、受験のことや人間関係のことも心配です。
今までの生徒から相談されたことをベースに、よく相談される悩みとその対処法を解説しました。
心配なこと
- 辞めさせてもらえない
- 他の部員に迷惑がかかる
- 元部員との人間関係
- 受験に影響はないか
部活を辞めたあとに何をするのか、事前に子どもと話し合っておくことが大切です。
間髪入れずに新しいことにチャレンジしましょう!
何から勉強すれば良いかわからない場合は、学校の授業の予習復習から取り組むことをおすすめします。
学校の予習復習におすすめの学習サービスは、次の3つです。
おすすめの学習サービス
- 地元の学習塾
- タブレット教材・通信教育教材
- 映像授業
今回の記事が、お子様が有意義な学校生活を送るための参考となればとてもうれしいです。
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!
この記事では、中学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。
続きを見る
-

-
高校生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!
この記事では、高校生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。
続きを見る
-

-
オンライン家庭教師おすすめ10選!元塾教室長が徹底比較!
オンライン家庭教師はわかりやすい授業だけでなく、特徴的なサービスを提供している場合が多いです。料金だけで比較するのではなく、利用目的に合わせて子どもに合ったサービスを選べると、学力を伸ばすことができます。
続きを見る
-

-
定期テストで点数を取れない3つの理由と8つの対処法【元塾教室長が解説!】
定期テストで点数を取れないと悩む中学生・高校生は多いです。この記事では、定期テストで点数を取れない理由と具体的な対策について解説しています。
続きを見る
-

-
タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
タブレット教材は効率よく勉強できるのでおすすめですが、デメリットも多いので適切なケアが必要です。この記事では、タブレット教材の8つのメリット・デメリットについて解説しています。
続きを見る
-

-
定期テストで450点取って高校受験でも勝つための勉強法
学校の定期テストで5教科450点の壁をなかなか突破できないという中学生は多いです。この記事では、定期テストで450点以上取って高校受験でも勝つための勉強法を解説しています。
続きを見る
-

-
塾に通っているのに成績が上がらない理由3パターンと解決策【元塾教室長が解説!】
成績が上がらないからといって安易に塾を変えるのはおすすめしません。この記事では、塾に通っているのに成績が上がらない3パターンの理由と解決策について解説しています。
続きを見る
-

-
【段階別】中学生の数学の伸ばし方を元塾教室長が徹底解説!
数学は意識や取り組み方を変えると一気に伸びる教科です。この記事では、学習段階別に数学の成績の伸ばし方を解説しています。
続きを見る