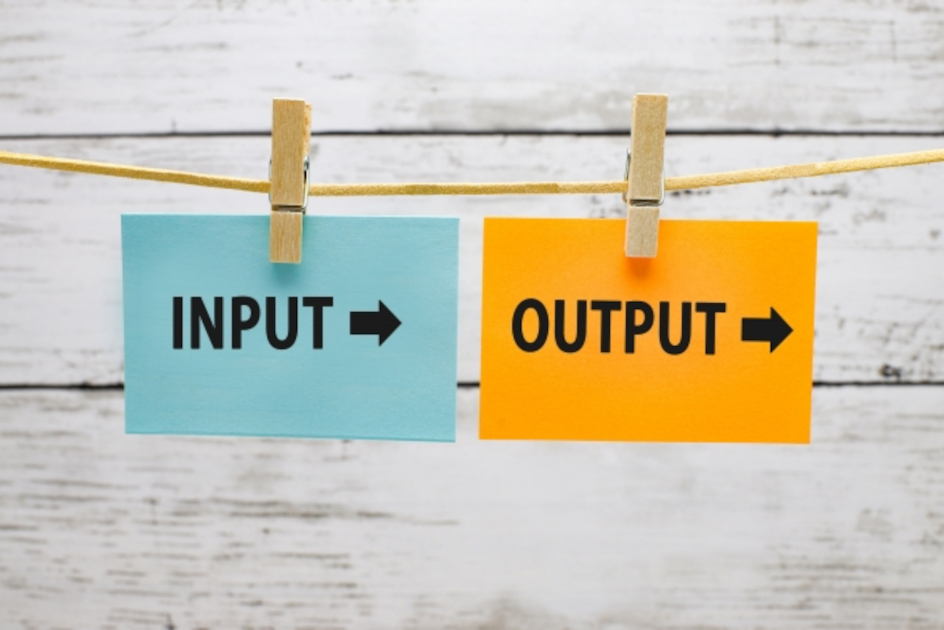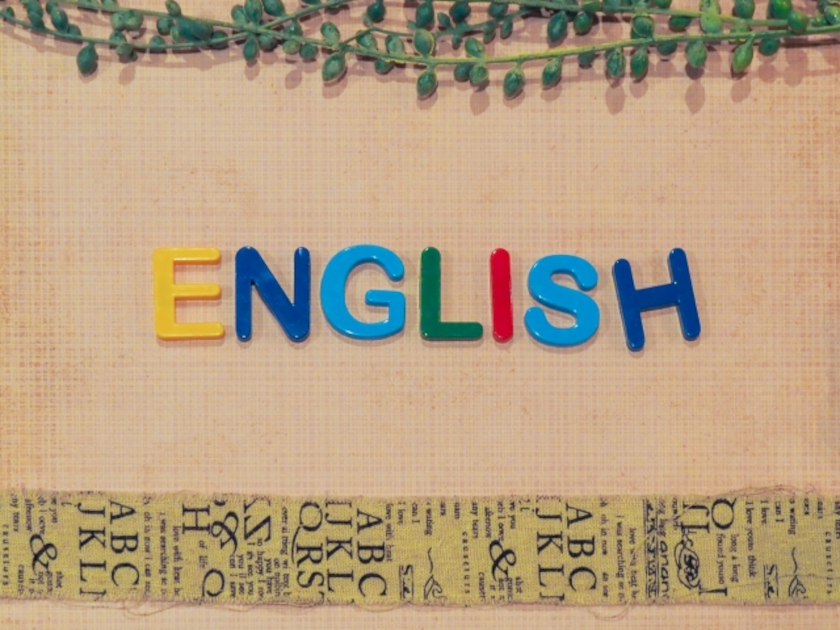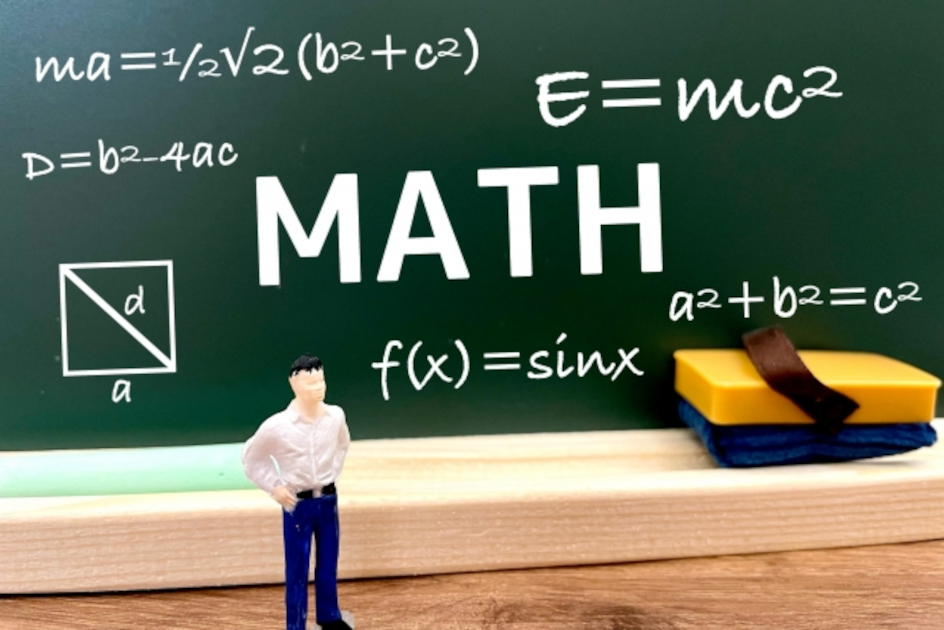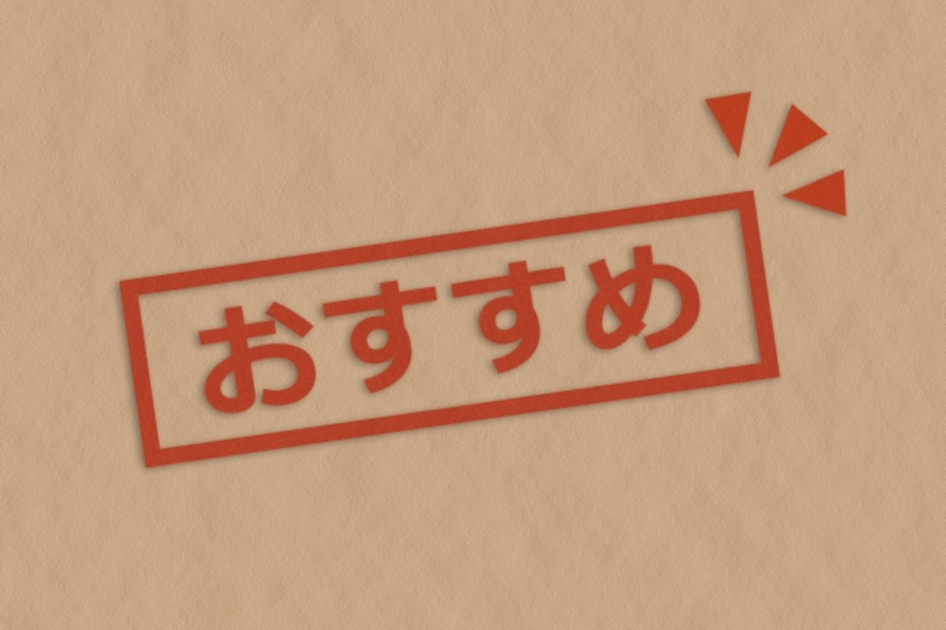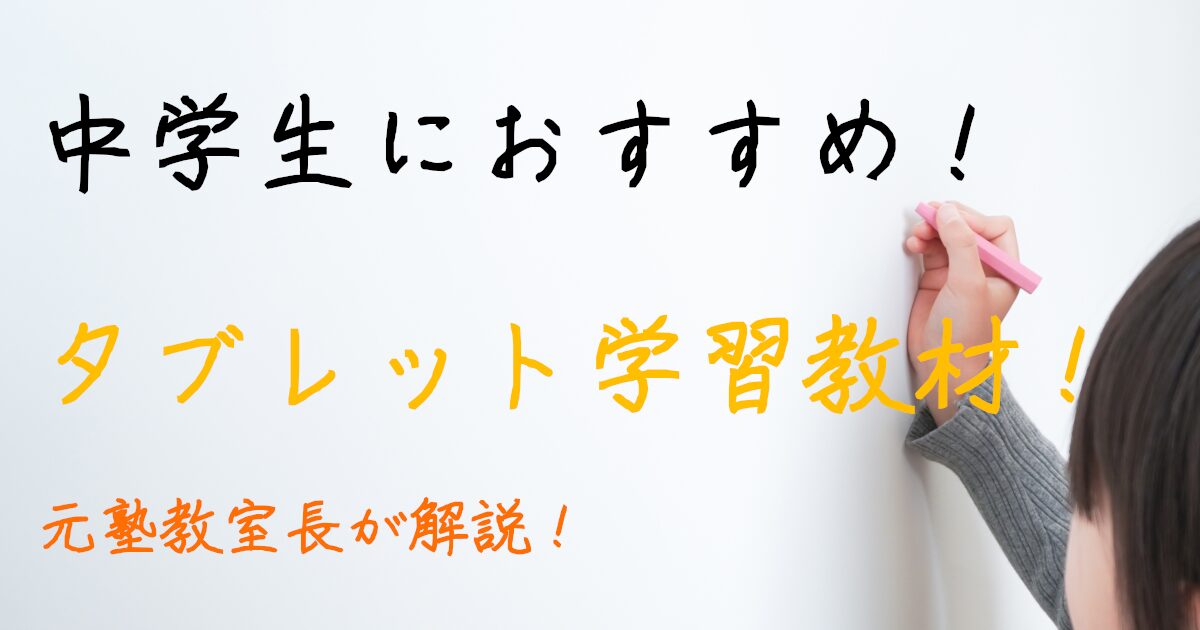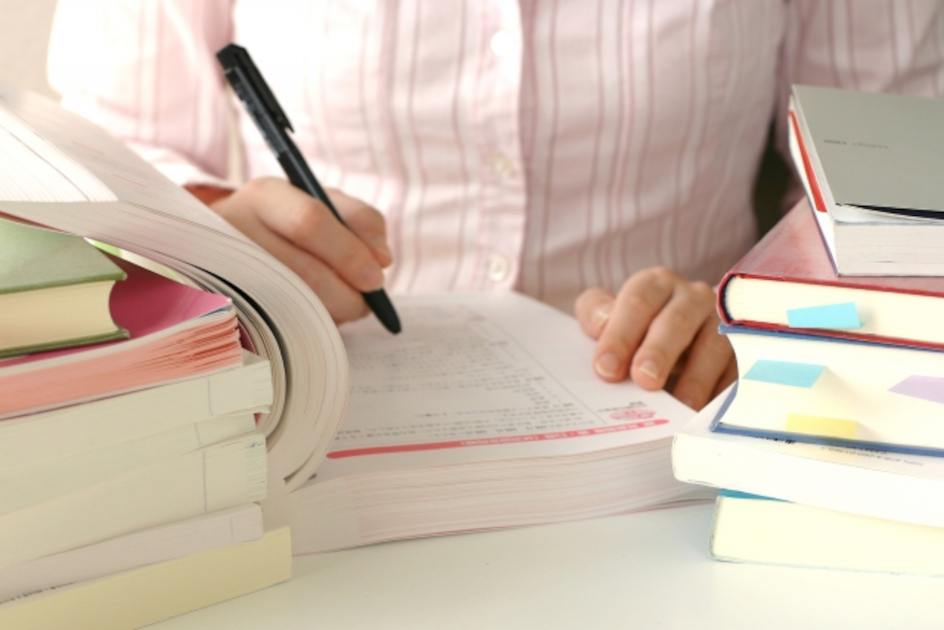こんにちは。エデュサポ(@edsuppor)です。

高校受験に向けて受験勉強をはじめようと思っても、何をすればよいのかわからないと悩む中学生は多いです。
保護者の方としても、志望校に合格するためにどのようなことに取り組ませれば良いのかと悩まれているのではないでしょうか。
結論
受験勉強は、基礎固めからはじめることが大切です。
受験勉強をスムーズにスタートさせるためには、普段の勉強を大事にすることが重要です。
今回は、高校受験の受験勉強は何をすべきかについて解説します。
教科別のはじめかたや、はじめる前にやるべきことについても解説します。
最後まで読んでいただき、お子様がスムーズに受験勉強をスタートさせて、志望校に合格するための学力を身につけていくための参考としていただければとてもうれしいです。
この記事の筆者

エデュサポ
(@edsuppor)
- 元塾教室長
- 集団塾と個別指導塾で講師と教室長を務め、オンライン教育系の塾運営責任者も務める
- 塾業界勤務経験は20年以上
- 教育業界での経験を活かして、勉強や受験に関する情報を発信するサイトやブログを開設
対面型の個別指導のような授業をオンラインで!
「オンライン家庭教師WAM![]() 」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!
」は、対面型の個別指導塾に近いスタイルの授業を、オンラインで受けることができるサービス!
安心の返金保証・成績保証!
▼詳しくはこちらから!
>>オンライン家庭教師WAMは個別指導スタイルの授業をオンラインで受けられる!料金・特徴は?
受験勉強は何をすればいいのか
受験勉強でやるべきことを大きく4つのステップで分けると、次のようになります。
受験勉強でやるべきこと
一つひとつ解説します。
ステップ1:授業を受けて知識をインプットする
受験勉強で最初にやるべきことは、知識のインプットです。
教科書や参考書を読んで知識をインプットすることもできますが、インプット学習は、授業を受けて誰かに教わったほうが効果的です。
授業では、文字情報だけでなく音情報も入ってきますし、ノートを書いたり先生の質問に答えたりと、多くの感覚を使って学ぶことができるからです。
まずは授業を受けて知識をインプットしていけると良いです。
概念理解や考え方の理解は特に授業が重要
英数学の考え方や英文法の学習では、概念的な理解が必要になります。
概念理解が必要な内容ほど、授業を受けてインプットしていくことが重要になります。
概念を文字情報だけで理解するのはとても難しいからです。
説明が上手な先生に、難しい概念を噛み砕いて解説してもらえると理解しやすいです。
授業以外のインプットも重要
インプットは授業を受けるだけでなく、自分で基礎演習に取り組むことも重要です。
英単語や英熟語、漢字や古文単語など、自分でコツコツと積み上げていくインプット学習も大切です。
基礎演習でインプットすべきこと
- 英単語・英熟語
- 漢字・言葉の意味
- 古文単語
- 地名・人物名
- 用語
▼あわせて読みたい
>>効率的な暗記方法!長期記憶にするための19のコツ【元塾教室長が解説!】
▼あわせて読みたい
>>【元塾教室長が解説!】英単語の覚え方20のコツ
ステップ2:問題演習でアウトプットする
授業や基礎演習で知識をインプットしたら、今度は問題演習を解くなどして、知識をアウトプットする練習をします。
勉強は「わかる」だけでは不十分で、自分の力で「できる」ようにしなければならないからです。
自分の力だけで問題を解けるようなって初めて、テストで点数を取れるようになります。
「インプット→アウトプット」の繰り返し
「インプット→アウトプット」を何度も繰り返すことで、学習内容が定着していきます。
一度やったら終わりにするのではなく、同じ学習内容を何度も繰り返すことが大切です。
「自分の力だけでできる」を追求することが大事
問題演習で解けなかった問題は、必ず解説を読んで解き方を理解する必要する必要があります。
さらに、解き方を理解して終わりにするのではなく、次の日にもう一度同じ問題を解いてみます。
何の助けも借りずに解くことができたら、その問題は「自分の力だけでできる」ようになったということです。
もう一度解いてみて解けなかったら、まだ「自分の力だけでは解けない」ということです。
もう一度解説を読んで解き方を理解して、次の日にもう一度トライしてみます。
「自分の力だけでできる」ようになるまで、何度でも挑戦します。
とにかくたくさん問題を解くのはなく、一つひとつの問題を、「自分の力だけでできる」ようにしていくことが重要です。
ステップ3:定期的に復習をして定着させる
受験勉強では、各教科の単元ごとに、一つひとつ勉強を進めていくことになりますが、ある程度勉強が進んだら、これまでに勉強した内容の総復習に取り組めると良いです。
定期的に復習に取り組むと、以前に学習した内容をより一層定着させることができるからです。
逆に、定期的に復習に取り組まないと、以前に学習した内容を忘れていってしまいます。
特に、夏休みや冬休みなどの学校の長期休み期間は、これまでの学習の復習に取り組む絶好の機会です。
▼あわせて読みたい
>>【高校受験】中3夏休みの志望校に合格するための過ごし方!
▼あわせて読みたい
>>中学生の冬休みの過ごし方!勉強時間や勉強方法は?【1年生・2年生】
▼あわせて読みたい
>>中2夏休みの勉強方法!勉強時間や高校受験で勝つためのポイントは?
▼あわせて読みたい
>>【高校受験】受験生の冬休みの過ごし方!勉強時間や勉強方法は?
▼あわせて読みたい
>>【中1】夏休みの効果的な勉強方法!勉強時間や気をつけるポイントは?
ステップ4:過去問を解いて傾向を研究する
高校受験の受験勉強の仕上げは、過去問演習です。
入試に対応できる学力が身についてきたら、その学力を最大限点数に結びつけるための練習をする必要があるからです。
実際の入試問題を解くことで、実力を点数に結びつけることができます。
過去問演習でできること
- 入試の出題傾向を研究できる
- 実際の難易度を肌で感じることができる
- 解く順序や時間配分を決められる
- 苦手分野を見つけて対策できる
過去問は、実際に受験する高校の過去問だけでなく、似たような出題傾向の高校の過去問もたくさん解くと良いです。
入試直前期に過去問演習にたっぷりと時間を割けるように、できる限り早期に基礎力を身につけられると良いです。
▼あわせて読みたい
>>中学生の英語の先取りは受験で勝つために超重要!【元塾教室長が解説!】
▼あわせて読みたい
>>中学からの数学の先取り学習は難関大学合格のために必須
【教科別】受験勉強は何からはじめるか
ここからは、高校受験の受験勉強は何からはじめるべきか、教科ごとに解説していきます。
どの教科にも共通して言えることは、基礎固めからはじめるべきということです。
勉強は、基礎基本が一番大切だからです。
【教科別】受験勉強は何からはじめるか
【英語】英単語・英熟語・英文法から
英語の受験勉強は、英単語・英熟語・英文法の3点セットからはじめるべきです。



入試では、文法のマニアックな知識を問われる問題は少なくなり、文章を読む中でスピーディーに文法を使いこなせる力が求められるようになってきています。
英単語・英熟語・英文法は、悩まずにスピーディーに運用できるようになるまで、徹底的に定着させるようにすると、入試で有利です。
▼あわせて読みたい
>>英語が全然できない中学生のための苦手克服勉強法!おすすめの教材や得意にするための対策も!
▼あわせて読みたい
>>英検が高校受験に超絶有利な3つの理由!中学生は英検を絶対に受けるべき
▼あわせて読みたい
>>中学生が英語の成績を上げるために英会話をはじめるべき2つの理由!
▼あわせて読みたい
>>中学英語が難しくなった!つまずいてしまったら早期に対策!
【数学】計算練習から
数学の受験勉強は、計算練習からはじめるべきです。
多くの高校で計算問題が出題されますし、計算問題の配点は決して小さくないからです。
また、計算力は数学の力を伸ばすための大切な基礎力でもあります。
まずは中学1年生で学習した「正負の数」や「文字式」、「方程式」の計算から、順番に計算練習に取り組んでいくと良いです。
まずは解き方を理解しているか確認
数学の計算練習に取り組むときは、まずは解き方がしっかりと身についているかどうかを確認していきます。
解き方が身についていない単元や、計算方法を忘れてしまっている単元がないか、中学1年生の学習範囲から一つひとつチェックしていけると良いです。
速さと正確性も大事
数学の計算練習に取り組むときは、速さと正確性を追い求めることも大切です。
計算方法が身についている単元も、繰り返し練習をして、速く正確に解けるようにトレーニングを続けることが大切です。
▼あわせて読みたい
>>数強塾は数学が苦手な中学生・高校生の強い味方!料金・サービスは?
▼あわせて読みたい
>>【段階別】中学生の数学の伸ばし方を元塾教室長が徹底解説!
▼あわせて読みたい
>>【元塾教室長が解説!】中学数学を復習するための効率的な勉強方法
▼あわせて読みたい
>>【中学数学】証明問題の苦手を克服するための根本的な方法【元塾教室長が解説!】
▼あわせて読みたい
>>数学の応用問題が解けない!解き方のコツと勉強法【元塾教室長が解説!】
【国語】漢字・古文単語・文法と読解方法を知るところから
国語の受験勉強は、漢字・古文単語・文法の基礎知識の積み上げと、正しく文章を読解する方法を知るところからはじめるべきです。
漢字の暗記に取り組むときは、漢字の練習をするだけでなく、熟語の意味も一緒に覚えられると効果的です。
たとえば、「矛盾」という漢字を暗記するときは、「矛盾」を書いて覚えながら、意味は「前後のつじつまが合わないこと」と覚えてしまえると良いです。
国語では、現代文でも古文でも語彙力が非常に重要になるので、言葉の意味を覚えることはとても大切です。
▼あわせて読みたい
>>【高校受験】漢字の勉強は超重要!効果的な勉強法とおすすめの問題集
▼あわせて読みたい
>>漢検が高校受験に超絶有利な3つの理由!中学生は漢検を絶対に受けるべき
文法は古文も現代文も
古文を読むためには、古文の文法知識が必要です。
そのため、古文の勉強では、まずは古文の文法の基礎知識を身につけておく必要があります。
古文と現代文の文法にはつながる部分も多いので、どちらの文法も取り組むべきです。
現代文の文法の勉強をおろそかにしてしまう中学生は多いのですが、現代文の文法は英語の文法の理解にもつながりますので、しっかりと取り組むべきです。
文章読解は問題を解くだけでは身につかない



正しい文章の読み方を知らずに文章読解問題を解いても、なかなか解けるようにはなりません。
まずは正しい文章の読み方をインプットして、それから読解問題を解いてアウトプットすべきです。
国語対策におすすめのオンライン指導!
- 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※国語の読解力強化特化!東大生と1:1対話! - オンライン家庭教師WAM

※対面型個別指導塾に近い指導!
▼あわせて読みたい
>>ヨミサマ。は国語特化で本質的な読解力・思考力を育てられる!料金・特徴は?
▼あわせて読みたい
>>塾は国語の授業も受けるべき!メリットと注意点を元塾教室長が解説!
▼あわせて読みたい
>>読書をして国語の成績を上げよう!ただし読むだけではダメです
【理科】用語暗記と現象の理解から
理科の受験勉強は、用語の暗記と現象の理解からはじめられると良いです。
用語暗記は言葉を覚えるだけでなく、絵や図、写真などと一緒に覚えるようにするとより良く理解できますし、忘れにくいです。
化学や物理の分野では、どのような現象が起きているのかを理解することが大切です。
文字情報だけで現象の理解をすることは難しいので、写真や動画で確認したり、授業で先生に噛み砕いて説明してもらったりすると身につきやすいです。
▼あわせて読みたい
>>【中学生】理科の効果的な勉強法!定期テストでも入試でも得点源にできる!
【社会】用語暗記と歴史の流れから
社会の受験勉強は、用語暗記と歴史の大まかな流れの理解からはじめられると良いです。
地理は、地図や写真も交えて用語や地名を暗記するようにすると良いです。
歴史は、資料や写真も交えて出来事や人物名を暗記しながら、歴史の流れを把握するようにすると良いです。
公民は、表やグラフを参照しながら、用語や仕組みの暗記ができると良いです。
受験勉強をはじめるときにやっておくべきこと
ここからは、受験勉強をはじめるときに、事前にやっておくと良いことを解説していきます。
受験勉強をスタートさせてから、同時並行で進めていっても大丈夫です。
受験勉強をはじめるときにやっておくべきこと
一つひとつ解説します。
準備1:受験の制度や仕組みを調べる
受験勉強をはじめるときは、受験の制度や仕組みを調べておくことが大切です。
受験は情報戦でもあるからです。
たとえば、推薦入試では内申点(通知表の評定)が重要であることは広く知られていますが、実は内申点は公立高校の一般入試でも重要になります。
都道府県によってルールは異なりますが、公立高校の一般入試の合否は、試験本番の点数と内申点の合計で決められるからです。
▼この表は横にスクロールできます。
| 項目 | 東京都 | 神奈川県 (第1次選考) |
千葉県 | 愛知県 | 大阪府 |
| いつの通知表か | 中3の2学期 | 中2の学年末 中3の2学期 |
中1の学年末 中2の学年末 中3の2学期 |
中3の2学期 | 中1の学年末 中2の学年末 中3の2学期 |
| 内申点の 計算方法 |
5教科の評定 +実技4教科の評定×2 |
中2の9教科 +中3の9教科×2 |
中1の9教科 +中2の9教科 +中3の9教科 |
中3の9教科×2 | 中1の9教科×2 +中2の9教科×2 +中3の9教科×6 |
| 内申点の満点 | 65点 | 135点 | 135点 | 90点 | 450点 |
| 学力試験の満点 | 500点 | 500点 | 500点 | 110点 | 450点 |
| 配点比率 (学力試験:内申点) |
学力試験を700点に換算 内申点を300点に換算 比率7:3 |
各高校による (例1)6:4 (例2)7:3 |
各高校による (例1)500:135 (例2)500:270 |
各高校による (例1)11:9 (例2)22:9 |
各高校による (例1)7:3 (例2)4:6 |
※参考
令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について|東京都教育委員会ホームページ
公立高校入学者選抜制度の概要 神奈川県ホームページ
令和6年度千葉県県立高等学校第1学年入学者選抜要項について/千葉県
愛知県公立高等学校入学者選抜 - 愛知県
大阪府/令和6年度公立高等学校入学者選抜
あらかじめ受験の制度やルールを知っておくと、効果的な受験対策の取り組むことができますし、いろいろな選択肢を考えておくこともできます。
▼あわせて読みたい
>>高校入試の内申点とは?重要性・計算方法・上げ方を徹底解説!
▼あわせて読みたい
>>受験は情報戦でもある!情報を制する者は受験を制す!
準備2:志望校を決める
受験勉強をはじめるときは、志望校を決められると良いです。
具体的な目標があったほうが、勉強を頑張ることができるからです。
憧れでも仮決めでも良いので、具体的な学校を決められると有意義です。
志望校は、今の成績で行けるかどうかで決めるのではなく、子ども本人が通いたいと思えるかどうかで決めるべきです。
今の成績は、努力次第でこれから伸ばしていくことができるからです。
本人が通ってみたいと思う学校を目標にして、その目標に向けて努力することができると、成績を大きく伸ばすことができます。
将来のことを考えることも大事
志望校選びでは、子ども自身が、自分の将来のことを考えることも大事です。
高校受験は、子どもにとっても人生の大きな岐路になるからです。
この機会に、自分が将来何をしたいのか、どのような人になりたいのかを考えられると良いです。
将来の夢を見つけられると、夢を叶えるために努力できるようになります。
親子で子どもの将来について対話する時間を作って、勉強する目的を見つけられると良いです。
▼あわせて読みたい
>>将来の夢が決まらない?夢の見つけ方11のポイント
▼あわせて読みたい
>>将来の夢がない子どもに見てほしい動画5選【保護者の方にも見てほしい】
準備3:模試や学力テストを受ける
受験勉強をはじめるときは、模試や学力テストを受けてみることをおすすめします。
模試や学力テストを受けると、志望校までの距離を測れるだけでなく、対策すべき苦手分野や弱点を見つけることもできるからです。
模試を受けると、点数や志望校判定ばかり注目してしまいますが、成績表をよく見ると、もっと細かいデータまで分析することができます。
子どもの苦手分野や、今すぐ取り組むべきことなどがアドバイスとして記載されていることも多いので、これからの勉強に役に立ちます。
何からはじめるか迷ったときこそ、模試や学力テストを活用できると良いです。
▼あわせて読みたい
>>模試の復習のやり方・ノートの作り方は?模試の最強活用法8つのポイント
▼あわせて読みたい
>>定期テストはできるのに模試の点数が取れない!たった1つの理由と4つの対策方法
準備4:おおまかな学習計画を考える
受験勉強をはじめるときは、大まかな学習計画を考えておけると良いです。
受験にはタイムリミットがあるからです。
いつまでに何をすべきか、大まかに決めておけると、あとで後悔しません。
一般的な高校受験対策の学習スケジュール
多くの中学生は、次のようなスケジュールで高校受験対策に取り組んでいきます。
中3の1学期まで
学校の授業と定期テスト対策中心
中3の夏休み
これまでの学習内容の総復習+2学期の学習内容の先取り
中3の2学期
学校の授業と定期テスト対策+中3全範囲の先取り学習
中3冬休み以降
過去問演習や実践演習中心
難関高校を目指す場合の高校受験対策の学習スケジュール
難関高校合格を目指す場合は、先取り学習を活用しながら、一般的なスケジュールを前倒しで進めていきます。
中2の3学期まで
学校の授業と定期テスト対策中心+中3学習内容の先取り学習(英語と数学中心)
中2の冬休み+新中3の春休み
これまでの学習内容の総復習+中3学習内容の先取り学習
中3の1学期
学校の授業と定期テスト対策+中3全範囲の先取り学習
中3の夏休み
これまでの学習内容の総復習+過去問演習や実践演習
中3の2学期
学校の授業と定期テスト対策+過去問演習や実践演習
中3の冬休み以降
過去問演習や実践演習中心
▼あわせて読みたい
>>高校受験の受験勉強はいつから本気を出せば間に合うのか【元塾教室長が解説!】
▼あわせて読みたい
>>【中学生】いつから塾に通う?高校受験対策の入塾のタイミングは費用と効果のバランスが大事!
準備5:学習習慣を身につける
受験勉強をはじめるときは、事前に学習習慣を身につけられていると良いです。
勉強は、毎日の積み重ねが大切だからです。
受験勉強をはじめるときは、「何をやるか」よりも、まずは「やってみる」ことが重要です。
学習習慣が身についていなければ、何をやっても続きません。
勉強する時間についてのルール作りをしたり、目標を立てたりして、まずは学習習慣を身につけましょう。
▼あわせて読みたい
>>勉強のやる気を出す26のテクニックとモチベーションの上げ方
受験勉強は普段の勉強が大事
学校での普段の勉強と受験勉強を別々のものとして分けて考えてしまう中学生も多いのですが、受験勉強においては、普段の学校の勉強こそが大事です。
受験勉強は、学校での勉強の延長線上にあるからです。
普段の勉強をおろそかにしていては、受験勉強はできません。
ここからは、受験勉強で成果を出すための、普段の学校の勉強の取り組み方を解説します。
普段の学校の勉強の取り組み方
一つひとつ解説します。
取組み方1:学校の授業をフル活用する
受験勉強で成果を出すためには、学校の授業をフル活用することが重要です。
一つひとつの授業内容の理解の積み重ねが、入試に対応できる学力になっていくからです。
授業中は先生の話を聞いて板書を写すだけでなく、授業に積極的に参加して、少しでも多くのものを吸収できるように意識できると良いです。
予習・復習に取り組む
学校の授業は、予習と復習に取り組むべきです。
最低でも、復習には取り組むべきです。
勉強は、同じ学習内容を繰り返すことで定着するからです。
授業を1回受けただけでは学習内容が定着しないので、予習・復習で繰り返して定着させていきます。
予習・復習に取り組んで、1回1回の授業内容をしっかりと定着させていけば、受験勉強に対応できる基礎力を着実に積み上げることができます。
また、授業の予習に取り組むと、授業中に発表などで活躍できる可能性が高くなり、内申点(通知表の評定)アップも期待できます。
取組み方2:課題や宿題は必ず取り組む
受験勉強で成果を出すためには、授業で出された課題や宿題には必ず取り組み、必ず提出することが重要です。
学校の授業は授業だけで完結するわけではなく、宿題や課題にも取り組むことで完結するからです。
宿題をやらなければ、授業に出なかったのと変わりません。
また、提出物は通知表の評定(内申点)にも大きく影響します。
学力アップのためにも、受験戦略のためにも、学校の課題や宿題は必ず提出すべきです。
取組み方3:定期テストは本気で取り組む
受験勉強で成果を出すためには、定期テストに本気で取り組むことが大切です。
定期テスト対策は、勉強の基礎基本を習得するために一番効果が高いからです。
定期テストは出題範囲が狭いうえに、基本的な問題が出題されやすいです。
そのため、定期テスト対策が学習内容の基礎基本の習得につながり、基礎基本の積み重ねが入試に対応できる学力につながっていきます。
定期テスト対策と受験勉強は別のものとして分けて考えるのではなく、効果的な受験勉強に取り組むための準備として、定期テスト対策に本気で取り組むことが大切です。
▼あわせて読みたい
>>定期テストで点数を取れない3つの理由と8つの対処法【元塾教室長が解説!】
▼あわせて読みたい
>>定期テストで450点取って高校受験でも勝つための勉強法
▼あわせて読みたい
>>定期テストはできるのに模試の点数が取れない!たった1つの理由と4つの対策方法
▼あわせて読みたい
>>定期テスト成績アップのためにすべき親のサポート【元塾教室長が解説!】
受験勉強で何をすべきか迷ったら
受験勉強で何をすべきか迷ったときは、塾や通信教育などの学習サービスや、教材などを利用することをおすすめします。
受験や勉強にはいろいろな要素が絡まり合っているため、ご家庭だけでは解決できないことも多いからです。
受験勉強のために利用できる学習サービス・教材としては、おすすめ度順に次のようになっています。
おすすめ度順学習サービス・教材
おすすめ1:学習塾
受験勉強に取り組むのであれば、塾に通うのが一番おすすめです。
塾は勉強面だけでなく、受験面でも手厚くサポートしてもらえるからです。
塾は「授業がわかりやすい」という点にばかり注目されますが、他にも通うメリットはたくさんあります。
塾のメリット・デメリット
▼この表は横にスクロールできます。
| メリット | デメリット |
| ◯ 学習習慣を身につけられる ◯ 苦手克服に取り組める ◯ 学校の授業を深く理解することができる ◯ 定期テスト対策に取り組める ◯ 受験対策に取り組める ◯ 部活と勉強を両立させやすい ◯ 自習室を使える ◯ 受験情報が多い |
✕ 費用の負担が大きい ✕ 送迎の負担が大きい ✕ 好きなように勉強に取り組めない |
費用負担のことを考える必要はありますが、できるだけ早期から塾を利用できると、受験勉強には有利です。
通うか通わないか決まっていない場合でも、複数の塾の体験授業を受けてみて、塾のリサーチをしておけると良いです。
▼あわせて読みたい
>>【中学生】いつから塾に通う?高校受験対策の入塾のタイミングは費用と効果のバランスが大事!
▼あわせて読みたい
>>塾の体験授業って何をする?上手な活用方法とメリットを元塾教室長が解説!
中学生におすすめの個別指導塾
- 【森塾】

※先生1人に生徒2人まで!1科目+20点の成績保証制度! - 【個別教室のトライ】

※完全1対1のマンツーマン個別指導塾! - 個別を超えた「子」別指導【坪田塾】

※映画『ビリギャル』のモデルとなった自習力を伸ばす塾! - 個別指導の明光義塾

※対話型授業!レベルに応じた10段階学習法!
学習塾比較表
▼この表は横にスクロールできます。
| 塾名 | 公式サイト | エリア | 指導タイプ | 料金 | 特徴 | 体験授業 |
| 森塾 | 【森塾】 |
関東 静岡 新潟 |
個別指導 |
週1回、月3回授業
|
|
▼最大1ヶ月無料の体験授業に申込む 【森塾】 |
| 個別指導塾WAYS | 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |
関東 近畿 |
個別指導 |
1コマ120分
|
|
▼120分の無料体験指導に申込む 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS |
| 個別教室のトライ | 【個別教室のトライ】 |
日本全国 | 個別指導 |
1コマ120分
|
|
▼無料体験に申込む 【個別教室のトライ】 |
| 坪田塾 | 個別を超えた「子」別指導【坪田塾】 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 愛知 兵庫 大阪 |
個別指導 |
1時間あたり1,530円~2,736円 |
|
▼無料体験に申込む 個別を超えた「子」別指導【坪田塾】 |
| 明光義塾 | 個別指導の明光義塾 |
日本全国 | 個別指導 |
週1回税込み
|
|
▼無料 >>無料体験に申込む |
| スクールIE | スクールIE | 日本全国 | 個別指導 |
週1回税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 京都 大阪 兵庫 福岡 |
個別指導 |
1コマ80分
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 湘南ゼミナール | 湘南ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
集団指導 |
税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 臨海セミナー | 臨海セミナー | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
集団指導 |
税込み
|
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| 栄光ゼミナール | 栄光ゼミナール | 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 宮城 京都 |
集団指導 | 教室によって異なる |
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
| Z会進学教室 | Z会進学教室 | 東京 神奈川 埼玉 大阪 兵庫 京都 奈良 静岡 宮城 |
集団指導 | コースによって異なる |
|
▼無料 >>体験授業に申込む |
▼あわせて読みたい
>>中学生の塾の選び方!失敗しないための11のポイント!
▼あわせて読みたい
>>個別と集団を徹底比較!子どもに向いている塾はどちらか【元塾教室長が解説!】
▼あわせて読みたい
>>失敗しない個別指導塾の選び方!9つのポイント
▼あわせて読みたい
>>集団指導の塾の選び方!失敗しないための15のポイント【元塾教室長が解説!】
教科特化ならオンライン家庭教師
数学や国語などの教科特化で受験対策対策に取り組みたい場合は、オンライン家庭教師・オンライン個別指導塾がおすすめです。
教科特化のオンライン指導であれば、比較的安く、専門の講師にマンツーマンで指導してもらうことができるからです。
教科特化型の学習塾には、対面指導の塾も存在しますが、都市部にしかなく、費用も非常に高額になることが多いです。
一方で、オンラインであれば、どこに住んでいても専門の講師の指導を受けることができます。
オンライン家庭教師の特徴
- マンツーマン授業のわりに料金が安い
- 全国の講師から子どもに合った講師を探せる
- どこに住んでいても教科特化の指導を受けられる
▼あわせて読みたい
>>オンライン家庭教師の9つのデメリット!対面や塾のほうが良い?
おすすめの特化型オンライン指導!
- 「数強塾」オンライン数学克服塾〈プロ講師〉

※数学特化!プロ講師によるマンツーマン授業! - 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※国語の読解力強化特化!東大生と1:1対話!
各オンライン家庭教師・オンライン個別指導サービスについては、『オンライン家庭教師おすすめ10選!元塾教室長が徹底比較!』で詳しく解説しています。
-

-
オンライン家庭教師おすすめ10選!元塾教室長が徹底比較!
オンライン家庭教師はわかりやすい授業だけでなく、特徴的なサービスを提供している場合が多いです。料金だけで比較するのではなく、利用目的に合わせて子どもに合ったサービスを選べると、学力を伸ばすことができます。
続きを見る
おすすめ2:タブレット学習教材
受験勉強に取り組むのであれば、タブレット学習教材もおすすめです。
最近のタブレット学習教材には、AIが搭載されている教材が多く、効率よく勉強に取り組むことができるからです。
演習教材だけでなく、映像授業がついているサービスも多く、インプット学習にも活用することができます。
費用も学習塾と比べると非常に安いので、無理なく利用することができます。
一方で、タブレット学習教材を子どもに与えただけではなかなか勉強に取り組めない中学生も多く、保護者の方のサポートが必要になることが多いです。
タブレット学習教材の特徴
- 料金が安い
- AIによって演習を効率化
- その場で採点され、すぐに復習に取り組める
- 保護者の方のサポートが必要
▼あわせて読みたい
>>タブレット教材の8つのメリット・デメリットを元塾教室長が解説!
高校受験対策におすすめのタブレット教材
- 【進研ゼミ中学講座】

※都道府県別の対策にも取り組める! - Z会の通信教育 中学生コース

※難関高校の受験対策にも取り組める! - 塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】

※苦手克服に特化!担当コーチがつく!
中学生向けのタブレット学習教材については、『中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!』で詳しく解説しています。
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!
この記事では、中学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。
続きを見る
おすすめ3:基礎固めができる参考書・問題集
受験勉強に取り組むのであれば、基礎固めができる参考書や問題集を活用するのも良いです。
参考書や問題集は1冊1,000円から2,000円程度のため、費用がほとんどかかりません。
一方で、参考書や問題集を子どもに買い与えただけでは取り組めません。
中学生が自分の力だけで勉強に取り組むのは難しいからです。
学習計画を立てたり、学習進捗をチェックしたり、家庭内のルールを作ったりと、保護者の方がサポートをしてあげる必要があります。
また、参考書を利用しての勉強は、文字情報中心の勉強になってしまうのも大きなデメリットです。
参考書・問題集の特徴
- 格安
- 文字情報中心の勉強になる
- 保護者の方の手厚いサポートが必要
まとめ
それでは、高校受験の受験勉強は何をすべきかについての解説をまとめます。
結論
受験勉強は、基礎固めからはじめることが大切です。
受験勉強をスムーズにスタートさせるためには、普段の勉強を大事にすることが重要です。
受験勉強でやるべきことを大きく4つのステップで分けると、次のようになります。
受験勉強でやるべきこと
- 授業を受けて知識をインプットする
- 問題演習でアウトプットする
- 定期的に復習をして定着させる
- 過去問を解いて傾向を研究する
高校受験の受験勉強は何からはじめるべきか、教科ごとに解説しました。
【教科別】受験勉強は何からはじめるか
- 【英語】英単語・英熟語・英文法から
- 【数学】計算練習から
- 【国語】漢字・古文単語・文法と読解方法を知るところから
- 【理科】用語暗記と現象の理解から
- 【社会】用語暗記と歴史の流れから
受験勉強をはじめるときに、事前にやっておくと良いことを解説しました。
受験勉強をはじめるときにやっておくべきこと
- 受験の制度や仕組みを調べる
- 志望校を決める
- 模試や学力テストを受ける
- おおまかな学習計画を考える
- 学習習慣を身につける
受験勉強で成果を出すための、普段の学校の勉強の取り組み方を解説しました。
普段の学校の勉強の取り組み方
- 学校の授業をフル活用する
- 課題や宿題は必ず取り組む
- 定期テストは本気で取り組む
受験勉強のために利用できる学習サービス・教材としては、おすすめ度順に次のようになっています。
おすすめ度順学習サービス・教材
今回の記事が、お子様がスムーズに受験勉強をスタートさせて、志望校に合格するための学力を身につけていくための参考としていただければとてもうれしいです。
中学生におすすめの個別指導塾
- 【森塾】

※先生1人に生徒2人まで!1科目+20点の成績保証制度! - 【個別教室のトライ】

※完全1対1のマンツーマン個別指導塾! - 個別を超えた「子」別指導【坪田塾】

※映画『ビリギャル』のモデルとなった自習力を伸ばす塾! - 個別指導の明光義塾

※対話型授業!レベルに応じた10段階学習法!
おすすめの特化型オンライン指導!
- 「数強塾」オンライン数学克服塾〈プロ講師〉

※数学特化!プロ講師によるマンツーマン授業! - 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※国語の読解力強化特化!東大生と1:1対話!
高校受験対策におすすめのタブレット教材
- 【進研ゼミ中学講座】

※都道府県別の対策にも取り組める! - Z会の通信教育 中学生コース

※難関高校の受験対策にも取り組める! - 塾に通わず自宅で学習!自分のペースで学習できる!【すらら】

※苦手克服に特化!担当コーチがつく!
国語対策におすすめのオンライン指導!
- 国語特化のオンライン個別指導【ヨミサマ。】

※国語の読解力強化特化!東大生と1:1対話! - オンライン家庭教師WAM

※対面型個別指導塾に近い指導!
-

-
オンライン家庭教師おすすめ10選!元塾教室長が徹底比較!
オンライン家庭教師はわかりやすい授業だけでなく、特徴的なサービスを提供している場合が多いです。料金だけで比較するのではなく、利用目的に合わせて子どもに合ったサービスを選べると、学力を伸ばすことができます。
続きを見る
-

-
中学生におすすめのタブレット学習教材6選!目的別に元塾教室長が徹底比較!
この記事では、中学生におすすめのタブレット学習教材を徹底比較しています。
続きを見る